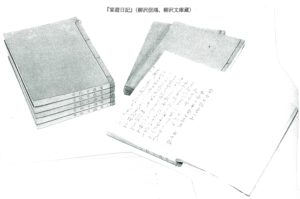次に検討するべきなのは、ポルトガルのカルタが日本に伝来した際の中国とのかかわりである。日本では、カルタは十六世紀にポルトガル船の船員によってもたらされたとする直接伝来説が圧倒的に支配的である。だが、この、カルタがポルトガル人から直接に伝来したという通説に疑問を持った者が一人いた。長崎市の永見徳太郎[1]である。永見は明治二十三年(1890)に長崎の豪商の家に生まれ、十分な教育を受けて教養に富み、この地を訪れた多くの作家、画家等とも交友のあった名士で、郷里の長崎への思いが強く、大正期 (1912~26)から昭和前期 (1926~45)にかけて南蛮美術の研究家で文筆家でもあった。永見は郷土長崎の江戸期の文化に詳しく、早くから南蛮文化の遺品を蒐集してコレクターとして第一人者であり、その学識も豊かであった。今日の南蛮文化研究の礎石を現地長崎で築いたのは永見である。
永見は昭和十五年(1940)の雑誌論文「ウンスン・カルタは支那版にもあり」[2]でカルタは中国経由であるとする間接伝来説を表明した。すなわち、「このウンスン・カルタ研究に関しては、幾多先輩の考證があるが、何れも、歐洲より直接我國へ渡つたのだとしてある。然し私は、ヨーロッパ船の交通により彼らの物質をもたらす以上、地形と歴史より見て、印度、南洋、支那を經ねばならぬとして居る。其等東洋諸國より、歐洲に向けられたり、或は又、逆輸入になつたものも物によつてはあるのではないかと思ふ。‥‥舶来文明品の殆んどの種類が、日本に擴められる前に、必ずと言つても良いように、彼支那で手なづけられたのであつた。」というのである。
永見がこういう信念で長年心がけていたところ、論文執筆の直前のことであるが古い版木を用いた硯箱を入手できた。それが中国製のウンスン・カルタの版木の再利用品であり、三十四枚分のカードの図像が見える。この硯箱の外箱には、日本人の手跡で「大明萬暦かるた硯箱」と古風に書かれている。萬暦は中国の年号であり、西暦で1573年から1619年までであり、日本の年号では天正(1573~92)、文禄(1592~96)、慶長(1596~1615)、元和(1615~24)というカルタ草創の時期にあたる。永見はこの史料を紹介することで、「支那にあつても、ウンスン・カルタが製作された証據を挙げ、その方面の研究資料としたい」としている。
この永見の着想は、大正十二年(1913)の新村出の『南蛮更紗』所収の論文「賀留多の伝来と流行」[3]以降すでに確立されたかに見える通説、ポルトガル人からの直接伝来説にたった一人で挑む、中国経由の間接伝来説となる。永見がここで支那製と見た「大明萬暦かるた硯箱」(以後は「カルタ版木硯箱」と略称する)は、その後兵庫県芦屋市の資産家でカルタ史のもっとも優れた研究者であった山口吉郎兵衛の手に渡り、中国製ではなく江戸時代の日本製、「彫刻も大分粗末で製作年代の降る」天正カルタの版木の硯箱と鑑定され、山口の著書『うんすんかるた』冒頭に、図版「天正カルタ版木 拓摺実寸複製 硯箱蓋表面及側面図」として紹介されているので今日でも内容が分かる[4]。こうした山口の鑑定にもかかわらず、永見は南蛮文化に詳しい蒐集家、研究者であり、その長年の研究の中から出された中国経由伝来説は軽々しく無視できない。少し詳細に検討してみたい。
[1] 永見徳太郎の生涯は、大谷利彦『長崎南蛮余情 永見徳太郎の生涯』、長崎文献社、昭和六十三年。同『続長崎南蛮余情 永見徳太郎の生涯』、長崎文献社、平成二年に詳しい。
[2] 永見徳太郎「ウンスン・カルタは支那版にもあり」『浮世絵界』昭和十五年一月一日号、五頁。
[3] 新村出「賀留多の伝来と流行」『南蛮更紗』、改造社、大正十三年、一〇三頁。
[4] 山口吉郎兵衛『うんすんかるた』リーチ(私家版)、昭和三十六年、巻頭口絵三一頁。山口は、この硯箱の外箱やそこに日本人の手跡で「大明萬暦かるた硯箱」と古風に書かれてことについては沈黙している。その理由は分からない。あるいは、山口が入手したときには故意か偶然か、外箱が除かれていたのであろうか。