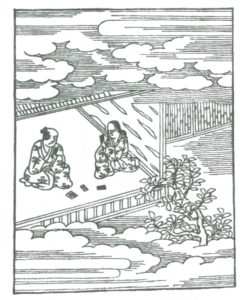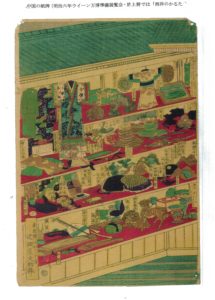江戸時代初期の京都、大坂などには、「合せカルタ」という遊技法があった。だが、その存在を裏付ける史料は少ない。文献では、江戸時代初期(1603~52)の史料で、この遊技法であると特定されるものは未発見であり、寛永年間(1624~44)の末年に刊行された著者不明の『仁勢物語』がこれを扱った最古のものと推定される。これについて私は『ものと人間の文化史173 かるた』で細かく紹介したので、それを再録しよう。
寛永十六年(1639)頃に成立し、寛永年間(1624~44)の末年に刊行された作者不詳の書物が『仁勢物語』[1]である。題名が『伊勢物語』もどきであるところに端的に表されているように、全編が『伊勢物語』のもじりで、高尚な貴族文化の描写を各々の段ごとに江戸時代初期(1603~52)の庶民の卑俗な日常生活に巧みに置き換えている。そのもじりの仕方は極めて優秀で、パロディとしては最高の評価に値する。その中で、カルタに関するのは『伊勢物語』第百十九段に関わる部分である。
『伊勢物語』では、この段は、「むかし、女の、あだなる男の形見とてをきたる物どもを見て、形見こそ今はあだなれこれなくは忘るるときもあらましものを」である。その趣旨は、女が、浮気な昔の恋人の男が別れる際に形見だとして残していって捨てかねて持っている品物を見ながら、この形見は今ではもうあだになっていて、これがなければ昔のことを忘れることもできるのに、と思っているということである。
これが『仁勢物語』になるとこうなる。「をかし、女はあさもつ。男は、そうたもてり。はやく打ちすてたりけるを見て、かちこそは今はあだなれ是なくはそうたはよもにあらまし物を」。その趣旨はこうなる。「おかしい。カルタをしていて、女が手中にアザを持っていた。相手の男はソウタを持っていたが、早い段階で打ってきたので、女が言った。今、ソウタを打って得られた(このトリックでの)勝ちが仇になりましょう。これでアザで勝てることになりました。このように打ってくださらなければ、アザに打ち勝つソウタが四方の参加者のどなたの手中に隠れているのかが分らなくてアザの打ち時に困っておりましたのです」。こうしたストーリーだとすると、カルタの遊技で、「ハウの一」のカードである「アザ」は切り札だが、「ハウの十」、「ハウのソウタ」(別名「釈迦十」)も切り札で、「ソウタ」のほうが「アザ」よりも強いことになる。これはカルタ札の中で常に切り札になるのが「ハウの二」つまり当時の呼称で「青の二」と「釈迦十」「アザ」で、この順番で強弱がある「合セ」の遊技法である。「ヨミ」や「メクリ」ではこうはならない。「合セ」の遊技法が笑い話の種になっているのだから、江戸時代初期(1603~52)に「合セ」がごく普通に遊ばれていて、この話のおかしさが多くの人に伝わることを示している。
次に、江戸時代前期(1652~1704)になると、貞享年間(1684~88)の『雍州府志』[2]と『鹿の巻筆』[3]がこの遊技法に言及した最も古い例である。このうち、黒川道祐著の『雍州府志』は、「合(アハセ)」と名称を特定し、カルタ札の「紋」を合せる遊技という説明が具体的であり、第一級の史料と思われる。
ところが、この文献については、山口吉郎兵衛が『うんすんかるた』で、これは「めくりカルタ」の祖型の「プロトめくり」を指しており、「紋」を合わせるは「数」を合わせると書くべきところの誤記であるとする理解、すなわち誤記説を示した。それ以来、それが確立した通説として君臨していた。これに対して私は、昭和末年(1985~89)から平成年間初期(1989~98)にかけて、同書の記述を素直に読めば「紋」を合わせるトリック・テイキング・ゲームの説明として首尾一貫していて誤記ではないという説を提起した。その後、平成年間(1989~2019)にそこに介入したのがネット上の江戸カルタ研究室(以下、研究室)で、基本的には「めくりカルタ」の前身、「プロトめくり」の「数」を合わせる遊技法であるという誤記説に近い認識を示すとともに、『雍州府志』が「紋」を合わせると記述した場合の「紋」は紋標の意味ではなく、模様のような意味であり、「紋」を合わせるという表記は数の同じ札を合せるという語義であると解されるので誤記ではないと主張した。そこでは、『雍州府志』をどう理解するのかが、「合せ」という遊技法の発祥を解明する鍵となっている。ここでは、『雍州府志』の詳細な解読を示して、それを通じて「合せ」というカルタ遊技の実体を解明したい。
[1]「仁勢物語」高山高至『校本仁勢物語』(和泉古典文庫6)、和泉書院、平成四年、一七四頁。『假名草子集』下巻(『日本古典全集』第百一回配本)、朝日新聞社、昭和三十七年、三四八頁。
[2] 立川美彦『訓読 雍州府志』、臨川書店、平成九年、四三六頁。
[3] 「鹿の巻筆」『江戸笑話集』(日本古典文学大系第百巻)、岩波書店、昭和四十一年、一六四頁。