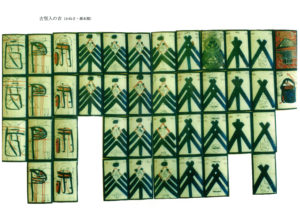大正年間(1912~26)の取り締まり当局による名古屋地域の博奕の報告書[1]では、花札を使う「四一(シッピン)」、別名「金吾」「ドサリ」という遊技が記録されている。私は、この遊技法が往時のきんごカルタの遊技法を最もよく留めているものと考えている。報告書によると、この遊技では花札から「桐」のカス札三枚を抜いて四十五枚にして使われている。この枚数は、四十枚が一組のかぶカルタでは札が不足して実施できないから、四十八枚が一組のきんご札を使っていた江戸時代前期のきんごカルタの遊技法を受け継いだものであろうと推測させる。そこで、使用札を花札から天正カルタに戻したと想定してこの遊技法の手順を説明しよう。次のような展開になる。
- 遊技に参加する者は何人でも良い。「親」と「側」に分かれ、各々が同額の賭金を出す。
- 「親」が「側」一人につき二枚ずつ、裏面を上にして札を配る。
- 「側」は自分に配られた札を見て、良い方を残し、もう一方は捨てる。二枚とも良くないときは二枚を捨てて勝負から離脱する。
- 「親」は自分の前に札を一枚置く。
- 「親」は一番右に居る「側」に札を配る。「側」は紋標数の合計が十五になるまでは何枚でも要求できる。
- 紋標数の合計が十五になった時を「金吾の本取り」と呼ぶが、「側」は「取り」と宣言して伏せてある最初の一枚を起して証明して勝ちとなり、賭金を全部取る。勝負はここで終わり、次回に移る。
- 「側」の札の紋標数の合計が十五を超えてしまったときは「ばれた」と言って賭金も札も投げ出して敗退する。
- 「側」は、紋標数の合計が十一以上であれば、札の配布を止めて次の「側」に順番を譲ることができる。その場合、紋標数の合計十一を「うんすん」、十二を「二ぞう」、十三を「三ずん」、十四を「四すん」と呼ぶ。この四者の中では、「四すん」が最強で、「うんすん」は最弱である。
- 二番目以降の「側」が順次同じ所作を行う。先行する「側」が「取り」になればそこで勝負は終了であるから、順位が遅れる「側」はノーチャンスで敗退になる危険性がある。
- いずれの「側」も「取り」にならず、止めた者がいる状態ですべての「側」の所作が完了したら、「親」が自分でも札を引く。紋標数の合計が十五であれば「取り」、十六以上は「ばれ」であり、十四以下で止めたときは残っている「側」と札を開け合い、最も高目のものが勝ちで賭金を全部獲得する。「親」と「側」が同点の場合は「親」の勝ちとし、「側」と「側」が同点の場合は右側の「側」が勝ちとする。
以上の流れであるが、いくつかの特例がある。
- 紋標数四の札と一の札を得たときは「四一(しっぴん)」であり、「金吾の本取り」と同様に、そこで勝ちが確定して勝負が終わる。
- 紋標数九の札と一の札を得たときは「九役」、別名「九一(クッピン)」であり、その後に「金吾の本取り」か「四一」が出ないで最後の見せ合いになった時は「四すん」以下に勝つ。
- 紋標数五の札と一の札を得たときは「五役」であり、見せ合いで「九役」(「九一」)には負けるが「四すん」以下には勝つ。
- 紋標「ハウ」の一の札、つまり「あざぴん」は「消えぴん」であり、一と数えることも、ゼロと考えることも、一・五と考えることもできる。紋標数の合計が十六になった時にこの札が入っていれば、ゼロと数えて「金吾」になる。見せ合いになった時にこの札が入っていれば一・五と数えて、同点の者に勝つことになる。
- 紋標「ハウ」の六の札は「四五六」と呼ばれ、本来は六に数えるが、五に数えても、四に数えても良い。紋標数の合計が十七になった時でも、この札があれば四に数えて「金吾」になるし、十六の時には五に数えて「金吾」になる。
- 参加者が四人以上、つまり「側」が三人以上いるときは、末席の参加者は自分の順番が来る前に他の「側」に「金吾の本取り」や「四一」がでて勝負が終わってしまうノーチャンスの不利益が強いので、この者に順番が回ってきた時は、紋標数の合計が十六であっても「金吾の本取り」として扱う。これを「乙十六」と呼ぶ。
この遊技は別名が「どさり」である。この遊技では勝者は賭金を全部獲得するのであるが、それを懐中にするのではなく場に残して、自分が「親」になり、次回での賭金とする。これに対して新たな勝負での「側」は、その賭金の山の下に手持ちの札を差し込んで、「親」と差しで総額の勝負を挑むことができる。この場合、その「側」が勝てばすべての賭金を獲得できるが、負けた場合は同額を差し出して賭金の山に積まなければならない。こうして賭金を差し出すことを「どさる」という。遊技名「どさり」の語源である。この「どさり」により、賭金の額が倍倍ゲームで急速に大きくなり、遊技の場がヒートアップする。これが過熱状態にならぬよう、場を冷やすために、同じ「親」に対する二度目以降の挑戦は、賭金の山の半額までと制限される。
以上が「四一」の遊技法である。『博奕仕方風聞書』で紹介され、今日まで伝わっている「きんご」の遊技法は、親が最初に子に配る札は一枚で、勝負に「金吾の本取り」役がなく、「四一」ができてもそこで打ち切りではなく「九一」と同じく最後の見せ合いの際に最強に扱われる役であるなど、現代のかぶカルタに近いが、名古屋の「四一」のほうがこれよりも大分古い印象がある。
[1] 松坂広政、高木常七「賭博に関する調査」『司法資料』第百二十一号、司法省調査課、昭和二年、五八頁。