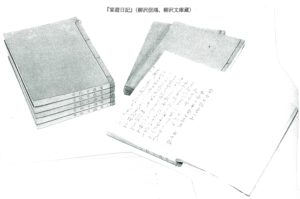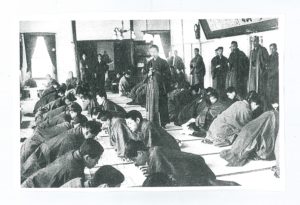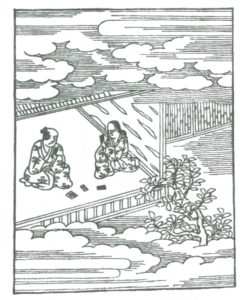元禄年間(1688~1704)以降に生じたと思われる絵合せかるたのデュプリケイション、四枚絵合せかるたの誕生がもたらした大きな変化についてまとめておきたい。
四枚絵合せかるたは、一つの紋標が四枚の札で構成されており、そのうちの一枚の手札で場札として展開されている同じ紋標の札を釣り取るゲームである。その際に、札の図像に精粗の差を設け、また、札に固有の点数を付けて、選択に意味を持たせるような工夫が生じた。今日まで残されている物品史料の例で言えば、高点札は四枚の内の一枚で、残りの三枚の札は皆十分の一の配点であるのが標準的である。
こうして、同一の紋標の札の中で「役」を構成する札ないし高点の札を競って釣り取る四枚絵合せかるたが成立した。その代表的な例が、草花を描いた花合せかるたである。この種類のかるたについて明記している、現存するもっとも古い文献史料である江戸時代中期(1704~89)、安永二年(1773)十二月の柳沢信鴻『宴遊日記』[1]には、「儀助ニ花合せ骨牌お隆貰ふ」とある。だ。儀助は信鴻の側近の臣下で、お隆は信鴻の最愛の側室である。領国の伊賀上野からの旅の土産であるから、その地のものか、領国近くの京都で求めたものかであろう。主君の側室への土産になるのだから、高級な手描き、手作りのカルタであったと思われる。ここで興味あるのは、呼称の表記が「花合せ骨牌」であって「花かるた」ではないことである。当時の京都、大坂では「虫合せ骨牌」や「鳥合せ骨牌」など、絵合せかるたが多種多様に存在していて、「花合せ骨牌」はそうした絵合せかるたの一種で、女性が好みそうな図像のものであったのであろう事情を推測させる。
[1] 柳沢信鴻『宴遊日記』(藝能史研究會編『日本庶民文化史料集成』第一三巻)、三一書房、昭和五十二年、四八頁。