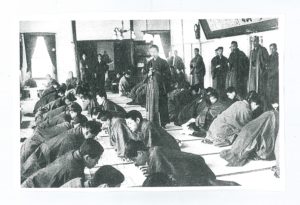絵合せかるたの魅力は何といっても二枚の合い札を並べたときに出現する図像の楽しみにある。「源氏物語絵合せかるた」では、光源氏を巡るその巻のストーリーの情景が眼前に現れる。似たような場面での混乱を避けるように巻名が表示される。「譬え絵合せかるた」では、二枚の図像を合わせるとその譬えの意味合いが図像として理解できる。虫尽し、鳥尽し、馬尽し、魚尽し、花樹尽し、草花尽し、花鳥尽し、野菜尽し、日用器材尽し、職人尽し、武具尽しなどの絵合せかるたでは、図鑑の一頁を開いて知識の宝庫を見たような印象が残る。まさに「絵合せ」の語感に合っているが、考えてみれば、そもそも「貝覆」の遊技では、室町時代に貝殻の内側に源氏物語の情景画などを描くようになり、対になる二枚の貝片をうまく合わせて裏返すと、正解を得た喜びとともに情景の図像が出現するのも楽しみであったと思われるのであり、絵合せかるたはこの楽しみをしっかりと受け継いでいると受け止められる。
貝覆の精神を継受したかるたであるという点とともにもう一点貝覆との関係で注目されるのは、絵合せかるた一組の札の枚数である。上記に紹介したように絵合せかるたではほぼ五十対・百枚というのが定型であるように見える。元々貝覆では貝殻の枚数はもっと多くて、室町時代には百八十対・三百六十枚が基準で、三百対・六百枚で一組、あるいは三百六十対・七百二十枚で一組のものもあった。『雍州府志』の「貝」の項でも、「倭俗婦人合貝為遊戯、其法以三百六十之貝左右分之圍並床上空其中央。」(倭俗に女性が貝を合せて遊戯とする。その方法は、三百六十の貝をもってこれを左右に分け、床の上に囲み並べ、その中央を空ける。)と、百八十対・三百六十枚か三百六十対・七百二十枚であることが記されている。
貝覆がこれほど大部のものであると、実際の遊技でこれをすべて畳の上に広げて使おうとすると多量に過ぎるようで、何組かに小分けして使ったものと考えられる。実際、残されている当時の貝覆の遊技図を見ても、通常は多くて数十枚の貝殻が描かれており、三百六十枚や七百二十枚の貝殻を並べているものは見たことがない。『うんすんかるた』では、三百六十対で内側に描く図像が「花鳥」「草花」「源氏絵」「調度品」の四種の主題に分かれている貝覆が紹介されているが、遊技の際には、これのうちいずれかの主題の貝に絞って用いれば手ごろである。四種の図像に分かれるとすると一種は九十対であり、その規模を活かせば遊技がしやすい。それをかるた札に移せば百対で一組の絵合せかるたになるし、半分に縮小すれば五十対で一組の手ごろなものになる。また、『うんすんかるた』では、貝覆の実例の紹介の中で、一組が三百対でその図像が「草花」百五十対、「花鳥」百五十対のものなどを紹介している。のちの時代のものだが、「古今和歌集歌合せかるた」で千対・二千枚を超える規模のものがある。これをすべて畳の上に広げると収拾がつかない。このかるたでは、札自体が最初から「春の歌」「秋の歌」「恋の歌」などに小分けされて小型の内箱に収納されており、その規模で遊技するのに取り出しやすく工夫されている。
実際に残されている物品史料から判断すれば、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の絵合せかるたは五十対・百枚で一組のものが基準であったように見える。例外は、江戸時代中期(1704~89)の百対・二百枚構成の「百句譬えかるた」であるが、この名称は後世の蒐集家による命名であり、元来は、明和年間(1764~72)の大坂の出版記録[1]にある、正続二種の「評判たとへかるた」五十対・百枚と「後編たとへかるた」五十対・百枚の混合、あるいは正続合併の「たとへかるた大全」百対・二百枚であろうと思われる。五十対・百枚が基準であったのは、京都の手描きのかるただけでなく、大坂の木版かるたでも同様であったことが分かる。
一方で、同じく江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の「歌かるた」の類では、『雍州府志』に記載されている五十首一組の「五十人一首名所歌かるた」のように五十対・百枚で一組にしたものもあるが、基本は百対・二百枚であり、『うんすんかるた』にも、「百人一首歌カルタ」のほか、元禄年間(1688~1704)のもので上下句札のいずれにも図像がある「古今集絵入歌カルタ」[2]、同じく元禄年間(1688~1704)のもので上句札に図像のある「古今集春の歌絵入歌カルタ」[3]などの百対・二百枚の「絵入り歌かるた」が紹介されている。当時は、「古今集」の一千首あまりの歌から百首を選んでかるたにしており、「新古今集」から百首を選抜したかるたもある。文字だけの歌合せかるたでも同様であるので、図像の付いたものでも百対・二百枚が一応の基準であったことが分かる。
ただし、この時期にも、貞享年間(1684~88)頃のもので上下句札に図像のある「自讃歌絵入歌カルタ」[4]は百七十対・三百四十枚であり、元禄年間(1688~1704)のもので上下句ともに図像のあるもの二組、下句札にだけ図像のあるもの一組も百七十対・三百四十枚である。同じく元禄年間(1688~1704)の「伊勢物語絵入歌カルタ」[5]では、上下句札ともに図像のあるもの二組、下句札にだけ図像のあるもの一組がいずれも二百九対・四百十八枚である。他方で、「源氏絵入歌カルタ」[6]は五十四対・百八枚であり、「三十六歌仙絵入カルタ」[7]や「女房三十六歌仙絵入歌カルタ」[8]は三十六対・七十二枚である。元禄年間(1688~1704)の「貝合絵入歌カルタ」[9]も三十六対・七十二枚である。要するに歌合せかるたでも、定型は五十対・百枚か、百対・二百枚であり、その他に歌集の構成によって二百九対、五十四対、三十六対のものもあるということである。
[1] 大阪図書出版業組合『享保以後大阪出版書籍目録』、臨川書店、昭和一一年、七〇、九〇頁。
[2] 山口吉郎兵衛『うんすんかるた』、リーチ(私家版)、昭和三十六年、一二九頁。
[3] 山口吉郎兵衛、前引『うんすんかるた』、一三〇頁。
[4] 山口吉郎兵衛、前引『うんすんかるた』、一三二頁。
[5] 山口吉郎兵衛、前引『うんすんかるた』、一三三頁。
[6] 山口吉郎兵衛、前引『うんすんかるた』、一三三頁。
[7] 山口吉郎兵衛、前引注1『うんすんかるた』、一二五頁。
[8] 山口吉郎兵衛、前引注1『うんすんかるた』、一三四頁。
[9] 山口吉郎兵衛、前引注1『うんすんかるた』、一三五頁。