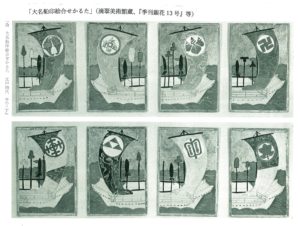そこでは、ページの上部に「二子(にこ)ゝゝと三子(さんこ)にちかきよみがるた 青二(あをに)ひねれば丸二(おかわ)なりけり」という狂歌があり、下部に、男二人、遊女らしい女二人で夜間にカルタ遊技を楽しむ場面が描かれている。場面は、右側の男が右手に四枚の札を持ち、女二人が右手ないし左手に五枚の札を持ち、そのうちの女一人がさらに一枚、「オウルの二」か「オウルの三」に見える札を右手に持って打とうとしている。この女は六枚持っていることになる。もう一人の男は手札を畳んで重ねているので何枚であるのかは明言できないが、図像では四枚程度に描かれている。場には二枚、「ピン」と「青の二」が表を上にして出されている。右側の男の前に三、四枚の札が裏面を上にして積まれている。
この図像をどう解読するかであるが、まず目につくのは、描かれている札の数の少なさである。確認できるのは、手札が四人のものを合わせて十八、九枚、場札二枚、取り札三、四枚、合計二十四、五枚であり、一組四十八枚のカルタを使う遊技としては少なすぎる。紋標「イス」の札を除外して三十七枚で遊技しているとしても読みカルタの遊技場面としては少なすぎる。ここで想定できるのは、見えていない二十枚が取り札として他の遊技者の手元に引き取られていて、それが人物像の陰にあるという事態である。これを四人で合せカルタをしている場面と考えると、すでに六トリックが出されたゲーム中盤で、七トリック目、まだ一トリックしか得ていない右側の男が「ピン」を出し、女が切り札の「青の二」を出して勝負に出て、次の女が「オウルの二」を出して肩透かしをし、もう一人の男が何を出そうかと考慮中という瞬間を描いたものと考えて見ると、多少の札不足が見えるがおおむねは平仄が合う。だから私は、この絵は、同じページに「よみがるた」と書かれていても、実は「合せカルタ遊技」の勝負中盤の場面であると判断している。
この本の制作過程にどういう経緯があったのかは知らない。絵師の西川祐信が勘違いしたのか、彫師が勘違いしたのか、事情はいろいろと推測できるが、いずれにせよこれは「合せカルタ遊技」の一場面である。そこで私は、『ものと人間の文化史173 かるた』で、これを「『合せ』の遊技」の図として紹介した。こうすれば文献史学の人が文句をつけるだろうと予想していたが、早速、江戸カルタ研究室から批判された。
研究室の批判は、同じ頁の上部の狂歌に「よみがるた」と書いてあるのに江橋はなぜ「合せカルタ」の遊技風景だというのか全く理解できないということである。「ただ、間違い無く言えるのは、これは『あわせ』では無く『よみ』の遊技風景を描いたものであるという事です。何故ならば…そこに『よみがるた』と書かれているから[1]。本来ならばこれだけで理由として十分であり、余計な説明は不要な筈ですが、念の為に傍証も示しておきましょう。」ということである。「よみがるた」と書かれているから「読みカルタ」の遊技風景だというのである。こういう文献史学丸出しの批判に対して、「絵画史料は偏見を持たずに絵画そのものを見よ、それを理解できるまで見て、絵画が自らを語り始めたらそれに耳を傾けよ」という研究手法の私としては、「あんた何言ってんのよ」としか言いようがない。
カルタ関係の文献史料やかるた札の物品史料で、掲示されている書の文字と挿画が食い違っている例などいくらでもある。「百人一首歌かるた」で、同じ歌人の図像が違った名前で二度登場して違った和歌を詠み、百人一首ならぬ「九十九人百首かるた」になっている例もあれば、上皇の図像の札の歌人が臣下を名乗りその者の和歌を詠んでおり、逆に公家の図像の歌人が上皇を名乗りその和歌を詠んでいる「とりかえばや百人一首歌かるた」もある。絵を描く画工、文字を書く書家、木版に彫る彫師の仕事場が別々で、手から手に半完成品が渡って徐々に仕上げられてゆく江戸時代の生産様式ではどうしてもこういう事故が起こりやすい。
『繪本池の蛙』も、注文主が絵師の西川祐信に「読みカルタ遊びの絵を二枚お願いします」と依頼し、その時注文主としては「読みカルタ遊技」の図像二枚を頼んだつもりであったのに、西川が気を利かせて、「読みカルタ札」を使った遊技の絵画を二枚なら一枚は「読みカルタ遊技」の図像でもう一枚は「合せカルタ遊技」の図像にしようと考えて描いて、大家の作品なので描き直せとも言えなくてそのまま用いられたと考えても一向に不思議ではない。西川の絵画を引き継いだ書家が同じ頁の下部の図像をしっかり確認しないままに上部に狂歌を書いたのかもしれない。だから私は、この図像でも図像そのものを虚心に見ることを心掛けている。
何よりも気になるのは、二十枚の札が消えていることである。場札も二枚しかない。研究室が言うような「読みカルタ遊技」ではこういうことは起きようがない。サントリー美術館蔵の邸内遊楽図屏風を見ると、読みカルタの場面で、場には十数枚の札が散らかっている。読みカルタの情景描写はこうでなければなるまい。また、『繪本池の蛙』のもう一枚のカルタ遊技の図では、六人が参加して五人が五、六枚の手札を持ち、場札は畳まれて裏返しになっているものが数枚、表を見せているものが二枚以上で、行燈に隠れて残りが何枚かは良く見えない。その中で一人の女はすでに手札を多く出して勝利寸前であり、今は一枚を抱えて出す機会を狙っているという場面である。合計で四十枚程度は描かれているし、手札が一枚になっている者も描かれているのでこれは読みの遊技の場面と判断されるのであるが、こういう絵画と比べるとこのページのカルタ札は少なすぎる。四枚一組のトリックとして各遊技者の手元に引き取られたものでなければ、いったいどこに行ってしまったのだろうか。
研究室もこの不自然さには気が付いたのか、私を批判する「傍証」では、これらは「よみ」の競技開始時の描写で理に適っていると説明する。それならば、場に二枚しかないことの説明はつくが、開始時であるとすると、三十七枚のカルタ札での遊技とすれば遊技者各人は手札を最低でも九枚か八枚持っていないと数が合わない。四十八枚のカルタ札での遊技とすれば遊技開始時は十一、二枚である。この絵画の遊技者は、私には手札を一人五枚持っていると見えるのだが、同じ絵が研究室にはなぜ、遊技開始時の手札の数、一人九枚だとか十二枚だとかに見えるのだろうか。不思議なことである。
次に、一人の男の前にある三、四枚の札の塊である。研究室は、「傍証」としてこれを「よみ」を打つ際に不要な紋標「イス」のカード、「赤絵札」だと説明する。赤絵札という言葉はほとんど見かけない。普通は「落絵」、「死絵」等である。江戸時代には、カルタ札で「絵」というときは、ソウタやウマやキリのような人物像を意味するのではなく、「札」そのものを意味する。したがって、「絵札」という表現は「札札」と言っていることになるので成立しない。この点、トランプの札を「絵札」と「数札」に分けて呼んでいる近代社会の用語法とは異なる。「赤絵札」は紋標「イス」の札という意味なら「赤絵」で良いのではなかろうか。それはさておき、この絵画でのこの札の塊は、私には「合せカルタ遊技」での一トリックの四枚の札だと思われるが、同じ頁を見て、どうして絵画が語り掛けてくるものがこんなに違うのか驚く。私には、画面には三、四枚の札しか見えない。この札の塊を、不要なので取り除くとき生じる十一枚の赤絵札と、元々三十七枚を四人に均等に配ると余る一枚の落絵、合計で十二枚の札の塊だと見ることはとてもできない。三、四枚と十一、二枚ではまるで違う。西川祐信の絵画はそのようには語りかけて来ない。
研究室は、「傍証」として、これは読みカルタの場面で、女が「オウルの三」の札を出そうとしていて、場に「ピン」と「二」があるのだから「一」「二」「三」の順で出されていて競技開始時の描写として理に適っているという。だが、研究室が頼りにしている同頁上部の狂歌では、「青二」をひねったら「丸二」になったと書いてある。「丸二」つまり「オウルの二」は、その図像が排便器具の「おまる」を上から見たところに似ているので「おまる」と呼ばれ、さらにその俗称の「おかわ」と呼ばれるようになった。上部の狂歌の「丸二」に「おかわ」というルビが付く理由である。だからこの札は、研究室の立場からすると、絶対に「オウルの二」でないと困る。「オウルの三」では「おまる」に似ていないので「おかわ」にならず、狂歌が成立せず、理に適わない。これを「オウルの三」と見ちゃ、折角の文献史学が台無しでしょうよ。ちなみに、私の合せカルタ遊技説からすると、もう最強の「青の二」で切られた後のこのトリックの敗戦処理だから、「オウルの二」でも「オウルの三」でも理に適っており、説明に苦しむことはない。
研究室は、「傍証」の最後で、この絵画を合せカルタの遊技と考えると、右側の男の一人勝ちで不自然だと言い、その男がやけに嬉しそうだという。この絵画が研究室にはこう語りかけているのか。私の知る限りでは、この男の前頭部に手を当てる仕草は、まずかった、失敗したという表現に見える。おでこに手をあてて喜ぶ人がいないとはいえないが、普通は失敗者を表現している。他の邸内遊楽図でのカルタ遊びの場面でも同じようなおどけたポーズの男がいることがある。そしてこの図像では、男は第七トリックで「ピン」を出したのにすぐに「青の二」で切られて取られてしまい、こりゃ失敗だったわ、しくじったわ、と後悔している。笑っているように見えるのは嬉しいからではなく、おどけた苦笑いである。私にはこう語りかけている。これが「傍証」で述べているように「読みカルタ遊技」の開始直後の描写であり、「一」「二」「三」と打ち出されているさまは通常の展開であり、自然に受け止められるというなら、一人が一枚ずつしか出さない全くぬるい読みカルタ遊技の始まりで、自然過ぎてどこにも洒落も見立てもしゃれももじりもない退屈な絵になってしまう。そういう魅力のない平凡な絵画をなぜ出版したのか、「傍証」がいうぬるいがまだ失敗とはいえない段階の、遊技開始直後の場面だとすると、右側の男はなぜ自嘲気味の笑いを浮かべているのか。さっぱりその趣旨が分からなくなる。読みカルタ遊技説ではこの笑い顔はどう理解されるのだろうか。
[1] この部分の文字のポイントが大きいのは研究室のウェブサイトの記載に従った。