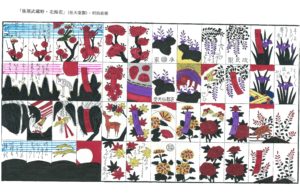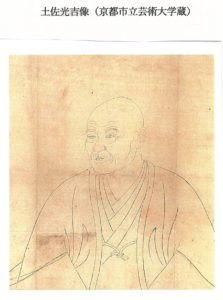百人一首は、和歌文化の範囲を超えて、江戸時代の文芸に広く影響した。岩田は、俳諧、とくに雑俳の「小倉附け」「小倉笠」の果たした役割の重要性を指摘して、享保十八年(1733)刊の『雨のおち葉』の「きりぎりす・泣とおさえる歌かるた」を例示し、また、江戸座附句集の「八重むぐら臼盗まれて広く成」、解説すれば、八重むぐら茂れる宿で、臼(太った妻であろう)を盗まれたのでその分広々として淋しさがいっそう募る、を挙げている。中島悦次、大坂芳一等の狂歌、俳諧、川柳に及ぶ百人一首の影響の研究も参考になる。百人一首を時に「ひゃくにんしゅ」と読むことがあるが、それは、これを雑俳などで取り上げる際に、「ひゃくにんいっしゅ」では長すぎるので「ひゃ」「く」「に」「ん」「しゅ」の五音に圧縮する工夫に由来する。この発音が広く通用するほどに百人一首は多く採り上げられた。江戸期の文芸の文化では、雅なるものと俗なるものが巧みに混交されている。うつし、もじり、しゃれ、やつしなどの手法を駆使して百人一首は身近な笑いの種になっていったのである。
百人一首がらみの文芸としての楽しみは、身分制秩序が緩み、武士が町人とともに文化、芸術を享楽した江戸時代中期の社会では、比較的に上流階級の文化人が大いに楽しむ世界である。そして百人一首が抜きんでて愛好されたのは、文字が読めないような庶民の間でも流行したからである。「むべ山」はその一つであり、文字が読めなくとも、和歌の歌意が理解できていなくとも、読み手の言葉がたとえば「濡れにぞ濡れし小判かな」であれば川に落ちた小判の戯画で「みせばやな」のカードを取ることができるし、「霧立ち登るおやじの木登り」であれば木登りの戯画で「むらさめの」を取ることができる。大変に分かりのいいことであるから、百人一首の歌意に明るくなくても理解できるのである。
こういう背景の下で、百人一首は文字を読めない者も含めて多くの人々に享受された。落語の世界では、小倉色紙を探す「鼻利源兵衛」(別名「出世の鼻」)、相撲取りの登場する「千早ふる」、若旦那と小町娘の恋わずらいの「崇徳院」、西行法師の「西行」、在原業平と小野小町がでてくる「口合小町」(別名「洒落小町」)、柿本神社が舞台の「明石飛脚」(別名「明石名所」)などがある。
狂歌、川柳の世界では、百首の和歌、百人の歌人のほとんどすべてについて、それを扱った作品がある。濱口博章は、狂歌につき、百人一首をもじった作品として、生白堂行風(せいはくどうぎょうふう)の寛文六年(1666)刊『古今夷曲(ひなぶり)集』、寛文十二年(1672)刊『後撰夷曲(ひなぶり)集』、石田未得(みとく)の宝暦七年(1757)刊『吾吟我(こぎんわが)集』、唐衣橘洲(からごろもきつしゅう)らの天明三年(1783)刊『狂歌若葉集』、四方赤良(よものあから)(大田南畝)らの天明三年(1783)刊『万載(まんざい)狂歌集』、四方赤良の天明五年(1785)刊『徳和歌後万載集(とくわかごまんざいしゅう)』、大田南畝の天保十四年(1843)刊『蜀山人(しょくさんじん)狂歌百人一首』などを広く紹介している[1]。川柳については、十七文字の制約で三十一文字をもじるのはできないが、百人一首を題材にしたものは、柄井川柳(からいせんりゅう)、呉陵軒可有(ごりょうけんあるべし)が始めた明和二年(1765)から天保十一年(1840)刊行の『俳風柳多留』の全百六十七編などに大量にあり、たとえば阿部達二[2]は、「小倉百人一首」を扱った川柳を集めて、そうした世界を活写している。百首の和歌のうち九八首について関連する川柳が登場し[3]、また、「歌かるたちょきちょき切って叱られる」(ちょきちょき切るのは賭博用のかるた)など、かるた取りの遊技の風景なども好んで取りあげられた。中には、「赤人を白妙にした新古今」などと、山部赤人の和歌が本来「真白にぞ」だった部分を『新古今和歌集』の選者が「白妙の」に改作した事情を笑ったり、「鶯も蛙も鳴かぬ小倉山」など、なかなか学のあるものもある。
後者は、よく知られているように、『古今和歌集仮名序』で歌心を掻き立てるとされた美声の鶯やかじか蛙が、百人一首には登場しないことを揶揄したものである。かつて吉海は、これが日本文学史の古典、古今和歌集の仮名序を踏まえた川柳作品であることが理解できず、鶯も蛙も花札の図柄をさしており、花札に登場する蛙が百人一首には登場しないという意味であるのだから、こういう川柳から江戸時代の花札の柳の札に早くも小野道風と雨蛙が登場していることが分かるという珍説を唱えて、花札史研究者、和歌文学史研究者の双方で失笑を浴びたことがある[4]。いうまでもなく花札の柳の札は、元禄年間(1688~1704)の草創の時から明治二十年代(1887~96)の八八花札の流行の時期まで、雷雨の中を走る男の図柄であり、小野道風は登場しないので雨中で柳の枝に飛びつく蛙も登場しない。論語読みの論語知らずならぬ古今集読みの古今集知らずであり、この失態を知れば川柳好きの江戸時代の町民たちも大笑いしただろう。
江戸の音楽の世界にも和歌は登場する。濱口は、謡曲の『松風』、富本節の『徒髪恋曲者(いたずらがみこいのくせもの)』、長唄の『京鹿子(かのこ)娘道成寺』などの例を紹介している[5]。幕末期の都々逸本には百人一首をもじって都々逸にしているものが多い。『百人一首吉原都登逸』や『小倉山都々逸百首』もあるが、『都々逸恋(いろ)の美南本(みなもと)』[6]の「小田のかり庵(ほ)にふくとまよりも 荒いお前のすて言葉」「かささぎの渡す橋さへふつゝり絶て こぬのはあきたかじらすのか」などの都々逸をくちずさむとき、和歌は口承文芸という江戸人の思いが一段と身に沁みる。都々逸は文字で読んでも面白くない。同様に、百人一首は狂歌[7]や川柳[8]、あるいは地口、もじり[9]の格好の種であった。これらも耳で聞いた方が楽しめる。
「いろはかるた」でも、「取り手」は「読み手」の「発声」に応じて、「絵」でカードを探して取るのであり、そこに文字が無くても遊技が成立することは絵札に文字をまったく欠いた「道齋かるた」の取り札が成立した例を考えれば理解できる。「百人一首」でも、ちょうど現代で音楽のファンが、楽譜が読めなくても耳から入った「調べ」を再現し、言葉の意味が理解できていなくても外国語の歌詞を再現するように、和歌を吟誦で理解して音声で再現できる。読めない文字、読みにくい書きぶりの文字があればそれは多少のハンディに過ぎない。だからもし百人一首歌合せかるたの「下の句」のカードに「絵」があれば文字を読めなくてもかるたの遊技に参加できる。「むべ山かるた」がそういう需要に応じたことはすでに述べた。
大きく考えれば、ある社会の共通言語の骨格を形成したのは、ヨーロッパでは聖書、イスラム社会ではコーラン、中国では四書五経、そして日本では小倉百人一首であるとまで言える。南は薩摩の地から、北は津軽、松前まで、江戸時代に人々が共通して口にできたものは、「小倉百人一首」だったのである。宗教の書でもなく、君子の道の書でもない。和歌を共有する文化という日本文化の特徴がこうして形成されたことの意義は、いくら強調しても足りない。
[1] 濱口博章「小倉百人一首」『日本のかるた』カラーブックス二百八十二号、保育社、昭和四十八年、一一四頁。
[2] 阿部達二『江戸川柳で読む百人一首』(角川選書三二八)、角川書店、平成十三年。
[3] ただし、秋山忠弥「江戸市民文芸にみる百人一首」(東洋大学井上円了記念学術センター編『百人一首の文化史』、すずさわ書店、平成十年)は、すでに百首もれなく関連の川柳を見つけて並べていたのであるから、阿部達二の研究不足である。
[4] 吉海直人「『花かるた』の始原と現在」『同志社女子大学日本語日本文学』第十六号、同志社女子大学日本語日本文学会、平成十六年、三九頁。
[5] 濱口博章「小倉百人一首」『日本のかるた』カラーブックス二百八十二号、保育社、昭和四十八年、一一四頁。
[6] 倉田喜弘『江戸端唄集』(岩波文庫)、岩波書店、平成二十六年、二〇〇頁。
[7] 江口孝夫『爆笑江戸の百人一首』(『百人一首の散歩』、『百人一首江戸の散歩』の改題)、勉誠出版、平成十七年。
[8] 阿部達二『江戸川柳で読む百人一首』角川選書三二八号、角川書店、平成十三年。
[9] 武藤禎夫『江戸のパロディーもじり百人一首を読む』、東京堂出版、平成十年。