カブの遊技法については、山口吉郎兵衛も苦労しながら探索している。丹念に遊技法の記述の例を拾い出しているが、史料不足の苦労がしのばれる。また、山口は、「京カブ」という親と子が一対一で勝負する、カジノのルーレットのような対戦形式のものと、「引カブ」という、トランプのポーカーのような、参加者同士が勝負する形式のものと大きく二分されることを報告して、『雍州府志』がいう「かう」は「京カブ」の系統の遊技法であり、「ひいき」は「引カブ」の系統であるとしている。
それならば、山陰地方に古くから伝わっていた九度山はどういう遊技法なのであろうか。九度山札から絵札八枚を除いて成立した「オウル」紋標のまめカルタはどうだったのか。瀬戸内海沿岸の小丸札、四国の目札、九州北部の大二札はどんな遊技法だったのだろうか。山口はいずれも分かっていないようであるが、その事情は今日もあまり変わりなく、私も良くは知らない。大正年間(1912~26)の検察当局によるカルタ賭博の調査は、本体は東京管内、もう一つは愛知県内の動向をまとめたものなので、東日本のカルタ遊技については比較的に分かるが、西日本のそれについては分からない。「オウル」紋標のまめカルタ遊技が特に分かりにくい。私の史料調査も京都、大坂、江戸が中心になって、どうしても西日本が手薄になっていた。カルタの遊技はもともと北九州で始まり、全国に広がったものであり、西日本はカルタ文化の本場であった。だから、江戸時代、この地方にも、ローカルなカルタ文化を明らかにする史料、文芸作品が豊富に存在していたと思われるが、私の探索は十分ではない。この地でのカルタ遊技を扱ったローカルな文献史料の発掘が待ち望まれるところである。
そしてもし可能なら、西日本全体が圧倒的にまめカルタの遊技に染まっていった中で、強固にめくりカルタにこだわり、「下天正」や「小獅子」等の地方札を継承していた鹿児島県内のカルタ遊技事情も知りたいものである。カルタ札だけでなく、その遊技法においても、遠い昔、京、大坂で栄えた遊技法が列島の西端に残っていたのではないか。このように夢想するときもあるが、だが、すでにその地方札も廃れ、今では、京都のカルタ屋の倉庫の隅に、往時のカルタ札の版木や表紙(おもてがみ)が残るだけである。
なお、平成年間(1989~2019)の初めに、愛媛県の漁村で高齢の女性が大二札で遊技をしている例が見つかった。同県の人が調査し、私も現地調査に同行した。成果は遊戯史学会の学会誌『遊戯史研究』誌上で公表した[1]。この調査以前には、大二はかぶカルタに似た遊技であろうと想定していたが、実際に発見されたものは古い「プロトめくり」の合せ遊技であった。四人で行い、三人が競技に参加して一人は休む。札は大二、一組四十枚に鬼札一枚が加わり四十一枚である。手六、場六に札を配分して、手札で場札を釣り上げ、山札を捲って場札を釣り上げるところは「プロトめくり」の進行方法である。鬼札はどんな札とも合わせられる。これを「食う(くらう)」といい、その結果場に残る一枚の札を「クライカス(喰らい滓)」といって、鬼札で「食った」人のものとする。札には「一」「二」「十」は十点、「三」から「九」までは紋標数が点数になる。若干の「役」がある。勝負は、釣り上げた札の点数合計の多寡で決まる。
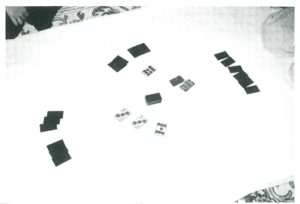
このような「プロトめくり」の遊技法は、江戸時代中期(1704~89)に始まった上方の「合せ」別名「てんしょ」が四国に移ったのであろうか。そういう場合は、「合せ」のカルタを用いればいいのであって、わざわざ一組四十枚のまめカルタ系の札を使う理由が見えない。逆に、まずまめカルタを用いる「合せ」の遊技法が西日本で考案されて、それが関西に移って「合せ」「てんしょ」になったと考えることもできないではない。
なお、「九十六」の調査では、手札が六枚、場札が六枚と記録されている。これで三人が遊技すると、手札が十八枚、山札が十八枚必要であり、これに最初に晒す場札が六枚だとすると、合計四十二枚になる。ところが「大二」は一組四十枚のカルタであり、鬼札一枚を加えても四十一枚で一枚足りない。最初に晒す場札が実は五枚であったのか、あるいは、ゲームの最後の人にはめくる山札が残っていないという変則の遊技法なのか、多少の違和感が残る。現地調査の記録にはこの点の記載がないし、もう二十五年も前のことなので、記憶も定かではない。現地でどのように確認したのか説明できないで申し訳ない。
[1] 三好正好「96(くじゅうろく)の謎」、江橋崇「同上解説」『遊戯史研究』第六号、遊戯史学会、平成六年、二七頁。

