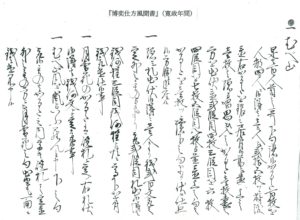もう一箇所注意するべきなのは、同じ序文のやや後半の部分にある表現である。「正月、このかたちある繪を手にふれたる人は、神徳を得て七なんをのかれ、七ふくのくわにをふ。去によつて七まい金入と云。二に花かたを付、大この事く(太皷のごとく)なるゆへうつと云。又十二月よミつきる心にてよむとも云。五こく成就の心をもつてまくと云。上るとは稲(いね)をうへて出る心なり。一節に目出度、田をかる故にかるたと云」。全体としてはダジャレの類であるがここに「七まい金入」の表記が有る。金銀彩が加えられた役札が七枚あるという意味である。「大極」のように札の図像に「金」の文字を加えることも考えられるが、本文の図像にはそういう例がないのであり、そうではなく、カルタ札一組の包装紙に商品のアピールとしてこの旨が摺りこまれていたのであろう。実際に、本書に掲載されている札の図像では「青のピン」(「あざ」)、「青二」、「青三」、「青のソウタ」(「釈迦十」)、「青馬」、「青きり」の六枚に「太鼓二」の合計七枚に金銀彩を加えたと思える描写がある。
これらの「金入札」がいつごろから出現したのかは分からない。もともと、ヨーロッパのカルタの制作方法からすると、海外から伝来した南蛮カルタには金銀彩はなかったもので、これは日本に入ってからの工夫であろうと思われる。注目されるのは滴翠美術館にわずかに一枚だけ残されている国産の三池カルタの「ハウのキリ」の表面に、木の葉状の模様など、金銀彩の痕跡が見られることである[1]。江戸時代初期(1603~52)にはすでに金銀彩が行われていたものと判断したい。こうしてみると、「七枚金入」は、読みカルタの発祥の当初から、そのカルタ札が読みカルタ用のものであるのか、その他の合せカルタ用のものか、カブ系の遊技のものかを識別する重要なポイントであることが分かる。
ここで参考までに明治年間(1868~1912)以降に残存した地方札で比較してみると、まず、「 小松 」と「 伊勢 」ではいずれも金銀彩が途絶えている。これらは読みカルタ系の遊技に用いられることもあるものであり、何枚かの札は図像の数以外の数の札として扱うことも許される「化け札」などの役札であるが、そのことを示す金銀彩がないので配分された時の喜びはキラキラせずにどんよりとしており、長い伝統のある読みカルタの末裔としては寂しい。
地方札の「 赤八 」には、「オウルの六」に分厚い金銀彩がある。「赤八」は「えび二」に布袋坊主の図像があるのが特徴で、これは元禄年間(1688~1704)の老舗、「ほてい屋」の屋号である。この「ほてい屋カルタ」は主として「合せカルタ」の遊技に用いられたらしいことが分かる。その後、これは江戸時代中期に上方で盛んになったフィッシング・ゲームの「合せ」「天正」の札となり、江戸に入って「めくり」の札となった。江戸時代前期(1652~1704)の「ほてい屋カルタ」が江戸時代中期(1704~89)に上方の「合せカルタ」に変身すると、「オウルの六」が重要視されて金銀彩が施された。そしてそれが江戸に入って「めくりカルタ」の札になると、「オウルの六」は単なるかす札になって金銀彩が消え、代わるように「青六」が高得点札になり、その図像に金銀彩や「壽」の金文字が加えられるようになった。今日、古い賭博系のカルタを見るとき、二枚の「六」の札のいずれに金銀彩があるのかで、「合せ」向けの関西のカルタか「めくり」向けの江戸のカルタかが識別できる。
また、今日まで残されている地方札では「七枚金入」とされた七枚のカルタ札に限って金銀彩を加えたものは存在していない。江戸時代中期以降の「合せ」や「めくり」の遊技法に適合させてもっと多くの札に金銀彩が施されている。中には「惣金福徳」と呼ばれるカルタ札のようにすべての札に金銀彩が施されているものさえ出現している。つまり、読みカルタの遊技法は一部の地域にかすかに残っていたが、それ専用の読みカルタ札は明治年間までに消滅して残っていないのである。平成年間前期(1989~2003)に京都の松井天狗堂という手造りのカルタ屋で 「小松」の復元 を試みて、これを読みカルタとしてコレクター向けに売り出した。同店の主人は、金銀彩のある地方札は手に余るとして復元制作を断念していたが、たまたま手本にした任天堂などの現代版の「小松」がすでに金銀彩を略して江戸時代の「七枚金入」の伝統から逸脱していたところ、それをそのまま真似したので、平成版の松井天狗堂の「小松」にも金銀彩がない。これもまた「七枚金入」の江戸時代の読みカルタ札の伝統とは遠く隔たっていたのである。松井天狗堂の主人は生前、小松は金銀彩抜きなのでその技術のない同店でもなんとか制作ができたと告白していたが、結局は一応現代の「小松」に近い外観を示すにとどまって、いつの時代の読みカルタを復元しようとしたものなのか、制作の趣旨がさっぱり分からない。これが商品として一般の市場で販売されたこともない。結局はコレクターズ・アイテムの参考模造品にとどまってしまった。世界で唯一人、手造りカルタの職人であった松井重雄の晩年の仕事としては残念な結果に終わった。今でも時折、残品がネットオークションなどに仰々しい宣伝文とともに高額で出品されているが、見るたびに松井の不名誉を暴露するように思えて物哀しい気持ちになる。
『雨中徒然草』に戻ろう。同書の序文は、少し前の部分で「七枚金入」の中の一枚、「太鼓二」について「太鼓(たいこ)二はかゝミ(鏡)なり」であり「正月このかたちある繪を手にふれたる人は神徳を得て七なんをのかれ七ふくのくわ(果)におふ」とした後に、「青きりは日本人、青馬は唐人、青二は龍人、青十は釈迦如来(しやかによらい)、青三は三種(さんしゆ)、天地人三徳、あさは虫をひやふす。」と残りの六枚のいわれを説明する。そして、この虫札にかこつけて、「此虫の大毒によつて、もろもろのむし蚤蚊(のみか)迄をそるゝゆへ蚊のましないと云伝ふ」と、夏の夜、開けっぴろげの屋内でカルタ遊びに耽って大騒ぎすることを「蚊のまじない」だと弁解している。
このように、『雨中徒然草』の序文は当時の読みカルタの遊技について、洒落、もじり、捻り、やつし等の江戸町民文芸の手法を駆使しつつ説明しており、当時の娯楽の雰囲気を知る格好の文献史料となっている。
余談になるが、ここでの「七枚金入」に関連して私が感動したのは、山形市内で幕末(1854~68)、明治初年(1868~77)に制作された「黒かるた」である。この地方札の場合は、「赤四」「赤五」の中心には菱形がなく、「青」も「赤」も「六」から「九」までにしか菱形が現れないという点では江戸時代後期(1789~1854)のカルタ札としての特色をもっているが、「あざ」「青二」「青三」「釈迦十」「青馬」「青きり」と「えび二」、「太鼓二」に真鍮粉を使ったと思われる金彩がある。「オウル六」にも「青六」にも金彩はないので、江戸時代中期(1704~89)の上方の「合せ」の影響もないし、江戸の「めくり」の影響もない。
「黒かるた」は形も縦長でめくりカルタより一時代古い古風なもので、顔料はすでに入手しやすい幕末、明治初期のものに交代しているが、図像の様式は、何百年も昔、京の都で栄えていた頃の先祖から伝承した読みカルタのものを維持している。山形は紅花の生産地であり、最上川の水運、坂田からの北前船の海運によって遠い上方と深く結びついていて、博奕も盛んであった。この航路沿いに、いつカルタ制作の生業が山形にまで届いたのかは分からないが、雪深い東北の町の片隅で、さほど多くはなかったであろう客からの注文に応じてひっそりと制作に励み、最後は店をたたんで北海道に移住していった職人の一家が山形市内に残していったものが最後の読みカルタ札であった。
これが私の実見した限りでは最後の実例である。もう三十年も前の話になるが、私は、制作者である中川代三郎というカルタ屋の痕跡や子孫を探し求めたが、一家は明治年間前期(1868~87)に北海道に移住していて以後の消息が不明であり、他にも何軒かあった沼沢権八などのカルタ屋の子孫の消息も得ることもできなかった。こういう図像のカルタを制作していた地域なのであるから山形県内に読みカルタの遊技法も残っていないかと調査したが発見には至らなかった。京都の松井天狗堂も、昭和後期(1945~89)の任天堂の「小松」等を復元のモデルに用いないで、この山形の「黒カルタ」を元にしていれば、誤ることなく本物の「最後の読みカルタ」を実現できたのにと残念に思う。
[1] 『文藝春秋デラックス古典の遊び日本のかるた』、文藝春秋社、昭和四十九年、五頁。