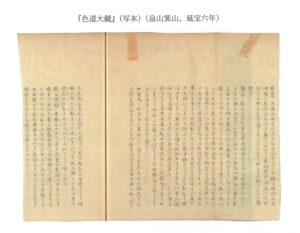さて、うんすんカルタの歴史にかかわる史料は以上に尽きるものであるが、物品史料、文献史料、人吉市の伝承史料を見たうえで、私には、なお、その歴史像が明確に把握できていない。今回書いたものもそこら中で分からないを連発しており、恥ずかしい。
私には、まず、『勧遊桒話』が主張した中国伝来説が否定できない。「ウン」や「スン」の図像を見ると、「蝙蝠龍」も「火焔龍」も中国経由ないし東南アジアの中国人社会経由のように見える。それに、これまで言及したことはないが、木版天正カルタの「キリ」の人物像に描かれている釣り上った眼は、世界の版画美術史研究では「アーモンド・アイ」と呼んで明末、清初の中国版画の決定的な特徴とされている。ヨーロッパにはこういう目の描き方は存在せず、日本の天正カルタに手本として直接影響したと思われるベルギーのアントワープのドラゴン・カードもこの目つきだけは全然違う。先入観なしにこの表情を見れば、明らかに中国人の描いた図像という印象になる。その昔、シルビア・マンと雑談する折に、神戸の版木は中国人画工の作ではないかなと疑問を漏らしたところ、マンが、自分は部外者なので言うのを遠慮していたけど同じ意見だと応えたことを思い出す。その他、これまでに見てきたいくつかの点から、私は、中国伝来説を否定せずに、留保させていただきたい。
こういう私から見ると、中国伝来説を全く無視して自説を展開している従来のうんすんカルタ史研究の大胆さは驚異である。私は、うんすんカルタは、ヨーロッパのカルタがアジアに入ってきて、どこか、東南アジアないし中国国内でヨーロッパ人と接触する機会の多かった中国人社会で「タロット」からうんすんカルタに変身して、それがポルトガル船ないし中国船によって日本に伝来し、日本国内では、その図像を微妙に日本風に変化させる微調整を経て使われてきたという歴史像を私の研究関心の外に追い出すことができない。江戸時代初期(1603~52)に、そういう経路で伝来した可能性を捨てることができない。そうした可能性を無視してうんすんカルタは日本国内で四十八枚の天正カルタから考案された純日本製のカルタで、その時期は江戸時代前期、延宝年間(1673~81)以前だと断定する人には、その元気の良さに驚くのである。
次に、うんすんカルタの伝来ないし発祥の時期と、それと天正カルタの発祥との前後関係であるが、それも分からない。天正カルタの場合は、江戸時代初期(1603~52)と思われる手描きのカルタと木版カルタの版木及び残欠が確認できているが、うんすんカルタには、現品も文献も残されていないので判断のしようがない。また、木版の天正カルタでは、「オウル」が南蛮カルタでは円形の金貨であったのに、初期の段階から早くも左右の端の部分を切り落とす図像になっており、又「コップ」の図像では、南蛮カルタでは聖杯であったものが理解できなくて天地を逆にしており、脚部が特に乱れて図像は意味不明の線の集まりになっている。ところが、手描きの天正カルタやうんすんカルタでは、「オウル」の図像は貨幣の形を維持しており、「コップ」の聖杯の脚部もしっかりと意味あるものに描かれている。こういう図像の変化は、天正カルタから延宝年間(1673~81)頃にうんすんカルタが枝分かれしたとする説では合理的な説明が困難である。
黒川道祐は、江戸時代前期の「宇牟須牟加留多(うんすんカルタ)は「かう」や「ひいき」と同類のカルタ札を使う「博奕の戯」だと言っている。トリック・テイキング・ゲームは、十七世紀のカルタの世界でのスタンダードであり、伝来したカルタの遊技法の王者である。それを黒川が「博奕の戯」と切り捨てるとは考えにくい。そして、今日まで残されている一組七十五枚のうんすんカルタの札は、元禄年間(1688~4)以降の上品な手作りのもので、上流階級の子女の遊技のツールであったと思われる。そういう上昇志向の強い遊技が、延宝年間(1673~81)と元禄年間(1688~1704)の中間に位置する貞享年間(1684~1688)でだけ下賤な「博奕の戯」に堕していてまたその後に上品な上流階級の遊技に上昇したとは考えにくい。黒川道祐の「畢竟、博奕の戯なり」という記述は、誤記であったことになる。
この難点を解消するために、『雍州府志』の「畢竟、博奕の戯なり」という記述は、一見すると「かう」「ひいき」うんすんカルタが悪質な博奕の遊技だと言っているように読めるけど、慎重に読めば、それ以前に触れた「読み」や「合せ」も含めて、海外から伝来したカルタの遊技は全部博奕の戯に過ぎないという、黒川道祐としての全体的な評価の一文なのだという解釈が現れた。
この解釈には、二つの問題点がある。一つに、黒川道祐は、『雍州府志』の全巻を通じてどこでも、重罪の犯罪行為やその用具を京都の名産品として紹介したことはないのであり、この「賀留多」の項だけ例外で、カルタの札はその本性が「畢竟、博奕の戯」という重罪の博奕行為に用いる賭具でしかないのに、その使い方まで詳細に紹介したことになる。この様に理解するのは、黒川の格調高い執筆姿勢を貶めるいかにも不自然な解釈である。
もう一つは、博奕という言葉の理解である。博奕という言葉は、現代の社会では、賭博行為一般の意味に理解されるが、江戸時代の博奕は罪の特に重い重罪に該当する犯罪行為を意味する言葉であり、骰子博奕や雙六博奕は著名で、カルタ遊技の中でも「カウ」や「ヒイキ」は博奕犯罪の扱いを受けたが、「読み」や「合せ」はそれほどまで罪責が重いとは考えられていなくて、準博奕の扱いであって、博奕には含まれない。だから、黒川道祐が、「読み」も「合せ」も含めて「畢竟、博奕の戯」であると言うはずはない。それは。現代人が、強盗殺人も過失致死も自殺ほう助も殺人罪だと言うはずがないのと同じことである。痴漢も下着泥棒もひっきょう強姦罪だとは言わないのと同じことである。それなのに黒川の表現をこのように読み解くのであれば、それは江戸時代の博奕という言葉を現代語の「博奕」の語義で大雑把に捉え過ぎていて、黒川道祐の江戸時代前期(1652~1704)の文章をその当時の主旨にそぐわない内容に解釈をしているのではないだろうか。
結局、『雍州府志』がいう「宇牟須牟加留多(うんすんカルタ)」という博奕に類したカルタの遊技は、今日まで残されてきた元禄年間頃に制作された一組七十五枚の豪華なうんすんカルタ札を使う多人数の遊技ではなく、それとは別物の、一組四十八枚の札を使用する博奕まがいのトリック・テイキング・ゲームの遊技法だということになる。「カルタ」でも「歌かるた」でも、使用する札の枚数や配分の仕方を詳細に検討している黒川が、一組が七十五枚のカルタが店頭にあったのならばそのことに触れないのはおかしい。六條坊門(五條橋通)の木版カルタ屋で七十五枚のものを制作して販売していたのだとすると、普及品のカルタ、三池カルタ、箔カルタ、木版の歌かるたをきちんと識別して説明していた黒川が、うんすんカルタの場合だけその構成や内容を説明しないのがいかにも奇妙である。私は、この時期には、六條坊門(五條橋通)のカルタ屋ではうんすんカルタは制作していなかったので黒川がそれについて書いていないのだと考えている。