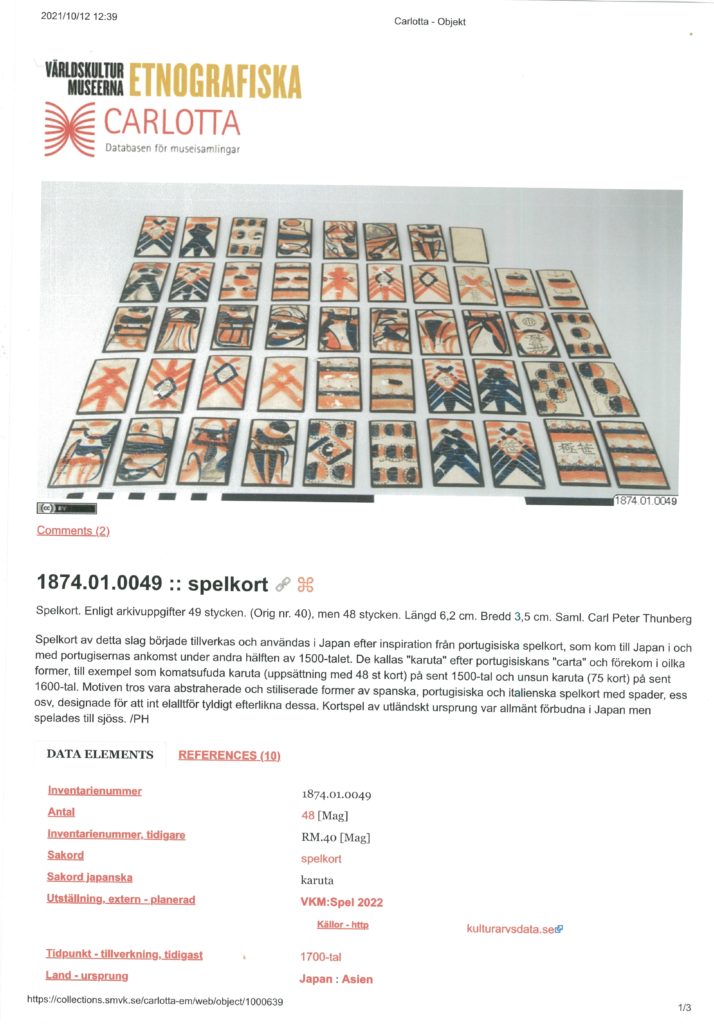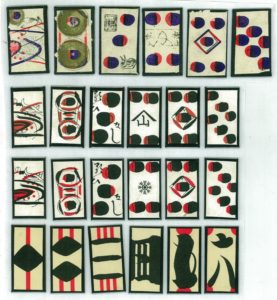本書をまとめ終えて、ある種の感慨がある。物品史料を駆使して麻雀の歴史を再検討する。その結論が、以前に誰かが唱えていた旧説であっても一向にかまわない。私が求めているのは、既成の麻雀史が描けなかった新説の提示ではなく、麻雀遊技の歴史について、今後、多くの研究者によって研究が積み重ねられていく基礎となる、「歴史学」のレベルに達した学術的なデータを提唱することにあるのだから。
従来の麻雀史の叙述は、随筆集から大学院の博士論文に至るまで、その人が入手した文献史料が史実を語っているという無言の前提を採ったうえで、それを新しく読解し、引用することで歴史を語ってきた。当然のことながら、以前の研究業績は繰り返し再利用されて継承されてゆく。私は、こうした往時の文献史料に基く研究の結果がすべて「疑史」だというつもりはない。多くの場合、「当たらずといえども遠からず」の粋にあるのだろう。ただ、こうした文献史学を続けている限り、文献史料の再解釈の成果は溜まる一方で、研究業績の「智」についての学界の共有資産としての蓄積はあまり期待できない。その結果、昔も今もほとんど変わらない歴史像が繰り返されているのである。最近ネットに溢れている日本麻雀史の文章は、昭和前期に書かれた同時代史の叙述と驚ろくほどに類似している。同じ史料を使った同じような指摘の繰り返しに近い。
私は、元来は「かるた」史の研究を進めてきた。その方法論は、まず物品史学の立場に立って物品史料が語る歴史を重視することにあり、さらに、「かるた」が属する遊技の世界では、その遊技文化は社会で生活する人々の間に自生するものであり、生活圏の範囲で成立する地域文化なのであり、そういうものとして認識することが大事だ、という二点に集約できる。
私の麻雀史研究は、ここで麻雀界の至宝、阿佐田哲也の『麻雀放浪記』を引き合いに出すのは不謹慎のように思えるが、「麻雀牌放浪記」として始まった。本書で書いたように、私は1980年代の終わりころ、中国山東省曲阜市の孔子廟門前の露店で、この地で遊技に使われている「曹州紙牌」を発見して驚愕した。中国は紙製のカード遊技の発祥した地域、いわば「紙牌」の故郷であるのに、1960年代の文化大革命で賭博は旧弊、害毒、反革命であるとして徹底的に弾圧されて消滅したと考えられていた。それがしぶとく生き残って地域の遊技文化として栄えている。それはまるで、もはや図鑑でしか見ることができなくなった、数十年前に絶滅したはずの天然記念物の蝶が眼前で優美に舞うのを目撃した昆虫学者、あるいはインド洋コモドの深海で生ける化石、シーラカンスを発見した古生物学者の感動に似た驚きであった。
そして、その気になってみると、実は中国各地にその地域に独特の「紙牌」の遊技が存在していた。それを発掘、蒐集しようと買い求めて、私は中国各地、多くの省、市、自治区を放浪した。それが、いつしか、「紙牌」蒐集から「麻雀骨牌」やそれの生史料文献の蒐集に拡大されるようになった。こうして私の旅は、「紙牌」であれ「骨牌」であれ「文書史料」であれ「古老の伝承」であれ、およそ麻雀史の研究に役立ちそうな物品史料を探し求めて放浪する「麻雀牌放浪記」になってしまったのである。
この探索の放浪では、私自身の他には、中国人であれ中国滞在中の外国人であれ、似たような発想で、同じように遊技具の史料探索をしている人にはおよそ出会わなかった。そういう人の消息も聞かなかった。広大な中国の大地で、行く先々で「お前みたいなやつは初めて知った」と珍獣扱いされる放浪の旅であった。
私は、機会があるたびに中国にわたり、こういう放浪を十年近く続けたが、その成果である中国各地の「紙牌」のコレクションは予想以上に豊かであり、それと東南アジア各国の放浪の旅で得たものも合せて一括して、2000年に刊行された、大阪商業大学アミューズメント産業研究室(その後研究所に改組)刊の『アジアのカードとカードゲーム』(梅林勲編)に提供したので、学界の共有情報資産とすることができた。そして、今本書で活用している「麻雀骨牌」のコレクションは、1999年に開設された「麻雀博物館」の蒐集、展示品の軸にするように「紙牌」コレクションや関連文書史料とともに寄贈した。そのデータは、開館を期して公刊された竹書房刊の『麻雀博物館大図録』の主要な内容として記録に残した。幸いなことに日本国内だけでなく、中国、アメリカ、ヨーロッパなどの研究者に学術資料としての価値が認められて、広く受け入れられて活用されてきた。
「麻雀博物館」の開設は、世界の麻雀史研究者にとっては衝撃的な事象であったと思う。設立時に同館の顧問として諸事万端の指導を委嘱された私は、ここを世界で初の物品史学の殿堂に仕上げたかった。竹書房の野口恭一郎は広く手配して欧米の文献史料を熱心に集めて、それに私が提供した東アジアの文献史料と、世に隠れた日本麻雀史の優れた探索者であった鈴木知志の日本麻雀史の文献史料とが合わさって、博物館の文献史料はどの博物館、図書館にも負けない世界一の規模に達したが、それ以上に力を入れたのは、麻雀牌という物品史料の蒐集と活用である。物品史料のコレクションは面白いもので、一、二点を集めただけだと沈黙のままで眠り続けるが、十点、二十点と集めると蒐集品が目覚めたようなひそひそした話しをし始め、百点、二百点が集まると相当にうるさく自己紹介や自己主張が始まり、千点、二千点と集めると収蔵庫はうるさいほどのおしゃべりに満たされる。麻雀博物館は三千点を超える規模で蒐集したので、博物館の営業時間後、深夜の収蔵庫に立ち入って収蔵品同士の会話に耳を澄ませると、それまで気付かれていなかったとんでもない史実が次々と明らかになった。ここにこそ、不正確な記述、主観的な意見の史料が多い文献史学にはない、客観的な物品史学の研究手法のだいご味がある。そして、そこで明らかになった麻雀遊技史の史実の一端が本書の主要な内容になっている。
本書で主として扱ったところは次の三点に要約できると思われる。第一に、物品史料の助けを借りて、従来の歴史学では明らかにされていなかった史実、いいかえれば文献史料の過剰な説明で混乱させられていた史実を整理することであった。この点では、1860年代後半期のもので、アメリカに持ち帰られて行方不明になっていたグロバー牌の、イギリスの研究者による劇的な再発見によって19世紀半ばの麻雀骨牌遊技の始まりが見えてきたし、その研究が大きく前進できた。また、麻雀博物館による現地調査で19世紀後半に浙江省寧波市で生まれた近代麻雀の祖型、寧波麻雀、別名「中發麻雀」が見えて近代麻雀の基点が明確になった。ここでは走り書きで麻雀牌の収納箱に書かれた当時の宣伝文句の解析が史実をリアルに教えてくれた。
そして、19世紀終期から二十世紀初頭にかけてイギリスのウィルキンソン、アメリカのキューリン、そして日本の名川彦作、井上紅梅らによって保存された清朝末期の麻雀遊技と麻雀牌、清朝末期から中華民国の時期に麻雀遊技のセンターになった上海租界での欧米人らの麻雀遊技、そこから流出して、バブコックらの活躍でアメリカなどに広まり、日本にも及んだ世界の麻雀文化も明らかにできた。本書では、ほぼ十年単位で麻雀遊技の変遷史を刻むことができたし、各地方の独自な発展についても目配りすることができた。麻雀は、華中の上海、寧波、蘇州、華南の福州、広東、香港、華北の北京、大連、済南、青島、そして日本支配下の大連などで栄え、朝鮮、台湾、ベトナム、タイなどの周辺国に広まり、欧米に普及し、そして日本に伝来したのであるが、その経緯とルート、そして各地に固有の麻雀牌と遊技ルールも明らかにできた。
最近の歴史学では、科学の急激な発展により、物品史料を測定し、解析する物品歴史学の意義が評価され、各分野で活発に活用されている。「物品歴史学」や「中世考古学」「江戸期考古学」などの用語も飛び交い、社会史史料としての「エフェメラ」の活用も唱えられるようになってきた。麻雀博物館の活動は、こういう新潮流に含まれ、その効用をいち早く示すものとなった。私は、巨費を投じて博物館を開設し、物品史料の蒐集と解析に尽力した竹書房の経営者、野口恭一郎の功績は極めて大きいと思う。
本書の内容の二番目の力点は、麻雀の日本への伝来に置かれた。この伝来史については、各地の関係者が書き残した、自分こそその功労者であるという自慢話が世に溢れ、実相が見えにくくなっていたが、麻雀博物館は史料の蒐集に実直に取り組み、大正期に中国から伝来した名川彦作牌などの麻雀古牌、昭和初期に日本国内で制作、販売された、プラスチック製の国産ゼロ号牌、文藝春秋社の国産一号牌、在北京の新聞記者で麻雀研究者の榛原茂樹が発掘した「榛原牌」などを続々と発見あるいは再発見し、また、上海在住の井上紅梅、大阪在住で名古屋に移り双方で振興に努力した司忠、東京の林茂光や菊池寛、鎌倉の文士たち、大連の中村徳三郎など、各地で活躍した人々の事跡を明らかにして、麻雀伝来史の史実に迫ることができた。蒐集した物品史料に依拠して整理してみれば、日本の麻雀文化は、中国からは上海麻雀、寧波麻雀、北京麻雀、天津麻雀、済南麻雀、大連麻雀、福州麻雀、広東麻雀、香港麻雀などが、また中国の外部からは、アメリカ麻雀、朝鮮麻雀、台湾麻雀などが重層的に伝来しており、その各々の中心人物が、我こそが日本への麻雀伝来の功績者であると自画自賛していたので混乱していた。麻雀博物館は、物品史料に加えて、蒐集した多くの文献史料も合せて研究して、この伝来の経緯をより立体的に、そしてより一層明確にすることができた。
この点から見ると、従来の日本麻雀伝来史は、書き手が麻雀遊技団体の中心的なリーダーであり、作家が多かったこともあって、東京中心の、いわゆる文士麻雀にスポットライトが強く当たっていた。しかし、麻雀牌やその他の器具や記録などを丹念に集めてみると、大正年間には、全国各地、とくに大阪、神戸の関西地域に無名の麻雀愛好家が相当数存在していて、中国から持ち込まれた麻雀古牌を使って、周囲の人間に遊技法を教えて共に楽しんでいた痕跡が見えてくる。実際に、最近のネット・オークションには制作時期不詳とされる中国製の麻雀古牌が時折に出品されている。それも関西方面からの出品が少なくない。そして、この使い古された麻雀古牌は、収納箱がまだ粗末なものであった時期のものであり、既使用品らしい汚れがあることもあって骨董品としてはあまり人気のある出品でなく、価格も安く設定されていた。私は、どこの誰かまでは分からないが、一つの家族の間で百年近く家族や友人での遊技に供され、あるいは何か事情があって押入れに仕舞われて時間が経過して、今になって子孫からネット・オークションに安価に売り出されている麻雀牌の流転の生涯に感じるところがあって、何組か、売れ残って出品者によって廃棄される前に買い求めていた。
日本での麻雀の伝来の第一号は名川彦作が上海で購入して帰国土産に持ち込んだものというストーリーが、麻雀史の定説として伝えられているが、ほぼ同じ大正時代に、名川と同じように中国でこの遊技に親しんで、帰国時に麻雀牌を持ち返ってきた人間が相当数いたのではないか。そして中には、名川彦作の麻雀牌よりも古い時期のものと思われる麻雀牌もある。本書で私は、こうして今は忘れられている日本麻雀史の先達の人々への思いも込めて、日本への麻雀伝来史を書いてみたのである。とくに、以前から中国との貿易なども盛んだった神戸、大阪での麻雀熱は、実際には東京の文士麻雀よりも先行していたように見える。それが、東京サイドの強い自己主張によって背景に移されて、日本に麻雀遊技を招来したのは菊池寛らの東京や鎌倉の文士麻雀の功績であるという神話が形成されている。私は、実際の伝来史は関西先行であった史実が紹介されていない現状を哀しく眺めてきた。今後、特に関西の麻雀関係者が、自分たちの地域の先覚者たちのことを調べ直して歴史として残し、名川彦作神話の壁を誇り高く乗り越えることを期待している。
本書で力点を置いた第三のポイントは、麻雀を通じた日本と中国の交流である。鈴木知志は、明治時代に中国に渡った日本人と麻雀の接触の実相を明らかにしたが、その後、日本の麻雀の歴史は中国のそれとの交流、親善、そして離反の歴史の中にあった。その中での両国人の友好、協力の歴史は貴重な先例であり、逆に、日本軍の中国侵攻による戦争と殺戮、破壊の歴史は強い批判と反省を要することでもある。本書では、日中の麻雀交流に尽くした井上紅梅や榛原茂樹と、その親しい友人であった京劇俳優の梅蘭芳らの友好、交流を中心にして、日中の交流の歴史を扱ってみた。ここでは、第二次大戦後に日本国内に残されていた梅蘭芳特別注文の美麗な麻雀牌を麻雀博物館が再発見して、交流の場の実際の空気、雰囲気を如実に示す物品史料として提示できた事がよろこばしかった。
この点では、1990年代から日中の健康麻雀交流の促進に尽力して、相互の代表団の訪中、訪日の旅を企画し、交流大会をしばしば開催して機運を盛り上げ、ついに1990年代の終わりに中国での健康麻雀解禁を実現させた、日本健康麻将協会(田辺恵三会長)の努力が大きく貢献した。同協会には、横浜市内の麻雀店経営者、斎藤正副会長らによるボランタリーな社会公益活動の企画とその実践という実績もある。日本国内でも国や自治体の健康文化事業に健康麻雀を組み込ませる活動、各地の自治体の「敬老健康麻雀大会」や国の「健康福祉祭」(ネンリンピク)での正式種目への採用を促進する活動、さらに高齢者のフレイル予防活動との連携など、高齢者中心の健康維持、老化予防の活動へのかかわりもあり、近時の健康麻雀推進の足跡は鮮やかである。残念なことに、その後の日中の関係は悪化の方向に向き、今日では交流の継続にも困難が生じているけれども、麻雀博物館が集めることができた貴重な物品史料と、「日本健康麻将協会」の日中友好の交流大会などの活動の記録は、この東アジアでのあるべき国際交流の一つの姿を示していると思われる。そして最近では、高齢化の問題への全世界的な関心の高まりの中で、中国、アメリカ、日本、台湾、韓国などの間での、健康麻雀国際交流の意義と効果が注目されている。この方面でこれまで進められてきた地道な努力と協力は今後もっとあきらかになり、活発になることへの期待も大きい。
なんだか選挙応援の演説のような雰囲気になってしまって申し訳ない。高齢者の繰り言はこの辺で流局にして、デジタル化の時代、大きく変貌する社会での、新しい麻雀遊技の鼓動に耳を澄ませたいと思う。
どうやらこれで、私の数十年の「麻雀牌放浪記」も終わりに近づいたようである。各方面の方々から恵まれてきた長年の交際、温かいご理解とご支援に感謝しつつ、筆を措かせていただこうと思う。多謝。
2023年05月31日 最終更新
2023年05月04日 加筆
2021年10月20日 改編
2020年01月23日 公開
※無断転載禁止