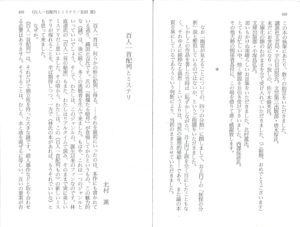百人一首の謎を解く』
百人一首を藤原定家による言語遊戯の傑作と理解する織田正吉の『絢爛たる暗号―百人一首の謎を解く』での問題提起は、発表時からセンセイショナルに受け止められた。私もさっそく読んで、衝撃を受けた。織田は、定家が、自身の開発した各種の作歌の技巧を重視し、二首が対になる編集を構築し、それをさらに言葉のつながりで次々と結び付けて、全体として一つの和歌の集合体を構築したと解析した。この着想は定家の頭脳の中を見透かして見事だと思った。織田が研究を深めて成果を発表したのは昭和後期(1945~89)のことであり、百人一首にいわゆる異本系のものがあるという認識はまだかるた史研究者という限定的な範囲での共有に留まっていた時期であったから、和歌文学史の中にいた織田にはまだこの論点は見えていない。そのことをとやかく言う積りはないが、平成年間(1989~2019)になってもなお織田の議論は影響力が強く、織田本人や後続者の議論がその始原の枠組みを出られないでいることには違和感が残った。
そして、織田自身の議論に関して言えば、百首は名歌を選んだのではなく、用いられている言葉の関連性から選ばれているという革命的な指摘は立派だが、編集にあたった定家に、隠岐に流刑されている後鳥羽上皇への追慕と、定家の若き日の式子内親王へのひそかな恋情があり、それが歌集の隠された主題であるというあたりは、よく理解できなかった。百人一首かるたの研究では、後鳥羽院と順徳院の二名の上皇の扱いよりも、かるた札上の歌人画像で、崇徳院から皇族の印である繧繝縁(うんげんべり)の畳を剥奪するという露骨な皇籍の剥奪、廃帝の扱いの方が気になった。崇徳院は没後二十年で、その悪霊ぶりに畏怖した京都の朝廷によって、それまでの讃岐院という廃帝扱いの蔑称から改め、崇徳院という諡名(おくりな)を贈られて一応は天皇としての在位も歴史に残されたのであるから、それから数百年後に刊本の『素庵筆百人一首』から百人一首かるたへの流れで、図像上で改めて皇位を剥奪するのは奇怪なことである。
織田の議論に接していてもう一つ気になったのは、百人一首という歌集のサイズ感の認識である。百人一首が構想された当時には、百首歌というタイプの歌集が何点か登場している。定家と同時代の後鳥羽院をみても、『正治初度百首和歌』『正治後度百首和歌』などがあり、隠岐に流されたのちの時期にも、自身の和歌を集めた『遠島百首』があり、定家、家隆の作品から五十首ずつを選んだ『定家家隆両卿撰歌合』があり、百人の歌人を各人三首ずつ集めた『時代不同歌合』がある。百首というボリュームは、現代の書籍で言えば文庫本のようなお手頃感である。そういう簡便な歌集であればこそ和歌にそれほど深い関心も理解もない人々にまで受け入れられて、後世にかるたという遊技具にも応用されて大流行したのは分かるが、そもそもこういう内容とボリュームの歌集が、定家によって、なぜ御子左家限りの秘本として隠匿され、その活用法はさらに秘匿性の高い口伝、秘伝とされたのかが織田の場合は検討されていないのが気になった。なぜ御子左家の存続にかかわる最重要な秘密の聖典とされ、百人一首伝授という儀式が生まれ、宮中で後水尾上皇自身によって「御所伝授」が行われるまでになったのかが織田説ではよく理解できなかった。
一方、定家に比べると息子の為家(ためいえ)はずいぶん気楽に見える。定家からこの秘伝を授かっており、その際には固く口留めされていたはずなのに、不用意に義父の宇都宮頼綱(よりつな)に口を滑らせてしまい、そこから、歌道の精進に関心のある頼綱(よりつな)が、その秘本の存在を知り、自身の歌道修行の為であろう、自分への教示を強く願い出たので、定家はやむなく『嵯峨中院和歌色紙』という形で提供したというストーリーが頭に浮かぶ。『明月記』によれば、文暦二年(1235)五月一日に依頼されて、同月二十七日に完成させた色紙百枚余りを届けたのであり、この一月足らずの短期間に新たな歌集を新規に構想することなど、到底、不可能である。『嵯峨中院和歌色紙』は、私の推測では、すでに定家のもとにあって息子の為家(ためいえ)に密かに示されたことのある未公表の歌集の和歌本文を色紙に書き出したものにすぎず、百人一首という歌集考案の歴史の中では脇道の作業のことと思われる。この原歌集を示されなくては、贈られた頼綱(よりつな)には収録された和歌の歌順が分からず、したがってどういう順番で色紙を貼るのかも分からない。歌人名にしても、「読み人知らず」が猿丸太夫になるなど、独特の解釈があり、これも分からない。古く安東次男が指摘したように、定家は何らかの成書を添えて贈ったはずである。私も、この「原歌集X」の存在を論理的に前提として考察を進めるべきであると思っていた。
だが、このために、結果的には御子左家の秘本の存在が嵯峨中院の来客である公家たちには知られるところとなり、徐々に情報も流出したであろう。そして為家(ためいえ)が御子左家を継いで当主になってからは、『米沢本百人一首抄』の序注に「定家の私の家色紙(ママ)に書き押されけるを息為家百人一首と名を書きて世上に披露なり」とある通りで、百人一首という題目を付けて世間に披露されて広まったのであろう。他方、これとセットになっていたはずの秘儀を扱う口伝は、二條家では為家(ためいえ)の代で早々に伝承が途絶え、為家(ためいえ)の跡を継いだ為氏(ためうじ)、為世(ためよ)以降の二條家には伝わらなかったのではなかろうか。
なお、為家(ためいえ)の没後に御子左家では相続争いが起きたが、為家(ためいえ)の遺言で、同家に残る歌集や典籍、また定家関連の文書などはすべて三男の冷泉為相(ためすけ)に譲られた。為家(ためいえ)の後妻の阿仏尼(あぶつに)は、実子の為相(ためすけ)の為に奮闘して差配したのであろう。そして冷泉家は京都の屋敷の隅に土蔵を建てて、それらの文書、典籍を時雨亭文庫として収納して神として崇めて秘蔵した。そうだとすれば、定家自筆の色紙の類も冷泉家に伝わって、時雨亭文庫として保存されたはずであるので、その痕跡がない。だから、室町時代に大量に出現した『小倉色紙』と呼ばれる和歌色紙は、冷泉家からの流出とは思えない。たとえば、『嵯峨中院和歌色紙』は宇都宮頼綱(よりつな)の所有物であり、為家(ためいえ)が相続した屋敷の設えになっていたのであるから、冷泉為相(ためすけ)に譲るべき定家の遺品には含まれず、頼綱(よりつな)から為家(ためいえ)に相続された屋敷の付属品扱いで、その家の改築の際に襖障子から剥されて二條家か京極家の子孫に伝わり、のちにその筋から流出したものと考えられる。
和歌の道には、古来、古今伝授という、古今集の解釈、鑑賞を主として、和歌の道の真髄を後継者に伝える、一子相伝、「師弟相承」の秘儀があった。御子左家の本流を自負する二條家では、それが、藤原定家(さだいえ)-為家(ためいえ)-二條為氏(ためうじ)-為世(ためよ)でいったん断絶した後に、-頓阿(とんあ)-経賢(けいけん)-尭尋(ぎょうじん)-尭孝(ぎょうこう)-東常縁(とうつねより)-飯尾宗祇(そうぎ)と伝わり、そこからさらに三條西家に移り、三條西実隆(さねたか)-公条(きんえだ)-実枝(さねき)-細川幽斎(ゆうさい)-八条宮智仁(としひと)親王-後水尾上皇-後西天皇-霊元天皇と伝わり、幕末期(1854~67)まで続いた。江戸時代初期には、三條西家筋の細川幽斎の講じる百人一首の表記が朝廷でも標準作とされ、これを使って後水尾上皇自らが行った「御所伝授」のインパクトも強く、ここに伝えられた表記のものが本流であると認められる大きな根拠となった。そして、朝廷とその周辺には、後陽成天皇『百人一首抄』、細川幽斎(ゆうさい)『百人一首抄』、中院道勝(みちかつ)『百人一首像讃抄』、烏丸光広(みつひろ)『百人一首抄』、後水尾天皇『百人一首聞書』、同『百人一首口訣』、中院通村(みちむら)講・近衛信尋(のぶひろ)記『百人一首聞書』などの注釈書があり、歌集そのものを書いた公家の歌集も多く残されている。近代日本の百人一首のイメージは、こうした、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の二條流による正統性回復の試みのシナリオに乗っており、元禄年間(1688~1704)以降には社会での理解もこの流れの影響を強く受けている。百人一首と言えばつややかな恋話の咲き乱れる雅びな王朝文化を想い憧れるようになったのはこの時期以降の話であり、百人一首の始原の姿とはやや遠い。百人一首かるた史の研究者としてみれば、当時、最も古い慶長、元和年間(1596~1624)のものと考えられていた道勝法親王筆かるたをはじめとして、何点かの江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の百人一首かるたが二條家流の表記ではないことに気付き、すぐにそれが冷泉家流の表記であることを知り、他にも、当時は数点、同様の表記の百人一首歌集が存在することを知り、二條家流の表記は登場していないことも分かってきたので、織田の議論が、頭から二條家流の表記を唯一の百人一首として扱い、冷泉家流の表記のものを無視するのには、相当の違和感があった。
室町時代には、百人一首伝授は「切紙」の形で行われ、二條流中興の飯尾宗祇(そうぎ)以降は、「伝授」は百人一首和歌の解釈、鑑賞を意味していた。そういう物と理解されるようになって、百人一首伝授は古今伝授とつかず離れずの関係になったように見える。定家から発した本来の口伝を受け継いでいない二條家はこう想像したのであろう。一方、私は、こうした二條家の伝承は、元来の百人一首伝授とは違うものであると考えた。もともと、和歌の作品を鑑賞して日本の歌道の真髄を学ぶのは古今伝授のカバーする領域であり、百人一首伝授が同趣旨の所作であるとすれば、それは屋上屋を重ねるものとなる。それも古今集という大伽藍の屋上にプレハブ建ての小屋を載せたような、質量ともに見劣りのするものである。定家が百人一首を通じて和歌の道の真髄を学ばせようとしたのだとすると、代表的な作品を選んだにしては貧弱なボリュームであり、撰歌に際しても不適切な選択が多く、歌人名や和歌本文での数多くの無断改変などからしてもいささか無理な注文である。高齢の父親、定家から、この歌集を手にして、数十年前の式子内親王への慕情など打ち明けられても気味が悪いだけであるし、これも数十年に及ぶ後鳥羽上皇への裏切りへの後悔と、上皇の悪霊への恐怖を懺悔されてもどうしようもない。後悔先に立たず、自分の尻は自分で拭けとしか言いようがなかろう。こんなことを秘伝として末代までの子孫に伝えるのが定家のこの歌集編纂の主旨なのであろうか。私にはそうは思えない。

そこで私は、それは古今伝授とはまるで別の目的を持ったものであり、別に存在し、定家の開発した作歌の作法を駆使して和歌を詠む術を学ぶ作歌術の指南書、職業歌人の家に伝わるべき「歌道の奥義」を伝授する秘本であったのではないかと考えた。定家は歌論の著作が少ない歌人である。私には、それは定家に子孫に伝えるものがなかったからではなく、それを秘伝として口伝の形で残したかったからではないかと理解している。それが、歌学の本家、歌道の家元に代々で伝えられるべき秘伝の味になる。はなはだ非文芸的で、和歌史の専門家からは俗に過ぎると非難を浴びそうだが、私以外にも、何人かの論者がこれは歌道の「教本」だと論じているし、田中紀峰は、『虚構の歌人 藤原定家』で、定家が開発した作歌の技法を「定家ジェネレーター」(歌詞や俳句などを自動生成するプログラムをジェネレーターという)と命名した。百人一首はまさにそのジェネレーターであり、「師弟相承」により、その操作法は他者に明かさない口伝で第一の弟子に伝えられる。紙に書かれた百首の和歌は作歌術のモデル・プログラムの集合体であり、口伝はそのモデルを操作して和歌を作り出す方法を扱うソフトウェアであろう。百人一首という歌集の取扱説明書は不文のものであったのだ。
そう考えるとき、後年に、二條為世(ためよ)と京極為兼(ためかね)の間で相続の争いが起きた際に、京極家側から、「為世卿ニ文書傳ワルニ不ラズ。口伝受ケルニ不ラズ(ママ)」と謗られて、後には、具体的に二條家に伝来したわずかな文書を列挙され、しかもそのうちの相当部分は散逸してしまっていると指摘されても、伝授された書物の実物という証拠を示して反論できなかったことの深刻性、重大性も理解できるように思える。同じく、御子左家の後継者であるというなら、当然に伝わっているはずの「口伝」が示せない。このことも深刻である。ただ、これまでの和歌史研究者は、ここで「口伝受ケルニ不ラズ」とあることに具体的な想像力が及ばなくて、読み流していたように見える。そうではなくて、これは、「小倉山荘色紙和歌」を本当に伝授されたのなら、それと表裏一体になっているはずの御子左家で第一に重要な「口伝」も示してみよ、それができないのは、二條家は正統な後継者ではないからだという、心胆を寒からしめる告発の言葉として理解するべきなのではないだろうか。そしてそれに満足に答えられなかったのが二條家の敗北の理由であったのであろう。
そして、思うに、二條家の系統では、百人一首が秘伝であるという認識は残っていたものの、その具体的な内容は失われてしまったのであり、そこで、飯尾宗祇(そうぎ)以下は、自らの想像で、古今伝授になぞらえて、百人一首の和歌の解釈、鑑賞を秘伝化して百人一首伝授と装ったのであろう。そうすれば、古今伝授と百人一首伝授の差異は少なくなり、両者のつかず離れずの関係が形成されやすい。ひどいときには古今伝授の中にその一部として百人一首伝授が入ったりする。そして、それを継受することが歌道の主の正統な後継者であることの証になる。それは、こうした伝授の内容を創造し、自分たちで管理している二條流、三條西家系統の公家歌人にとっては極めて好都合な展開であったことだろう。
だから私は、和歌の本家の秘儀とされた百人一首伝授の、特に口伝の部分に関する実証的な研究が進み、その正体を明らかにする成果物の出現を心待ちにしていたのであるが、残念ながらそれは現れなかった。その中で、たとえば鈴木元「伝授―『百人一首』受容史の一局面[1]」は「伝授」を中心的な主題に設定した論稿であるのだから、大きな期待をもって読んだのであるが、室町時代の二條流での伝授の経緯をよく見ているものの、それと、鎌倉時代の定家の企図した本来の伝授の始原の姿との異同の関係には及んでいない。鈴木に与えられた課題の設定は素晴らしかっただけに、踏み込み不足が残念であった。
[1] 鈴木元「伝授―『百人一首』受容史の一局面」『國文學』平成十九年十二月臨時増刊号、學燈社、一二四頁。