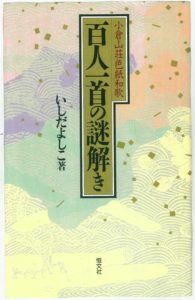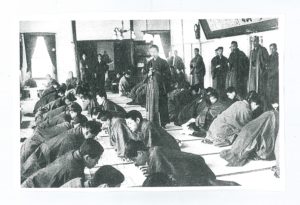織田に触発され、それに次いだのは、林直道『百人一首の秘密―驚異の歌織物』である。これは、百首の和歌を言葉のつながりを鍵にして十掛ける十の方形の中に配置して、そこに後鳥羽院が愛した水無瀬の風景を浮かび上がらせて、この歌集が定家の後鳥羽院への追慕を表現していると解く。織田の発見した言語遊戯という理解を超えて、ヴィジュアルな図像、歌織物として理解する手法は新鮮であり、百人一首が元来は中院の屋敷内を飾る色紙として創作されたことからすると、いかにもそれにふさわしい理解であるように見える。ただ、よく考えて見れば、襖障子の上に、水無瀬の風景が描かれている状態で和歌を書いた色紙を貼り込むには相当な巨大画面を要することになり、寺院の大伽藍でもなければ困難であるし、うまく貼り込めても作者の定家の才能と工夫、技巧ばかりが目立つようになり、贈られた側としては定家の気持ちに違和感が残るのではなかろうか。そして、実際には百枚の色紙を十掛ける十のマス目にすべてうまく収めて貼り込むことは難しい。織田正吉が『百人一首の謎』の「あとがき」で痛切に批判したような林の破綻も顕在化するであろう。嵯峨中院では、一枚の襖障子に二枚の色紙という伝統的な貼り方が踏襲されていたものと判断される。百人一首の全体構造を一枚の画像として認識しようとする試みには相当の無理がある
なお、林は、百人一首と百人秀歌の先後の関係について、原百人一首と呼べるような歌集がまずあり、しかしそれが後鳥羽上皇へ追慕の歌織物であるので、幕府を憚って、その要素を抜いた偽装の別編を作り、それを宇都宮頼綱(よりつな)に贈り、嵯峨中院の屋敷内に襖一枚に色紙二枚で貼り巡らせたが、別室に縦十枚、横十枚で密集させて貼り込み、来客に見事な歌織物を実際に見分する機会を作り、その才能への称賛を得ていたと理解している。他方、定家は、これと別に真実の百人一首歌集の色紙を作り、自身の小倉山荘に密かに展示していたとも推測されている。林の言う原百人一首は、あるいは原百人秀歌と呼ぶ方が適切であるのかもしれない。いずれにせよ、宇都宮頼綱(よりつな)に贈られた色紙歌が、依頼があって数か月で完成できるようなぶっつけ本番で書かれたとは思い難いのであり、それまで数年をかけて練られてきた原作、今は失われている歌集があったことは容易に想像できる。林の指摘には、別室に縦十枚、横十枚で密集させて貼り込んだという想定には賛成できないが、色紙には元になる歌集Xが実は完成していたという大筋には賛同できる。
そして、現在残されている百人秀歌は、嵯峨中院に貼り巡らされた歌人名の表記のない色紙和歌を写し取ったものである可能性もあるが、和歌の歌順の決定、和歌本文の表記、歌人名の記載などが色紙を見ただけでは冊子への編纂は不可能であると思う。歌順は二つの和歌が対句となるように、しかも、身分の高いものが左方に来るように配置されており、歌人名には、久曾神昇(きゅうそじんひたく)が説明したような整然としたこの歌集に固有の基準がある。そうすると、やはりそこには色紙に添えて定家から贈られた、歌順、歌人名などを教える冊子が存在していて、宇都宮頼綱(よりつな)か、彼の娘婿の藤原為家(ためいえ)がそれを写して『百人秀歌』になったものと思われる。ただ、その冊子には百一人、百一首の和歌が含まれているのであって、そこに「百人秀歌」という題目があったかは疑問で、むしろ『嵯峨中院障子和歌』であったように思われる。「百人秀歌」という題目は、この冊子が頼綱(よりつな)か娘婿の為家(ためいえ)から始まり、百首歌に整理されて為家(ためいえ)の三男、冷泉為相(ためすけ)に伝わる過程のどこかで付加されたものであろう。色紙は『小倉色紙』ではなく『嵯峨中院障子和歌』の色紙、つまり『嵯峨中院障子和歌色紙』ないし『嵯峨中院和歌色紙』であったのだろう。そして定家本人は、これと別に、歌順があり、歌人名もある和歌集を作成し、それを息子の為家(ためいえ)に渡し、それを使って作歌術の秘訣を口頭で伝えたのであろう。これが『嵯峨中院和歌色紙』とは別物の『小倉山荘色紙和歌』であり、後年になってから、為家(ためいえ)であろうか、何者かによって百人一首と改められたが、定家自身が百人一首と呼んだ例は残されていない。定家が百人、百首ということにどこまでこだわっていたのかもはっきりしない。林のように、百首を十首掛ける十首の歌織物と理解するには、定家自身が百首という数に決定的にこだわっていたという推測が前提になるのだが、そのこだわりを示す史料は示されていない。私は、百人とか百首とかいうまとまりにこだわったのは定家よりもその後継者、息子の為家(ためいえ)だったのではないかと思っている。『百人一首』という名称も為家(ためいえ)の考案であろう。だから、林の立論には大きな不安が残る。
こうして、『百人一首』は口伝を伴う御子左家の秘本となり、為家(ためいえ)筆のものは二條家に伝わり、これと別に『嵯峨中院障子色紙和歌』という歌集が冷泉家に伝わったものと思われる。冷泉家の時雨亭文庫には、『百人一首』一冊と『百人秀歌』一冊が保存されていた[1]。『百人秀歌』は同家に直接に伝わった定家直筆のものの模本であろうと推定できるが、『百人一首』は後世に持ち込まれたものである可能性が高い。私は、晩年の定家の念頭には、自身が長年苦闘して、せっかく歌道の本山となりえた御子左家の地位をいかに維持するかがあり、頼りない為家(ためいえ)以下の子孫であるが、他家には明かさない秘伝を残すことでいわば歌道の王道の特訓を施し、本山の主らしい実力を育成しようとしたと想像している。
日本の芸道では、武道の世界であれ、演芸の世界であれ、文芸の世界であれ、家元制度が立ち上がり、家元はその後継者ただ一人に奥義を免許状で、あるいは口伝で伝えるのが通例である。定家の気持ちがここにはなくて、歌織物を作成するところにあったとする林の考察は、このお手頃歌集を自家の門外不出の秘伝書とした定家の決心をどう理解するのであろうか。現代の人でも、老境に差し掛かって、ボケも入ってきて発言に締りがなくなり、数十年前の恋話を思わず家族に漏らしてしまうことはあるかもしれないが、それは、ハイハイおじいさん(おばあさん)、もうその話は何回も聞いてます、と聞き流されるものであって、それを、その家の秘伝として、子々孫々まで伝えよと命じる者などいるだろうか。鎌倉時代にはこんな人がいたのだろうか。私にはそういう人間像の理解は分からない。私の考えるところでは、秘伝と言えば、数百年続く老舗の料理屋で、その店にしかない味の出し方、先祖から受け継いで継ぎ足し、継ぎ足しで維持している出汁、たれ、つめの作り方が思い浮かぶ。それがあればこそ、家業がいつまでも一流の店として続けられるのであるが、職業歌人の家での、秘伝の味、神秘のたれに相当するものは、これまで研究者がとなえてきたような、後鳥羽院への思いと式子内親王への想いの追憶なのであろうか。定家は、こんなもので、歌道の本家という地位は維持できると考えたのであろうか。私にはそうは思えない。
なおまた林は、五年後の昭和六十一年(1986)に、『百人一首の世界』を著した。ここでは、前作の水無瀬の風景図を補正しているが、基本は百人一首の説明書であり、この書では、かるたの歴史や宝塚歌劇団の女優たちの芸名など、通俗的な解説書のような軽い文章が続く。肝心の歌織物に関する部分は相当に端折っており、前作を参照せよという指示が目立つ。そしてその代わりにこの書では、水無瀬の現地に足を運んで得た、定家の選歌が水無瀬の情景を細部にわたって的確に取り入れているとの発見が全面的に展開される。また、平安時代の水無瀬の地域史の出来事も組み込まれていることも発見されている。この辺は独自の世界観で、外からは言うべき言葉がない。ただ、林の主張に批判的で、それは恣意的で、その手法であればどんな絵でも想定できるとした者たちから見れば、林の説明が細かくなればなるほど、どうとでも言えるという批判が当たっていることの例証に使われてしまうのであろうと思われる。
織田、林に次いだのは、小林耕『 百人一首 秘密の歌集―藤原定家が塗り込めた「たくらみ」とは』である。小林は、百人一首が定家の御子左家の秘伝であることを重視し、その存在を隠すために作られたカモフラージュが百人秀歌であるとする。そして、百人一首は、歌順一番から六十四番までは中国の易経六十四卦に対応し、六十五番から百番までは三十六計に対応すると説明する。きわめて斬新な考え方であり、百人一首が秘本であることを正しく見抜いて考察の基礎に置いている点は同感できるが、歌順が複数あることへの目配りがないと、説明がうまく成り立っていないように見える。
まず、百人秀歌は、宮内庁書陵部で発見された冊子はその表題が『百人秀歌 嵯峨山庄色紙形 京極黄門撰』である。元来は色紙に書かれたところを冊子に纏めたもので、「京極黄門」が制作したという事情を説明している。色紙を冊子に写したのは定家本人ではなく、しかも、その者は定家を「京極黄門」と呼ぶ立場の者であったのである。
ここでもしその者が、御子左家の正統、二條家の者であれば、傍系の「京極」の名を冠して京極黄門とは呼ばない。だから、この書物は、定家の息子の為家(ためいえ)の没後に、その息子、定家からすれば孫の世代に御子左家が二條家、京極家、冷泉家の三家に分裂した後に、京極家に伝授され、それが京極家周辺ないし冷泉家周辺の者によって写されたことを示唆する。このほかに、のちに発見された二部の『百人秀歌』では、その祖本が冷泉家に伝わっていたことが分かっている。他方で、二條家の系列からは百人秀歌は発見されていない。また、もし、百人秀歌が秘伝の百人一首を隠ぺいするためのカモフラージュであるとするならば、それが肝心の二條家に伝わっていないことは理解しがたい。この辺は小林の説明に同意しかねる。
また、百人一首が秘伝で二條家に伝わったとすると、冷泉家に伝わった、百人秀歌に近い歌順の配列、歌人名、和歌本文の表記を持った異本系の百人一首はどう説明されるのであろうか。小林の議論は、二條家に伝わった百人一首の歌順がそのままの順番で易経の卦の順番に対応し、あるいは三十六計の順番に合致するものであるという前提で組み立てられており、こうした事態の合理的な説明が難しい。三家分裂のころに、秘伝の存在を冷泉家に知られたくないので、欺くために、百人秀歌に近いが歌順が狂っている偽書の百人一首を二條家がわざわざ制作し、それを冷泉家に与えることで欺瞞したとでも説明するのであろうか。これは私の想像力の範囲を超えている。小林がその独自の理解を組み立てた当時は、まだ冷泉家に伝わった異本系の百人一首の存在は一部の研究者の間でのみ知られており、広く社会的には明らかになっていなかった時期であるから、それを求めるのは酷な話ではあろうと思うが、いずれにせよ、結果的には、小林の議論はその史料的な基礎が崩壊している。
しかし、私は小林の著作を高く評価したい。というのは、小林は、歌道が御子左家の家業となっていて、定家は、頼りない為家(ためいえ)らの子孫を見て同家の衰退、滅亡を危惧し、それを防止するために秘伝の教本を制作しようとしたと見たのである。私も、同じような、何事かに使うツールとしての百人一首という印象を持っていた。そして、こう理解することで、百人一首というお手軽な歌書にまとわりついている妙な秘密性、教材であればあえて許される愚歌、凡歌の採択、あるいは教材に転用する目的でなければ先人の冒涜として許されないような定家による多くの赤ペンの跡なども、ツールとして必要な装備であったのだとすれば、天下の名人、定家の行いとしても合理的に説明できる。定家が、このような愚作、凡作でも、私の作歌術の数々を駆使すればこのように一応は見られる和歌になるのであると教示する場面が浮かぶ。こういう意味合いで、私は小林が教本だと見た点は評価するのだが、その先に、易経説に走ってしまったことをとても残念に思っている。
小林と同年に現れたのが、吉海直人「百人秀歌型配列の異本百人一首について」である。これは、織田以来の論議に直接は触れることなく、和歌研究史の新発見として公表されたものである。主旨は、要するに百人秀歌型の配列の百人一首が複数存在するという指摘に尽きる。吉海は、それ以前の吉海の百人一首研究からは想像もできない、まるでレベルの違うこの論稿を突然に公表したのであり、標準型の百人一首歌集と歌順が違うことは、従来は誤編集としていたのだが、そうではなく、異本というべき別系列であることを示唆している。研究者には、ある日不意に天から天使が舞い降りてきて画期的なアイディアを啓示するときがあるが、吉海は、和歌史研究者の中で誰一人気付いていなかったこの問題に突然に目覚めて、「天使にもらった歌」を歌うように説明している。
ただ、これはすでに書いたことの繰り返しになるが、昭和末期(1985~89)の東京の百人一首かるたのコレクターや研究者の間では、江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)のかるたがここで言う異本系の表記であることは、歌仙図像のうち崇徳院に皇族の印の繧繝縁(うんげんべり)の畳が描かれていないこととともによく知られており、この独特の表記の元が、当時は東洋文庫に出かけないと原本が閲覧できなかったのだが、その東洋文庫での調査を行って、角倉素庵筆の百人一首本、『素庵本』であることも理解できた。また、『別冊太陽愛蔵版 百人一首』の写真版により、素庵と親しい世阿弥光悦の百人一首の古活字本の表記もこれであることを知った。崇徳院の畳の消失については、『素庵本』で、天皇、上皇と式子内親王には繧繝縁(うんげんべり)の畳があるが、崇徳院と元良親王にはそれがなく、また、祐子内親王家紀伊と待賢門院堀河も誤って皇族扱いであり、それがかるたの歌人図像に影響していることが分かった。ただ、私は、その理解を開拓した一人であるが、かるたの場合は和歌が百枚の札に分割されていて、それが制作された江戸時代初期(1603~52)にどういう順番で考えられたのかは分からず、それを今日の常識で標準型の歌の順番に並び替えることには支障がないので、歌順の違いがあることは、『素庵本』、『光悦古活字本』の刊本を見るまでは気付かないでいた。そして、歌順の違いを知った後も、「光悦の百人一首は歌仙の配列順序が、一般に伝承されたものと若干違っている」という森暢、吉田幸一の説明に納得していた。そのことに特に留意してはいなかった。
事情が変わったのは、私が、田中宗作の『百人一首古注釈の研究』を読んでいて、論文「如儡子の百人一首注釈書について」に出会ったからである。そこには、水戸の彰考館にある江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の人、如儡子(にょらいし)の注釈書『百人一首抄』では、「作者歌の並べ順が普通のものとはいたく異なっている」と書かれており、そこで紹介されている和歌の順番は、光悦本と同じであり、元は百人秀歌本と同じであった。これを知った時、私は、もしかしたらこの差異は森や吉田が言う「若干違っている」という程度の軽いエピソードではないのではないかと思い、何点かの史料を調査し直し、また、かるた史研究仲間の山口格太郎や村井省三らとも協議して、確かにこの異本系の百人一首の表記が潮流として存在しており、その根源は京極家ないし冷泉家に在り、それは根源が二條家、三條西家にある標準型のものとは別系列であることが分かった。今となっては当時の記憶も朧げであるが、昭和六十年(1985)からその翌年にかけてのことだったように思う。ただ、田中の著作に触れたときの衝撃は昨日のことのように鮮明に記憶しており、道を開いてくれた田中への感謝と敬愛の気持も当時のままである。
その後、吉海が和歌の研究会でこの報告をしたのであるが、私はその事実を知らなかった。少し遅れてそれを知った時には、東京のかるた史研究者の間では既知の学術情報を自己の新発見であるかのように語るのはいただけないが、関西の大学の先生はこういうことをするのかと認識を改めた。だが、私たちは、自分たちの発見を特に和歌史の研究世界で発表したり、学界に情報提供したりする予定はなかったのだから、吉海がそれを行ったことには特別に悪い印象はなかった。ただ、吉海に本当に天使が舞い降りたのかどうかであるが、吉海が文中で、いかにも収まり悪く田中宗作の著作に触れるのは、かるた史研究者からの伝聞以外には知りえない些末な情報であり、同書を数十年勉強して見過ごしていたはずの吉海が、今回突然にこの部分の記述に辿り着いたというのはいかにも不自然であり、現実にはありえないことなのに、これも自分の発見になっているのには、こんなにすべて「天使にもらった歌」だなどと無理をせずに、東京でカルタのコレクターから聞いたと書けばもっと気が楽なのにと笑った。いずれにせよこれで、冷泉家に伝来したと思われる「この世に」表記の百人一首歌集の存在が吉海の努力によって和歌史研究者の間に知られるようになることは良いことと思っていた。
一方、吉海は、「天使の歌」学説をくりかえした。平成十年に刊行した『百人一首への招待』では、「私自身、何百本もの百人一首の写本・版本を調査してきたにもかかわらず、しばらくの間は配列が乱れているものがあるくらいにしか考えていませんでした。ところがある時ふと気がついて、おそるおそる百人秀歌の配列と比較してみたのです。まさかと思ったのですが、ものの見事に一致しました。その時の興奮は今でも忘れることができません」となっている。このストーリーは、要するに吉海は歌順の違いという一点の情報で異本百人一首を認識したという歌順一点主義を物語るのであるが、前作の論文「百人秀歌型配列の異本百人一首について」で、歌人名では家隆が「従二位」か「正三位」か、和歌本文では二條院讃岐の和歌が「わが袖は」か「わが恋は」か、それが歌順と並ぶ識別の指標、基準にならないか追及していたストーリーとは微妙に食い違うので、真実はどこにあったのかが分からないのであるが、それはさておき、いずれにせよ世紀の大発見のストーリーはこうして増幅していた。
他方で、私たち、かるた史研究者の間での認識は、標準型かるたの百人一首と江戸初期型かるたのそれとの相違点は、①歌順のほかに、②歌人名の表記、③和歌本文の表記に及んでいるというものであった。私たちが特に問題にしたのは、②の歌人名表記では、「権中納言敦忠」(標準型かるた)か「中納言敦忠」(江戸初期型かるた)か、「大僧正行尊」(標準型かるた)か「前大僧正行尊」(江戸初期型かるた)か、「権中納言匡房」(標準型かるた)か「前中納言匡房」(江戸初期型かるた)かであり、③の和歌本文の表記では、三條院の和歌の表記が「心にもあらで憂き世にながらへば」(標準型かるた)か「心にもあらでこの世にながらへば」(江戸初期型かるた)か、源俊頼の和歌の表記が「憂かりける人をはつせの山おろし」(標準型かるた)か「憂かりける人をはつせの山おろしよ」(江戸初期型かるた)か、俊恵法師の和歌の表記が「夜もすがら物思ふころは明けやらで」(標準型かるた)か「夜もすがら物思ふころは明けやらぬ」(江戸初期型かるた)か、であった。これらの諸点は、かるたの場合は、元禄年間を境に江戸初期型かるたから標準型かるたに雪崩を打つように変化するポイントであるので、特に問題にした。またもう一点、これはかるたについてのみ固有の問題点であるが、崇徳院の歌人図像での畳の描写が皇族位の繧繝縁(うんげんべり)ではなく、他の歌人と同様の高麗縁(こうらいべり)であったものが、同じく元禄年間頃に繧繝縁(うんげんべり)に改まったのも気になっていた。
これに対して吉海の論文は、②の歌人名表記の相違は気付くことができなかったのか見逃しており、ただ、自分で実証的な研究をしなくても分かる、以前から取り上げられてきた家隆が従二位か正三位かという既知の論点にのみ言及しており、その立ち位置も「従来のように作者表記の相違を絶対視しての立論は、そろそろ見直されるべきでしょう」と気楽なものであった。③の和歌本文の異同についても、吉海以前から議論されていた「わが袖は」か「わが恋か」という既知の問題点には言及しているが、三條院については「なお、百人一首諸本の中には『この世』という本文異同もありますが、それは天皇歌として感情をあらわにするのはふさわしくないということで、改訂されたのでしょう」という、いつ誰が天皇の歌にこのような不敬な改訂をしたのか、実証的な証拠を一切示さないままの怪説を説示しているだけであり、源俊頼については以前から「山おろしよ」と呼び掛ける優れた形を「山おろし」と平凡な表記にしてしまったことの是非が和歌史研究者の間で問題視されてきたことも忘れたのかパスであり、俊恵法師の「明けやらぬ」か「明けやらで」も、これもすでに和歌研究者の間では注目されていた点なのにこの辺の勉強も足りないのかパスである。
そして、同書の公刊直後に、私は、当時赴任先の中国、北京市内の日本学研究センターで、たまたま吉海と会う機会があったので、直接に口頭で、かるた史学が明らかにしてきた江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の百人一首かるたの識別に関する以上の判断基準を指摘して、吉海に再考を求めた。吉海はその場では押し黙って下を向いて聞いていただけであるが、帰国後に、それまでの、かるた史研究者の先行研究を無視して、考証に欠ける和歌史の素人論議だと歯牙にもかけないそぶりを改めて、私を積極的に攻撃してくるようになった。
たとえば、平成二十年(2008)刊の『百人一首かるたの世界』において、吉海は、私が、かるたの場合は和歌が歌順の記載なくかるた札に切り離されているので歌順は特定しにくいが、①歌人名の表記、②和歌本文における「この世に」表記と「憂き世に」表記のように特徴的な異同、③崇徳院の畳の表現などの歌人図像の特徴、の三点を中心に、それが『素庵本』の強い影響下に成立していると論じているが、それは本文の校訂作業をきちんと完成させなければ踏み込めない世界であり、素人の江橋にはできていないと批判した。だが、吉海がここで専門研究者による緻密な校訂作業の見本として示したものは、「浄行院かるた」という江戸時代前期(1652~1704)のかるたに、二條流の近衛流百人一首の歌集の表記と密接な関係が有るので、むしろ二條流の百人一首の影響があるという指摘だけであった。私たちは、もちろん、この程度の例があることは知っていた。
かるたの制作工程からすると、かるた屋は、まず絵師に歌人図像を描かせて、その後にそれをかるた札大にして裏紙などと張り合わせてかるた札の形に加工して、その後に書家に歌人名と和歌本文を書かせていたと理解される。通常は、書家は、歌人図像によって残された空間に素庵本や尊圓本に従って冷泉流の表記をする。その際には、歌人図像の形次第で空間が決められるので、その空間に合わせて文字を加えるのであり、四行分かち書きのように決まった形で統一して書くものではない。また、時には興に乗ったのか、乱れ書きの札にしたりもしている。歌人図像の隙間に文字が書かれているのであって、まず書があってその隙間に歌人図像を描いたのではない。そして書では、書の形だけでなく、その内容にも書家に独自の見解があって、「浄行院かるた」のように歌人名で「権中納言敦忠」、和歌本文で「憂き世に」などと二條流の表記に従って書くこともありうる。このように理解しているので、浄行院かるたのような歴史上のバグのような例外があるからと言って、時代の傾向を見失うことはない。
吉海はまた、同書で、崇徳院の畳の図像について、寛保年間(1741~44)の書物にも繧繝縁(うんげんべり)でない例があるので、「一七五〇年頃がターニングポイント」だとする独自の見解を述べて私の説を否定した。実は、この問題について、上記の『百人一首への招待』では、どこで聞きかじったのか、無邪気にこの論点に触れ、「近世初期に崇徳院が臣下扱いにされていることは、百人一首絵の謎の一つと言えます」と書いていたのだが、この時期になると、こう書いた自分を忘れたのか、崇徳院に繧繝縁(うんげんべり)の畳がないのは何も江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)のかるたに限ったことではなく、江戸時代中期(1704~89)のかるたにもあるのだから「近世初期の謎の一つ」などではなく、かるた制作の年代測定の基準としては使えないと、積極的に私の発見の史料価値を潰しにかかってきたのである。私のことはさておくとしても、こうした吉海の言説が、崇徳院への不当な謗りを改めようと努力した延宝年間(1673~81)の百人一首歌人絵の改革者、絵師の菱川師宣の努力や、元禄年間(1688~1704)に師宣風の繧繝縁(うんげんべり)の畳を加えた図像が流行して百人一首かるた絵の世界で支配的になったという百人一首かるたの歴史を全く理解できていない初歩的な誤りであることは明らかで、はなはだ残念であった。
吉海は、また、同書で、異本系百人一首の存在について、「江橋崇氏も少し後に報告されています」と、自分の方が先行研究だと主張している。そして、私の指摘は、配列の不透明なかるたにまで踏み込んでいるので不安だとして批判している。「すぐに浮上してくるのは、歌仙絵のもととされている素庵本の扱いです。かるたが異本百人一首の本文に依拠しているとすると、歌仙絵だけ素庵本に依拠し、本文は別の異本百人一首に依拠したことになります。そうなると配列が異なっているのですから、歌人と歌がずれる可能性も高くなります。そんなややこしくて危険なことをするでしょうか」ということである。
これを読めば、吉海が、私は、初期のかるたは『素庵筆百人一首』を手本にして成立していると主張していることは明らかである。だが、吉海にとって残念なことに、私は、発祥期の歌人図像付き百人一首かるたには『素庵本』を手本としているものもあるが、おおむねは『素庵本』の歌人図像を模倣した『尊圓本』を手本として成立していると理解している。この『尊圓本』では、歌順は二條家流の、つまり標準型の百人一首に従っているが、歌人名も和歌本文も、その表記は『素庵本』に依拠しており、その大本となった光悦本は冷泉家流の表記であり、だから尊圓本も冷泉家流の表記である。かるたを制作するときには、『尊圓本』を参考にすれば、本文表記は冷泉家流、歌人図像はほとんど土佐派の絵師の提供した『素庵本』の百人一首歌人図像の模倣となり、何点か写し間違いがあるとしても全体としてはきちんと成立する。細かく見れば、歌順は光悦本が百人秀歌と一致しているのを標準型の百人一首の順序に改めており、歌人名は「中納言敦忠」「前大僧正行尊」「前中納言匡房」「正三位家隆」である。和歌本文の表記では三條院は「この世にながらへば」であり、源俊頼は「やまおろし」であり、俊恵法師は「明けやらぬ」である。したがって、吉海が言うような「歌人と歌がずれる」危険性はないし、「ややこしくて危険なこと」ではまったくない。
こんなことは『素庵本』と『尊圓本』を一読すれば高校生でも分かることであり、吉海が、実は『素庵本』や『尊圓本』すら実証的に研究していない、両本を読み返す手間も省いて他人を攻撃している事情を露呈してしまっている。その結果は、いわば、吉海の誤爆である。そして、こういう実証的な研究の苦手な吉海が、果たして独自に、歌順が百人秀歌と同じ百人一首があると気付くことができたのだろうかという疑惑も巻き起こるのである。その意味では吉海の自爆である。
吉海の論述には、この種の誤りは膨大に存在する。私は、吉海の指摘には実証的な研究による裏付けがないと繰り返し指摘しているが、こういうことなのである。吉海のこういう誤りを列挙すればキリがないが、そうすることにはかるた史研究にとっての客観的な価値がないので読み捨てにしている。
いずれにせよ、かるた史研究者の側からすれば、吉海が、そもそもの出発点で、「ある日天使が降りてきて天啓を示された」ではなく、「東京でカルタコレクターから聞いたことに触発されて」と書きさえすれば何の問題も生じず、和歌史の学界に紹介したという吉海の功績にも別に傷も付かないのに、なぜ、自分は無人の野を行ったのだと自慢し、先行業績を歯牙にも掛けないそぶりをしたのかがさっぱり理解できなかった。また、吉海は、三條院の和歌の表記が、冷泉家系では「この世に」で、二條家系では「憂き世に」であるという重要な相違点は知らなかったのであり、刊本とかるたで崇徳院の絵札に繧繝縁(うんげんべり)の畳がないことも知らなかったのである。これも、かるた史研究者の側からは、こうした情報を提供して吉海の研究が実り多いものになることを期待することにはやぶさかでなかったし、実際に北京で直接に教示したし、これを秘匿して対抗したり、吉海こそ中途半端な考証だと罵倒し返したりする意図もなかった。たとえば崇徳院像の畳の表現については、当初はその問題点に気付くことができなくて完全に見逃していた吉海が、途中で自分の発見であるかのように書いて、その辻褄が合わなくなってくると、また立場を変えて、今度は、こんなことは些末なことで、繧繝(うんげんべり)縁の畳のない崇徳院図像などは時期的にもズルズルと江戸時代中期(1704~89)の半ばまで長期にわたって制作されていて、制昨年代判断の決め手になんぞなりはしないのだと罵倒したように見えた。この態度の豹変も理解できなかった。
一般に研究者の世界では、先行する研究のアイディアを知ってそれを着服し、いち早く論文を発表して出し抜くとともに、自己の研究の独自性、先行性をことさら強調して真実の先行研究を否定し、あるいはそれがいかに不完全で先行研究とは言えないかを告発することで抹殺しようとして、実際には摩擦を起こして問題になることがある。理科系や医学系、薬学系の研究者の間では特許権の問題も生じるので、争いは分秒単位でし烈であり、ライバルの業績への不当な攻撃も日常茶飯事である。そういうことが身近で起きたのかともいぶかしく思った。
例えば吉海は、当初は、自分はもっぱら歌順の情報からだけで異本百人一首を識別したとする歌順一点主義であり、江橋は歌人名や和歌本文の表記の揺れなどまで素人のくせして取り上げていると批判していたが、いつの間にか歌人名も和歌本文も吉海による検討の対象となり、ついには、『百人一首かるたの世界』では、私の歌人名と和歌本文の表記の揺れに関する基準をさらに拡大した、吉海流の歌人名と和歌本文の比較表を作って、私の分析が不十分で誤りであると主張するまでになった。簡単に言えば、私の手法を採り込んで、自分の基準の方が詳細で正確だと主張したのである。標準型の百人一首と異本百人一首の区分論では、歌順の比較だけでは不十分で、歌人名や和歌本文も比較する江橋方式が良いが、その場合でも実際には素人の江橋よりも専門家の自分の方が優秀であるとして、標準型のかるたと冷泉家流の初期かるたの分類基準をいつの間にか自分のツールにしてしまった。自分は和歌の配列の相違に気付いてそれだけで異本百人一首を発見したのであり、「その時の興奮は今でもわすれることができません」と感動を告白していた歌順一点主義の吉海はいつの間にかどこかに行ってしまった。この比較表については後にもう一度扱う。私の比較表と吉海の比較表を比べれば、どちらの方が詳細で正確で、いわば本家の味を出しているのかは一目瞭然であろうけど。
私たちはかるた史の研究者であり、吉海はその方面では研究実績のない素人でもっぱら和歌文学史の研究者なのだから、自分の研究の境界を守っていれば衝突することなどないはずなのであり、吉海の意図を計りかねたが、いずれにせよ吉海からの攻撃は残念なことであった。
なお、この頃、古書展で、百人一首の色紙を何回か見かけた。中には、「小倉山荘色紙和歌」との題が付いた木箱に収められて大事に保管されて来たことをうかがわせる古いものも何点かあった。それらを見ると、和歌の表記は「この世に」タイプであり、江戸初期型かるたの表記であるが、ただ、古書展では、いずれの場合も、売り出した業者によって、二條家流の標準型の歌順に揃えて出品されており、それが江戸初期型かるたの百人一首の色紙であることが見えにくくなっていた。古書展では買い手が付かずにしばしば売れ残っていた。私は、当時は、財布の事情もあり、展示会の会場で見ることで満足して購入しなかったが、あれらはどこに行ったのだろうと思う。これまで、色紙型の百人一首についての捜索を試みた例を知らないが、それを進めれば何か重要な史実が見えてくるのではないかと、逃がした魚は大きいに似た気持ちが今でもある。この色紙形の史料群の掘り起こしと活用については、令和年間の新研究に期待するだけである。

「小倉百人一首」特集
さて、この時期に、織田庄吉ショックに真正面から対応しようとしたのが、『國文學』臨時増刊号「小倉百人一首 詞人の饗宴、雅のレトリック」(學燈社、平成四年)であった。ここには、従来の百人一首研究の延長線上の論文もあるが、私が特に興味をひかれたのは、百人一首という歌集についての史料批判の視点を持った論考と、織田庄吉およびそれの後に続いた林直道の問題提起に真正面から答えようとする論考である。前者では、樋口芳麻呂「歌仙ということ」、川村晃生「和歌史としての百人一首」、増田繁夫「百人一首批判」、塚本邦雄「身をば思はず」、竹西寛子「文化の本歌取り」などが、様々な角度からこの歌集の成立を分析している。各々の論文が、個々の論点ではいずれも鋭い問題提起を行っており、とくに川村晃生「和歌史としての百人一首」、増田繁夫「百人一首批判」は、その論文名が示しているように、百人一首という歌集の史料批判の趣旨が明確で、外部の領域の研究者にも理解がしやすい。ただ、定家がこれを編んだ根本的な動機、目的についての新説の開陳、素人にも分かりよい明快な説明は乏しい。百人一首とは何者なのかという根本的な問いかけに対する積極的な答えは示されていないように見える。
また、村尾誠一「百人一首は歌織物か」は林の歌織物説を批判し、錦仁「百人一首に暗号は隠されているか」は織田の問題提起を正面から受け止めて批判しており、今井明「後鳥羽院は百人一首を知っていたか」は定家と後鳥羽院の関係を検討して、織田、林が極端に強調している、定家による後鳥羽院への追慕という趣旨への疑念を示している。いずれも、和歌史研究の専門家としては織田や林の挑戦はその素人っぽい初歩的な誤りが耐え難いということであろうか。あるいは、「この林氏の《歌織物》説をめぐって、表題(百人一首は歌織物か)のごとき問題を考えよというのが、本稿に与えられた課題である」(村尾)、「編集部の依頼は、織田庄吉氏の説に触れながら百人一首に〈暗号〉が隠されているか検討せよ、というもの」(錦)、「定家の後鳥羽院への思いといったものを『百人一首』から抽出した時、一方の後鳥羽院は定家にどのような思いを抱いていたのであろうか。それは資料的に追跡できるのか、『百人一首』をめぐってそれは可能なのか。私に与えられたテーマはその辺りの問題意識から出てきているのであろう」(今井)と書いているところからすると、雑誌の編集部ないしその助言者の主導なのであろうか。歴史研究の水準で考えればごく当たり前のことであるが、従来の百人一首史研究では不足しがちであった資料を提示しての考察が展開されていて、理解がしやすい。だが、ここでも、それならば百人一首とは何者なのか、と言う問いへの積極的な自説の展開は少ない。要するに、織田、林という目障りな杭が的確に打たれているのである。
もうひとつ、私が興味深かったのは、塚本邦雄「身をば思はず」である。塚本は、江戸時代の戸田茂睡さながらに、百人一首への厳しい批評を繰り広げている。歌人の塚本らしい視点であると思うし、塚本にはほかに百人一首に登場する百人の歌人のもっと別の和歌を集めた『新撰小倉百人一首』があるように、百人一首における定家の選歌の基準を真正面から批判しているところは小気味よい。ただ、それ以上に興味深いのは、塚本の文章が終盤で急カーブして、百人一首関係の書籍が、百人一首かるたからの影響で、機械的な上の句、下の句の二分法に変質していることへの批判に転じていることである。「百人一首の解説はこの十年数年(原文ママ)でも幾種類かが数えられるが、とある特集の一部を分担した人が、百人一首をかるたとして享受する功徳をしきりにのべたて、これぞ人生最良の教科書と称えていた。私は反対である」。なぜならば「この読札・取札と、一首を機械的に二つに分けて、初句切・二句切・四句切の別なく、一切三句切視する弊害は言後(原文ママ)に絶する。生物識(なまものじり)に限ってこういう迷論を吐く」からである。塚本はさらに言葉を重ねて、「近年のかるた取り競技大会とやらの堕落・乱脈振りは沙汰の限りで、NHKが放映紹介すること自体心ある人は眉をひそめているが、それはさておき」と激しい。だから「「百人一首」関係の書の続刊されるのはめでたい。氾濫しても私の容喙すべき問題ではない。ただ「かるた競技」のためにやむを得ず三句切れの上・下で区切り、十把一紮(から)げに処理することわりを、解説の一端に加えておくべきであろう」ということになる。
私は、これほど真正面から「競技かるた」の非文芸性を指弾した例を知らない。私も、江戸時代初期(1603~52)以降に始まった歌かるたの遊技であるのに、それより数百年も以前の平安時代、いやそもそも「百人一首」という歌集が成立した鎌倉時代中期よりも以前の平安時代の衣裳を着せて正月に行わせ、使用する札は、江戸時代はおろか、はるか後世の明治後期(1903~12)以降にできた鉛活字の文字を用いて、一枚の札の上に、江戸は佃島の干し場の海苔のように端から順に五文字、五文字、四文字と並べて印刷した機械生産品という競技かるたは、文芸の遊技から遠く離れてしまった屋内スポーツだと認識しているが、これがあったおかげで「百人一首」は「源氏物語かるた」や「伊勢物語かるた」「古今集かるた」「自讃歌かるた」などのように明治年間(1868~1912)に衰退してしまう運命を免れて生き延びたのであるし、そもそも和歌を三句切で上の句札、下の句札に二分して遊技に使うのは「競技かるた」の発案ではなく、江戸時代初期に「歌合せかるた」が成立した時からの伝統であるから、その責めをすべて帰せて「堕落・乱脈」とまでは考えていない。いずれにせよ、塚本の暴走は和歌の文化を愛する歌人の言として共感するところがあった。
こうした様々な論考を含んで、この特集には、専門職業家と外部者の間での議論の応酬への道が開かれる希望が感じられた。だが、その後、これを受け継ぐ続編の特集は同誌に現れず、両者がその見解を直接に披瀝しあって討論して史実に近づこうとする企画も現れず、フォーラムは、同誌にも他誌にも現れず、相異なる知見を集合、集積して史実に迫る試みは消えていった。摩擦はそれを許さない程に激しかったのであろうか。ここで少し開きかけた扉はまた固く閉じられたように思える。その後、それなりに見識のある外部者がそれなりに根拠を示して疑問を投げかけて問題提起しているのに、大学教員という職業的研究者たちがそれに応答することなく、二十年以上も鑑賞と考証がごちゃ混ぜの文章で職を繫ぎ、外部者の論考は死屍累々と積み重なっているのを見ると、ここで開かれかけたフォーラムが結局成立しなかったことがいかにも残念である。
西川芳治『百首有情 百人一首の暗号を解く』は、この時期に現れ、織田説に大きく影響されつつ、百人一首と百人秀歌に隠された暗号を独自に解読している。百人秀歌は『最勝四天王院名所障子和歌』八首を文字鎖で隠し、百人一首は隠岐の後鳥羽院と佐渡の順徳院を思いやり、その帰京を願う心で編まれているというのである。ここでもう一つの先行業績は歌織物だと主張する林の著作であるが、西川の林への評価は低く、影響は受けていない。織田のインパクトの強さはこういう構成にも現れている。西川は、織田説のうち、後鳥羽院への思慕は受け入れているが、式子内親王への恋情は削除している。この程度の違いはあるが、これはいわば織田説の変奏曲のようなものである。
次に登場したのが松村雄二『百人一首 定家とカルタの文学史』である。これは、平成六年(1994)の夏に国文学研究資料館で開催された「夏季原典講読セミナー」の三回の講義の記録であり、専門家が素人に諭す内容になっている。表題は「定家とカルタの文学史」であるが、百人一首かるたに関しては新しい知見はなく、看板倒れの感がある。だが、百人一首という歌集の発生史に関してはさすがに専門家で、史料の考証も確かなものがある。ただ、もっとも肝心の、定家がなぜ①百首歌という形式で、②和歌史のエッセンスを取り出し、それを③御子左家の秘伝としたのか、という織田正吉以来繰り返し提出されている疑問に対しては、それを総合的に理解する明快な説明はない。それがこの時期の専門家の研究の水準であったのである。
まず、①の百人一首が百首歌である理由として、松村は、後鳥羽上皇が流刑地の隠岐で制作した『時代不同歌合』という百人の歌人を選んで左右に分けて歌合の形にした歌集への対抗意識を挙げる。後鳥羽上皇の仕掛けは、時代の異なる歌人を対抗させる仮想の歌合せを設定してその優劣を見るという恐ろしく超歴史的な、恐ろしく上から目線のものであり、いかにも和歌史の全歴史を差配する歌道の帝王という自意識にふさわしい。これに対して定家は、和歌の全歴史から百人の歌人を選び出すという、これもまた超歴史的な上から目線であるが、百人百首に縮減することで、誰にでも理解しやすく、暗記しやすい、いわば歌道の入門書的な通史のテキストを制作している。この、初心者でも理解できる入門書的な通史を百首歌という手ごろな歌集の形で制作しようとした定家の意図は、御子左家の初学者向けの歌道史のエッセンスの教科書の作成であり、その発想ははなはだ積極的であり、革新的であり、前向きであり、後鳥羽院への対抗意識などという消極的なレベルをはるかに超越しているように思える。後鳥羽院との関係にこだわる松村の理解には違和感が残る。
次に、②の和歌史のエッセンスを取り入れるという点であるが、さすがに松村もこれには言及している。定家は、百首の和歌を通じて、作歌の作法の要点を示していると思う。特に、序詞、歌枕、掛詞などを取り入れるモデルになるような和歌が多数取り上げられており、和歌の技巧を学ぶには格好の手本と言える。また、和歌の主題で言えば、春の歌は春の訪れ、草花の芽吹き、花の盛り、散花の情景、初夏への季節の移ろいなどが取り上げられ、恋の歌では、恋心の発生、相手方への発信、通い合う心、逢引きの約束、夜を共にした喜び、朝の別れ、恋人の間に立つ秋風、別離の悲しみ、孤独の寂しさ、死んだ元恋人への追慕などが取り上げられている。和歌の初級者が和歌の主題に思い至った時に、その主題にふさわしい作歌の先例が示され、本歌取りの手法などを用いれば天才でなくともそれなりの作歌が可能なモデル歌集になっている。定家ジェネレーターの適用できる範囲は広い。
そして、③定家が、山庄色紙ないし百人一首を御子左家の秘伝とした趣旨であるが、すべての勅撰和歌集から定家が撰んだエッセンスである和歌百首を学び、その歌人について学べば、とりあえず和歌の道に通じたことになる。御子左家の者は、この歌集を秘伝として家中で密かに学ぶことになり、他派、他流の者と接触する歌合などの機会においても、他流の者は御子左家の者の発言の根拠を知らないので、歴代の勅撰和歌集に通じているその学識に圧倒されるし、また、定家から口伝で密かに伝えられる作歌の作法を駆使すれば、技巧に長けた定家風のそこそこの和歌が誰にでも作れる。こうして御子左家の者が、定家風の歌風を守り、歌壇での優位を確保することが、定家が百人一首という冊子を御子左家限りの秘伝とし、特に作歌の作法を記録に残さずに口伝、秘伝にとどめて家外に流出しないようにした趣旨であろう。
定家は、早くから幕府に迎合して要人と交際し、鎌倉の意向を背景に勅撰和歌集を俊成(としなり)、定家、為家(ためいえ)と三代にわたって単独で編纂することとなり、和歌の道の本流の格式を得た。これは当時の歌人公家としては破格の成功である。そして、大事な点なので繰り返し書くが、定家は、自分ほどには天才でない家中の者、あるいは子孫が、将来にわたっても本流の格式を継続できるように、密かな指南書を残して、それを駆使する作歌の作法を特に秘密性の高い口伝として定めた。本歌取りはこういう風にするものだ、序詞はこう使え、歌枕の配置を忘れるな、掛詞で和歌の文字鎖を完成させよ、こうした作法の数々は、記録の残らない口伝として為家(ためいえ)に伝えられたのであろう。教材を色紙型にして歌人名を除外するのは、和歌の価値は人ではなく和歌そのものだという定家の強烈な教えを表していると思う。そして定家の子孫は、歌道の勉強が進み、御子左家に秘蔵されている勅撰和歌集に親しみ、百人一首に掲載されている和歌の元来の表記を直接に見ると、その素材を添削して改変し、名歌に変貌させている先祖、定家の恐ろしいまでの才能を知ることになる。
私は、これが、「秘伝百人一首」を制作した定家の主旨であろうと考えている。この目的のためには、教材として使いやすければ、あえて駄作、凡作の和歌であっても採用するし、序詞、歌枕、掛詞などの文字遊戯の技法に適合するように元の和歌の表現に赤ペンを入れて改変して採用することも厭わない。歌人名に、その和歌の作者は詠み人知らずではないかなどの多少の疑問が残ろうとも、百人を揃えるためには虚偽表示が含まれてもよい。何しろこれは御子左家の家中にのみ伝わるべき秘伝であるから、添削、改変が外部から問題にされることもない。和歌史上の著名な歌人の作品に遠慮なく添削の赤ペンを入れて採録を進める定家の、我こそ史上最高の歌人であり、添削は非礼ではなく至極当然の教育的指導であるという自意識に圧倒される。もう一度料理屋の例に例えるが、歌集は秘伝の味のたれに使う百種類の素材の列挙であり、それの具体的な調合とたれ作りの秘訣は口伝なのである。
冷泉家に伝わる百人秀歌の後記には「上古以来哥仙之一首、随思出書出之。名誉之人秀逸之詠、皆漏之。用捨在心。自他不可有傍難歟。」とある。名歌撰ではないというだけで、それではどういう編纂の意図であるのかは説明されていない。ただ「名誉之人秀逸之詠、皆漏之。用捨在心」、名誉ある歌人、秀逸な和歌も皆洩らしたが、用いるも捨てるも私の心に在るままである、と語っているだけである。この一文は、これまで、多くの研究者によって定家が凡庸な和歌を選んだことへの弁明と理解されているが、これを糸口に、ここで隠された定家の編集意図に肉薄する研究にはつながっていない。定家の弁明はここまでで、百首が必要な積極的な理由は開陳されていない。採録に際して表記を曲げた理由も説明されていない。私が疑問に思ったのは、歴代の歌道の識者が、そのことを不審に思っていなかったのだろうか、そこに言及しないことである。この謎はだれが解くのだろうか。
こうして、定家は百人一首を考案した。自分より出来の悪い子孫でも歌壇のリーダーたりうるための基礎教育のテキストである。ところが、百人秀歌には後鳥羽院、順徳院の和歌が抜けている。そうすると、将来、子孫が歌道を学ぶ際に、この二人の上皇を除外していれば二人に関する知識に欠けることになり、定家と後鳥羽院の不仲を知る京都の狭い公家社会では、二人をいつまでも無視し続ける御子左家の者は心が狭いというそしりを受ける。これは問題である。それにそもそも定家には、後鳥羽院の悪霊のたたりを恐れる気持ちがある。公家社会に有って、早くから幕府のアーリー・フォロアーになり、京都の朝廷や公家社会の動向を幕府側の要人に報告し、承久の乱の勝敗を決する情報戦の一端を幕府側で担っていたとすれば、敗者の後鳥羽上皇からは裏切り者としてたっぷり恨まれているであろうから、乱の後始末に乗じて破格の出世を遂げている御子左家にその悪霊がたたるのはごく当たり前に予測されるところであり、それに震えた定家が、同家の秘儀においても後鳥羽院と順徳院を尊重して祭り上げ、もって悪霊のたたりが同家に及ばないように悪霊封じをしたのではなかろうか。だから、この二人の和歌を採録し、その代わりに二、三の者を削除して百人に整える。このように考えたのは定家本人であることはありうるが、あるいは後鳥羽院の定家への怨念までを継承させられて、累が御子左家の子々孫々に及ぶことを避けたかった息子の為家(ためいえ)の工作であったのかも知れない。
ここで気になるのは、「百人秀歌」では天皇には「御製」の二文字が付いているのに、百人一首ではそれがなくて呼び捨てであることである。同じ定家が「小倉山荘色紙和歌」でこのように変心するのであろうか。百人秀歌の歌人名の表記には厳密に規則性があり、天皇、上皇には「御製」を付けるほか、公家の中でも摂政、関白、太政大臣などでは本名を呼ぶことを遠慮し、四位の公家には本名に「朝臣」を付け、五位以下の公家は本名のみである。僧侶にしても、高位の者には「大僧正」などの敬称を添え、地下の僧は「法師」を付けている。こういう厳密な基準の中で天皇、上皇に付けられた「御製」を定家が簡単に消したとは思い難い。
私は、定家の後を継いだ為家(ためいえ)が、単独で編纂した『続後撰和歌集』に二名の上皇の和歌を採録して、次に、こうして勅撰和歌集に収録されている和歌という百人一首に歌を採用される資格を得させて、上皇の和歌を採録し、そうすると、百人の歌人中に朝廷を恨んで怨霊化した崇徳院と、幕府を恨んで怨霊化した後鳥羽院、順徳院という廃帝が含まれるので、彼らにも敬意を払って天皇、上皇にしか加えていない「御製」をつけてもよいが、それは幕府と幕府に屈してその顔色を窺っている承久の乱敗戦後の現皇室との関係で憚られるのであり、かといって誰に御製をつけて誰に付けないかとする線引きも難しいので、いっそ逆にすべての天皇、上皇から「御製」を削除してしまえということで百人一首本を作り、それが二條家に伝わり、百人一首では「御製」が消えたのだと思う。為家(ためいえ)本と言われる最古の百人一首歌集ではすでに天皇、上皇には「御製」はない。そうすると、百人一首に改編したのは為家(ためいえ)であるという考え方の方が有力になる。
定家の遺品と言えば、様々な歌集もあるが、日記に『明月記』があり、これも冷泉家に伝来している。冷泉家は、先祖の定家を神のごとくにあがめ、その遺品を神格の時雨亭文庫としてその保存、伝承を同家の最大の使命として今日に及んでいる。そのおかげで、今日の和歌史研究がどれほど貴重な史料を知ることができたか、その計り知れない学術上の価値は、平成年間に公刊された『冷泉家時雨亭叢書』の圧倒的な内容からも理解できる。これを可能にした冷泉家の長年の努力、その功績は筆舌に尽くしがたい。
こういう事情であるので、百人一首の完成形態、いわゆる為家(ためいえ)本は二條家に伝わり、その後、何らかの機会に冷泉家にも伝わり、時雨亭文庫中に保存されたと考えられるのである。
[1] なお、その後、時雨亭文庫では、もう一点、江戸時代の冷泉為村が書写した『百人秀歌』が発見され、それの元となった歌集につき、様々な推測がされている。大山和哉「冷泉為村が書写した『百人秀歌』の出現」『百人一首への招待』、平凡社、平成二十五年、一四〇頁。