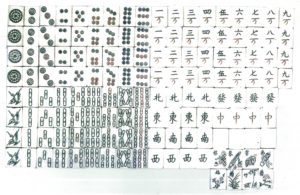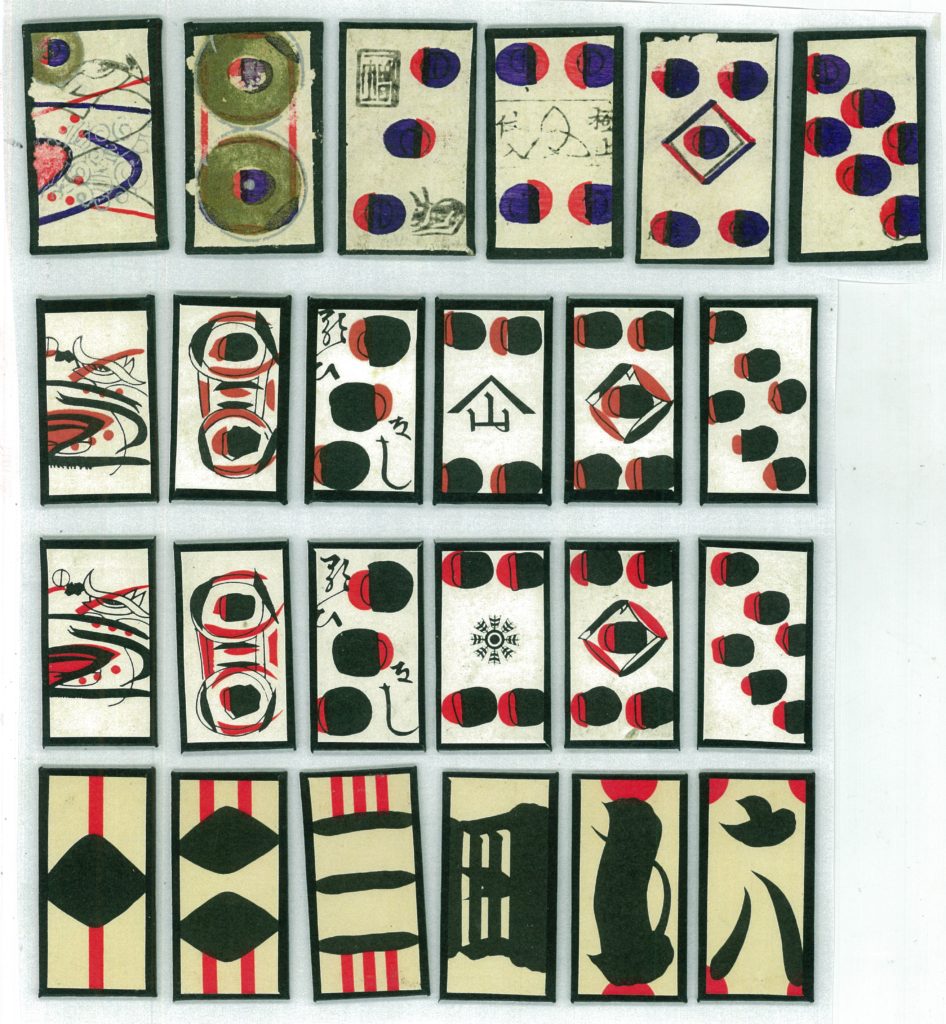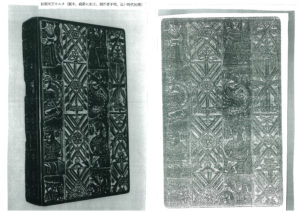江戸時代前期(1652~1704)に「読み」と人気を競っていたトリック・テイキング・ゲームの「合せ」カルタの遊技法は、江戸時代中期(1704~89)になると人気を失い、消滅していった。「合せ」と同種のトリック・テイキング・ゲームは世界各地にあり、ゲームとしては十分に興味深いものであるから、これがこの時期の日本の社会で嫌われた理由はよく分らない。ここで軽薄に日本文化論を展開してもしょうがないが、日本では、時に海外からの新文化の侵入によって社会が大きく変化するが、黒船の来襲に始まる幕末期の開国にしろ、第二次大戦敗戦の結果としてのアメリカ軍の占領にしろ、当初は敗北した自国の文化の立ち遅れへの失望と押し寄せた勝利者の「進歩的」な外国文化への無条件の憧憬、称賛が起き、熱心にそれに学び、それの模倣、導入が図られるが、二世代、約六十年を経過したころに、そうした物真似文化への反動も起き、日本らしい旧来の文化への復帰が生じる。カルタの場合も、伝来したポルトガルの遊技法は他の参加者と激しく戦い合い、手札として配布されたものを奪い合う激しさを持っており、当初は戦国の世の荒々しい気風にうまく合っていたが、それが、平和が回復して二世代、数十年ほど経過したあたりから、戦い合い、殺し合い、奪い合う激しい遊技法ではなく、互いに勤勉に作業をして、成果、収穫を競い合うことはあっても相手の財産をトリックとして根こそぎ奪い取ることはしない、日本的なフィッシング・ゲームの穏やかな遊技法に変わっていったように見える。いずれにせよこの江戸時代前期(1652~1704)に、海外から伝来したトリック・テイキング・ゲームは社会的には廃れた。同じ「合せ」カルタ系でもそれほど激しい戦い合いの遊技法ではなかったであろう上流階級のうんすんカルタなど、一部のグループの遊技法だけが残った。
この時期に関西地方に「天正(てんしょ)」というカルタの遊技法が登場した。これは「合せ」とも呼ばれているが、同名の、江戸時代前期(1652)のトリック・テイキング・ゲームとしての「合せ」に由来するというよりも、同じ江戸時代前期にトリック・テイキング・ゲームの「合せ」の遊技法と共存していた「絵合せかるた」系、特にマッチング・ゲームの「花合せ」かるたの「合せ」に由来すると考えた方が自然である。江戸時代前期には、何種類かの「合せ」かるたや「合せ」カルタの遊技法が共存していた。上記に加えて「歌合せ」かるたの遊技も登場していた。だからそこにもう一つの新種の「合せ」カルタの遊技法が現れても不思議ではない。
そして、後に「めくり」が流行した頃に「天正」と書いて「めくり」と振り仮名をした例[1]があるように、明和年間(1764~72)に江戸で「てんしょ(合せ)」の遊びから「めくり」の遊技法が考え出され、安永年間(1772~81)に大流行した。「てんしょ(合せ)」に使うカードを「てんしょ札」ないし「てんしょカルタ」という。明和年間(1764~72)に江戸で「めくり」が始まり、まもなくそれに適した「めくり札」がつくられたが、関西では依然として「てんしょ札」の方が主流であった。明和六年(1769)刊の大坂版の洒落本、史魯徳斎『間似合早粋』[2]にも「おなことざとうのすもふてんしよがはやるによつて半めくらじや(女子と座頭の相撲、天正が流行るによって半盲目じゃ)」とある。
関西の「てんしょ(合せ)」の遊技法は記録が少なくてよく分らない。ここで、同時代の記録として貝原益軒の『教訓世諦鑑』を重視する江戸カルタ研究室の理解がある。本書は、宝永八年(1711)刊のもので、その巻二、第三「博奕」(ばくえき)の記述の中に、「二と二とを、合せ、五と五とをあはせ、次第々々(しだいしだい)に、其かずに合せて、しやうぶをなすをば、あはせ哥留(かる)たと云ふ。」という文章がある。これは、宝永年間(1704~11)に、多分九州福岡と思われる地域に「合せ」というカルタ遊技があったことを示している。貝原はこれを「博奕」の一種として説明しているが、厳密にはトリック・テイキング・ゲームの「合せ」は軽罪の賭博遊技の一種に過ぎず、これを骰子博奕やオイチョカブ博奕のような「博奕」の一種として重罪に問うと書いたのは誤解であり、江戸時代の犯罪取り締まり記録である各地の『犯科帳』を見てもなかなか見当たらない表記である。すでに2-4で指摘したところで重複することになるが、多分、賭博犯罪における重罪と軽罪の区別がつかなかった貝原の勘違いの記述であろうと思われる。宝永年間(1704~11)と言えば、徳川吉宗政権による刑罰制度の抜本的な改革と御定書百個條による賭博犯罪の寛刑化の明示よりも以前の時期であるから、黒田藩の一藩士であった貝原が賭博関係の刑罰の軽重を理解できなかったことにも多少は斟酌する余地がないでもない。それにしても、ここでの説明は高齢の貝原の間接取材で、丁半博奕とオイチョカブ遊技の区別がついていないなど、説明が要を得ていない。紋標は異なるが紋標数が同じ二枚の札を合せる遊技法があったということ以上には説明力が足りない。私は、2-2で「合せかるた」の発祥を論じた際に、この江戸時代中期(1704~89)の文章を江戸時代前期(1652~1704)の『雍州府志』に言う遊技法の「合せ」を解明する文献史料として使用することに基本的に否定的であり、また、そのことを説明する際に、この文章が江戸時代中期(1704~89)の西日本での「プロトめくり」、フィッシング・ゲームとしての「合せ」の史料としても重きを置けない事情を述べておいた。繰り返しになるが、ここでもそれを指摘しておきたい。
貝原は、「合せ」では「二」と「二」、「五」と「五」を合わせて、「次第しだいに」勝負をすると書いている。「二」と「二」をどう合せるのか。先入観を持たないでこの文章を読めば多義過ぎて文意不明である。他の参加者が打った「二」の札に自分も「二」の札を合せるというのであればトリック・テイキング・ゲームである。しかし、貝原は手札を配分するとは記述していないので、「合せる」元になる札がどこにあるのかが分からない。手札の記述がないのだから、裏面を上にしている場札の「二」の札をもう一枚の場札の「二」の札に合せるトランプの「神経衰弱」のようなタイプの遊技法とも読める。そうだとすれば貝合せ(貝覆)の遊技法に似た直系の子孫である。あるいは、表面を上にして晒されている場札と、裏面を上にして場に積まれている山札を合せる遊技とも読める。裏面を上にしているカルタの札を表面に返す動作は当時も今も「捲(めく)る」と表現されるのであるからこの点では、この点に限っての話だが、「めくり」らしくなる。百人一首のかるた札を応用する「坊主めくり」に近い偶然性だけの稚拙な遊技法である。さらに、「二」の札と「二」の札を合わせたとして、その先がどうなるのかも書いてないから分からない。合せ捨てるのか、合せ取るのかが書いてない。合せ捨てることで手札が減り、早く打ち尽くしたものが勝ちとなるというのであれば、これは「読み」カルタの多少変形した遊技法である。合わせた札を自分の手元に釣り取るというのなら研究室が理解しているフィッシング・ゲームになるが、貝原の説明が「合わせる」で終わっていて「釣り取る」という動作の説明がないのでこの遊技法を説明しているとは確定することができない。
それに、「次第しだいにその数に合わせて勝負をなす」という言葉も理解が難しい。「次第しだいに」とは何の次第なのか分からない。合せる札の順番に「一」「二」「三」という「次第しだい」があるのか。札を打ち出す遊技者の順番なのか。「次第しだいに合せて勝負する」と書かれると、どうしても参加者が順番に札を出し合うトリック・テイキング・ゲームが思い浮かぶ。そうではなくてフィッシング・ゲームなのだとすれば、参加者は順番に手札を出して場札と合わせて釣り取るけれども、それは「取り番」でそうしているのであって、合せるその所作で「勝負をなす」のではない。「プロトめくり」のようなフィッシング・ゲームでは、「次第しだいに」数を合せるのではなく、「順に」ないし「番に」、つまり順番に数を合わせて行き、最後まで進んだら獲得した札の点数を数えるのである。
実は、この箇所で、貝原は「てんしょ(合せ)」という遊技の本質にかかわる不適切な説明をしている。「てんしょ(合せ)」は極めて日本的なカルタの遊技法である。元々、海外から伝来したカルタの遊技法には、勝負をして勝者が利益を独占するゼロ・サム・ゲームの色彩が強い。トリック・テイキング・ゲームで言えば、トリックごとに手札を出して他のメンバーと勝負して、何組のトリックを獲得するのかが勝負であり、一組でも多くのトリックを確保したものが賭金を独占する。これを譬えれば、すでに繰り返し説明してきたように、他者の領地に侵攻し、合戦に及び、武を競い合い、戦い合い、勝利して相手の領土、領民、富をすべて奪うが、敗れれば、逆に侵攻されて自己の領土、領民、富をすべて奪われる、戦国の世の武士の行為に近い。あるいは「読み」のような遊技法では、相手の札を奪い取るという所作はないけれども、早く手札を払い尽した者が勝ちで、いかに素晴らしい手役があっても手中に残って払い尽すことができなかったときは負けでゼロ評価になる。一人が出し尽くせばそこでゲームは終了で残りの参加者は全員が敗者で、ゼロと査定される。戦いの時機に遅れた者はそれまでがいかに善戦でも、まるで駄目でも、同じ敗者ということである。
ところが、「花合せ」かるたや「てんしょ(合せ)」カルタや後に述べるめくりカルタの遊技法では、釣り取った札の得点は常に有効で、また、釣り取った札の構成次第ででき上る「でき役」は、勝ち負けにかかわらず得点として評価される。勝負は参加者の中の誰かが上がったらその瞬間に終わるのではなく、最後の一枚まで使い尽し、その後各人の獲得した札の点数と役の点数を合算したものを比べあい、差額を敗者が提出するということになる。時には三人の参加者の内で二人が基準点を超えて札を獲得していて、もう一人が大敗していることもある。この場合は、勝者が二人いて、敗者が一人である。勝者が一人というトリック・テイキング・ゲームの「合せ」カルタとは原理が違う。
これはたとえて言えば、同じように田植えして育てた稲につき、その後の手入れの巧拙で収穫量に多寡が出るようなものであり、一人の農民の栽培技術が優れていて収穫量が多くて残りの二人の収穫量が少ないこともあるし、逆に一人の農民の栽培が下手で、他の二人の収穫量は多かったのにその者だけ収穫量が少ない場合もある。これは基本的に労働の成果を競うタイプの所作であって「生死を賭けて戦う」「勝負をなす」「勝者がすべてを取る」という伝来したカルタ遊技の勇ましい所作ではない。この穏やかさが日本式かるたの遊技法の肝なのであり、その系統にある花合せかるた、てんしょ(合せ)カルタ、めくりカルタにはそれが共通して見て取れる。貝原はそこの文化的な違いが理解できないままに伝聞のままに「次第しだいに‥‥勝負をなす」と書いている。
こういう次第なので、私には、すでに2-2で述べたようにこの江戸時代中期(1704~89)の文献を江戸時代前期(1652~1704)に「プロトめくり」遊技が存在していた論拠とすることに否定的であるだけでなく、同時代の「てんしょ(合せ)」の遊技に関する文献史料としても高くは評価できない。
[1] 隋羅斎「当世繁栄通宝」『洒落本大成』第十一巻、中央公論社、昭和五十六年、五八頁。
[2] 史魯徳斎「間似合早粋」『洒落本大成』第四巻、中央公論社、昭和五十四年、二七三頁。