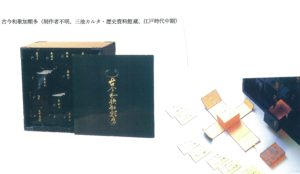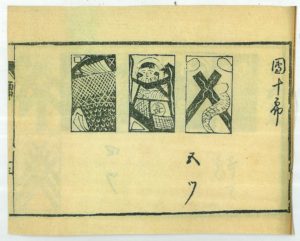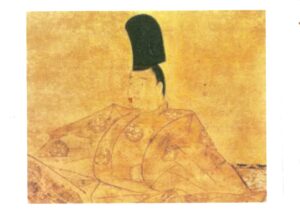「百人一首歌合せかるた」には、ゲームの比較研究の上では見逃せないもうひとつの大きな特徴がある。このかるたの遊びでは、江戸時代前期、元禄年間(1688~1704)頃から、音声が使われたのである。今日、日本人はこのことを全く当たり前のように受け止めているが、世界のカードゲーム史のなかではごく稀なできごとである。
日本の口承文芸を語るには、『万葉集』から始めなければならない。万葉集学の大家である中西進は、この歌集が始めは少数の和歌の集まりであったが徐々に膨れ上がって五千に近い大歌集になったものであり、その中心には、一番最初から含まれている約三〇首の「原万葉」があるといっている[1]。伊藤博は、万葉集の原型は「持統万葉」五三首であるという[2]。安引宏も、約三〇首の「原万葉」の和歌を析出する試みに挑戦し、それが、天武天皇の王朝によって実現した日本をたたえる、いわば日本賛歌を内容とする壮大な歌劇であったことを突き止めた[3]。
これらの研究者に共通しているのが、「原万葉」は、口承文芸として成立したという認識である。つまり、日本の和歌は、先ずは朝廷で朗唱されるものとして成立し、後に、それを記録するために、万葉仮名が用いられたのであった。従来は、万葉仮名は万葉集の記録のために開発されたと考えられてきたが、最近は、紀元三世紀ころ、卑弥呼の時代の日本と中国の交流の中で中国側に記録された日本の王名、地名、官職名、人名などを万葉仮名の読みで解読するとすっきりと理解できるとする研究もあり、そうだとすると万葉仮名の発祥は万葉集の成立よりずっと早期になり、万葉仮名という呼称も不適切であることになる。石川九楊は、文字表記を、紀元前三世紀の徐福伝説の時期に始まるものと推測し、遅くも西暦紀元ころには、日本の九州地方に成立した政権であろうか、そこから中国の宮廷に忠誠を誓う正確な漢文の文書が提出され、見返りに金印が下賜され、その後は日本側から発出される文書にその金印が捺され、中国側に残る印影と照合することで文書の真実性が確保されるというシステムが成立していたとする[4]。基本的に正しい歴史認識である。そこに成立した「音仮名」は、地名や人名など、中国語では表記できない日本発祥の固有名詞を表示するものであり、それが万葉集の頃までには固有名詞の範囲を超えて普通の言葉も万葉仮名で表記するようになった。いずれにせよ、和歌は口承文芸として成立して、万葉仮名で記録されたのである。
このことを記念して、かつて万葉歌人の大伴家持が国司として滞在したことのある富山県高岡市では、毎年一〇月の初めに「万葉集朗唱の会」[5]を開催し、歌集に含まれるすべての和歌を順番に読み上げる。市民二千人が参加し、三日三晩ぶっ通しで行われる一大イベントである。高岡古城の堀の上に設置された舞台に立って、万葉の衣装もまとって読み上げる人々を見、その和歌を聞いていると、日ごろ文字から接しているのとは違った万葉歌謡の印象が得られる。私もこれに参加したことがあるが、自分の順番が来て朗唱すると、気持ちが大いに高ぶり、歌人のイメージが一新される。日本は言霊の国で、今この瞬間にその言霊に接しているとの思いを色濃くするのである。
日本文学史の錦仁[6]によると、古代から、日本という国は、風景が和歌に読み込まれる範囲として成立していた。歌人がその地を訪れて、歌枕をあらわす。常識的には、上の句は風景を詠み、下の句で、それに心象風景を絡ませていくことになる。それができて、それがふさわしいところが日本なのである。それができなければ、同じ日本列島上の場所であっても、化外の地となる。日本という観念が先ずあって和歌ができたのではなく、先ず言葉ありきで、和歌によって、無限に続く列島の自然の中の一片が日本になる、というのである。こういうと、「小倉百人一首」には、中国で詠んだ安倍仲麿の歌があるではないか、といわれそうであるが、仲麿の歌は、ふるさとである大和の三笠山に出た月を偲んだものである。
だから、和歌とは日本文化そのものであるといえる。「原万葉」の歌は、聖徳太子の治世、大化の改新、壬申の乱を経て成立した、日本という独立した文化、独立した政治の誕生を祝い、それをもたらした天武天皇の王朝、持統天皇の王朝をたたえる奉祝歌謡であった。その演出家は、言うまでもなく、持統王朝の最高顧問であった柿本人麻呂である。
今日でも、宮中では、歌会始が毎年行われている。新年に行う歌会は、藤原定家の『明月記』所載の事例が最も古く、また、毎年行うという形式は明治年間(1868~1912)になってからであるが、朗唱する歌会という形は古くから連綿として継承されてきたものであり、口承文芸として和歌を詠みあげる始原の姿を今日まで伝えているものと考えることができよう。「百人一首歌合せかるた」が読み手が読み上げて取り合うという構造に進化した背景には、こうした口承文芸としての和歌という文化的な伝統があったのだと考えられる。
[1] 中西進「原万葉―巻一の追補」『万葉研究誌 美夫君志』第七号、美夫君志会、昭和三十九年、八〇頁。『中西進万葉集論』第六巻、講談社、平成七年、四四頁。なお、伊藤博『萬葉集の構造と成立上』第二章第一節五「仮説の認定」、塙書房、昭和四十九年、七一頁。
[2] 伊藤博「原『万葉集』の成立」、『日本古典文学大辞典』第五巻、岩波書店、昭和五十九年、五五四頁。
[3] 安引宏『原万葉 葬られた古代史』、人文書院、平成十四年、三頁。
[4] 石川九楊『二重言語国家・日本』日本放送出版協会、平成十一年、中公文庫、平成二十三年、一三九頁。同『ひらがなの美学』新潮社、平成十九年、八頁。
[5] 万葉集朗唱の会二〇〇三年度プログラム。
[6] 石井正己、錦仁編『文学研究の窓をあける―物語・説話・軍記・和歌』、笠間書院、平成三十年。