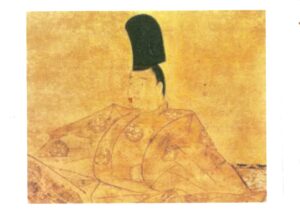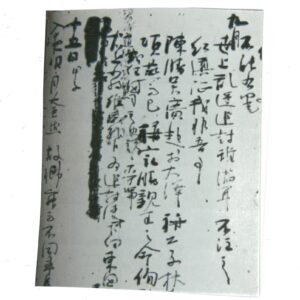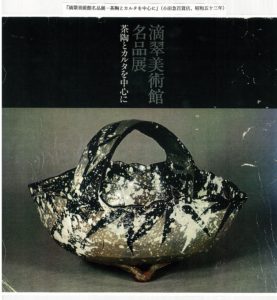ところが、ここで定家の計算違いの事態が出現した。軽率な息子為家は、この一子相伝、師資相承の秘儀が存在する事実を、妻の父、舅(しうと)である宇都宮頼綱に漏らしてしまった。あるいは、「伝授」の席での父定家の厳しい指導への愚痴をこぼしたのかもしれない。ここで頼綱が何を考えたのかは記録では明らかでないが、大いに驚いたであろうことは想像がつく。私は、ここに、なにがしか、頼綱の定家への不信が芽生えたのではないかと邪推している。定家は、承久の変に際しては親幕府派の公家の先頭に立ち、幕府側に協力的であり、朝廷方の情報も頼綱などに提供し、それゆえに敗退した後鳥羽上皇側からは公家社会への裏切り者と考えられていたであろう。その定家だが、それでも消えない後鳥羽院への思慕の念をこの一子相伝の「歌群」に残しているのではないかという疑念は消されない。定家と後鳥羽天皇(上皇)の関係はそれほど深い。そしてそれは、いずれ定家による後鳥羽院の復帰への動き、鎌倉方への裏切りに繋がる。そこで鎌倉幕府に忠実な武将であった頼綱は、定家に進行している事態を把握するために、その「歌群」の提示を迫ったのではなかろうか。

もちろん、それはぶしつけな審問ではなく、歌学の師に開示を願う後学の徒としての礼を尽くしての依頼であろう。そこには、「後鳥羽上皇様は誠においたわしくあらせられます。あなた様も後鳥羽上皇様へのお気持ちはおありでしょうから無理にとはお願い申しませぬが、」とやや婉曲(えんきょく)に定家の気持ちを問いただす意味合いもあったであろう。そして、それに応えて定家が頼綱に送ったのが、色紙にしたためたこの約百首の「歌群」の和歌であったのであるが、私には、嫌疑を避けるために頼綱への開示を求められるという微妙な立場に追い込まれた定家の、軽率な息子の行動に対する舌打ちの音が聞こえるような気がする。なお、田淵句美子は、従来の研究の基礎に立って、『百人一首』と宇都宮頼綱との関係について詳細に研究している¹⁸。その研究は極めて慎重で、従来の研究が安易に利用してきたような情報は排除され、着実な史料に基づく立論があり、大いに参考になる。だが、私には、それでも依然として、百人一首の原型は定家が後継者の為家の教育のために用意した先例集の教材であり、それを頼綱に提出させられたのは本来の作成目的とは異なる事態の出現であったとする私の理解を改めるには至らなかった。
定家は、後鳥羽院の愛顧によって引き立てられてきた。一方で、鎌倉の源実朝を弟子に迎えて交際を尽くすなど、親鎌倉幕府の公家でもあった。したがって、後鳥羽院の怒りを買って勅勘を受けた際にも、また朝廷と幕府が激突した承久の乱の際にも、双方から動向を疑われ、対応を一つ間違えれば御子左家は取り潰され、廃絶に追い込まれる存亡の危機にあった。定家は、そこで、親鎌倉幕府派であった主家の九條家に寄り添って、ためらわずに鎌倉方についた。こうして、御子左家の長としての処世には長けていた定家であったから、息子の為家の無警戒な、頼りなげな行動には怒りもあれば将来の不安もあったことであろう。
そして、定家から頼綱に贈られた「歌群」の色紙には、頼綱が疑ったであろう、承久の乱の責で遠島の流刑に処せられた、後鳥羽院や順徳院の和歌は含まれず、後鳥羽院の宮廷の歌人、女性歌人の和歌さえもが排除されていた。当時の女性歌人の中では、とり分け「俊成卿女(しゅんぜいきょうのむすめ)」と「宮内卿(くないきょう)」が後鳥羽院のお気に入りであり、『新古今和歌集』¹⁹でも華々しい活躍を見せており、さらに『院句題五十首』では六人の詠者のうちの二人が「俊成卿女」と「宮内卿」であったし、『千五百番歌合』でも大活躍してしばしば定家と番えられて定家を負かせているし、俊成九十の賀で「屏風歌」を作成する際にも十人の詠者に含まれているし、鎌倉将軍実朝を調伏するために建てたと言われる「最勝四天王院」の屏風絵和歌の詠者十人中にも「俊成卿女」が含まれている。彼女たちは、後鳥羽院とかくも近しい関係であったために、当時の歌壇で最も高名な二大ヒロインであり、それゆえに後鳥羽院、順徳院とともに歌人として抹殺されたのである。定家は後鳥羽院や順徳院を除外しただけでなく、後鳥羽院歌壇の歌人をも追放しているのであって、歌集としては異様な歪みを生んでいる。この「歌集としては異様過ぎる」という感覚が私の脳裏から消えることはない。
そして、ここまで徹底することで、自分には後鳥羽院への思慕はもはや存在しないというのが定家の弁明である。この変節をもって定家の人格をうんぬんすることは容易だが、風にそよぐ芦の葉のような中級公家、御子左家の主としては当然の、生き残りの知恵を絞った姿勢であろう。だから定家をあれこれ言うのは酷である。ただ残念なのは、この粛正によってこの時期に最も活躍した、天才少女の「宮内卿」や代表的な女性歌人であった「俊成卿女」が忘れさられたことである。現代の社会では、百人一首を飾る女性歌人たちの名前と和歌は知っていても、この二人の残したあまたの名歌を知る人はいないし、かたや『新古今和歌集』の歌人の中ではもっとも遅くまで生きた一人、かたや生没年も不詳の夭折の歌人であるがその人生も伝わらず、その名前さえ知られていない。「歌集を思いきり読んだあとは、書物を閉じ、一人沈思して、表現の熟成と沸騰を待った」俊成卿女と、「最初から最後まで歌集などを見ながら、ことばを拾い上げ書き付けては夜も昼も考え続け命を縮めた」宮内卿であり、「最初は権門の妻であったが、女房に転身して長い歌人人生を全うしたプロフェッショナルな女房歌人」俊成卿女と、「歌の多くは、突き詰めた思考の果てに、知的な趣向と独創性を求めて表現されている。その言葉は過剰なほどの密度で理知的に構成され、抒情性に乏しい面も見られる」宮内卿²⁰、塚本邦雄がいうように、『百人一首』の百人にこの二人の才媛が「漏れているのは寂しくかつ由由しい」²¹のである。
「宮内卿」は若くして消えたが、「俊成卿女」は長生きし、『新古今和歌集』世代ではもっとも長寿の一人であったので一言添えておこう。かつて森本元子は、「俊成卿女」の伝記的研究で、承久の乱以降の彼女を支えたのは定家であったと指摘している²²。定家が手配して彼女が諸方の歌会に参加していることなどが根拠である。また、後年、定家が勅撰集の撰進を託されると、「俊成卿女」は選歌の資料となるよう『俊成卿女集』を自撰した。しかし、『新勅撰和歌集』には、「俊成卿女」の和歌は「侍従具定母」という妙な名乗りで八首のみが採用され、他の歌人、藤原家隆(四十三首)、藤原良経(三十六首)、藤原俊成(三十五首)、源実朝(二十五首)、 相模(十八首)、殷富門院大輔(十五首)・藤原定家(十五首)、式子内親王(十四首)、二條院讃岐(十三首)などの歌人、とくに同世代の女性歌人と比べれば格落ちの冷遇である。なお、宮内卿は二首にとどまった。
そして、これを最後に、その消息は聞こえなくなる。『俊成卿女集』は、『新古今和歌集』の歌風と後鳥羽院歌壇への追慕を緩めることなく溢れさせていたのであるから、後鳥羽院歌壇の栄光に背を向けた定家らにとっては古傷を思い起こさせる「持て余しもの」であったのではなかろうか。実際、俊成卿女は、『新勅撰和歌集』について、定家編でなければ手に取る気もしないと酷評し、自分に対する冷遇については一言も文句を言わずに、後鳥羽、順徳、土御門の三上皇の無視を厳しく咎めている。そこには後鳥羽院歌壇の華であった歌人としての誇りは捨てられていない。歌人としての筋は通っている。一方定家は、後鳥羽院歌壇の歌人の排斥が中級公家の行う生き残りの政治的な打算であることは明らかなのに、『新古今和歌集は行き過ぎていた』と、新古今調の和歌は質が低いので落としたものであると言い訳している。あるいはまた、『新勅撰和歌集』で定家が選考して後堀河天皇の内覧に供した稿本には後鳥羽院の和歌は多数採録してあったのに、後の九條家関係の改訂で削除されたのだという風説も伝えられているが、これにも首をひねりたくなる。私には、承久の乱以降の時期に定家が失意の俊成卿女を支えて励ましたとは思えない。収録された「俊成卿女」と「宮内卿」の和歌も、元来の撰者の定家が入れたのか、定家が放り出した後を継いで採録和歌を改編して歌集を完成させた者が、その改訂作業の際に、定家による二人の無視を憐れんで加えたのかは分かっていない。ここでは、同時代人で二人をよく理解していた鴨長明が書き残したように、女房歌人として、命を削って精進し、「日常生活や女房生活の余技として詠歌するのではなく、和歌に純粋な情熱を傾け、詠歌の修練を重ね……後鳥羽院の励ましに身を賭けて、力のすべてを和歌に注ぎ込んで表現世界と対峙し、歌壇の歌人たちと競い合っていった」²³「俊成卿女」と「宮内卿」を無視し、政治的思惑から黙殺しながら「紅旗征戎非吾事」と嘯く定家の歌人としての誇りの綻びと老残を哀れと思うのみである。
他方で、以前に流刑の地、讃岐で憤死した「讃岐院(後の崇徳院)」の和歌は含まれていた。「陽成院」、「河原左大臣」、「光孝天皇」のグループも入っていた。そして「歌群」は何者かによって『百人一首』と題された。これはすなわち、もし、『時代不同歌合』にならって日本和歌史の百人の名手を集め、百首の名歌を集めるのであれば、この通り、「崇徳院」や「陽成院」は大いに問題のある帝であったけれども許容の範囲内であるが、「後鳥羽院」とその一味はその限界を超えて堕落したのでこの一味は抜きで百人は埋まっているのであって、もはやこの者らの占める席はどこにもないのだという、「後鳥羽院」とその一味の歌道史からの永久追放を意味している。
これは異常な状態である。定家は、承久の乱のさなか、取り組んでいた『後撰和歌集』の書写の奥書に「紅旗征戒非吾事(こうきせいじゅうわがことにあらず)」と書いた。定家は、自分は歌人であって、政治家でも武士でもないのだから、戦さは自分には関りがないとしているのである。この言葉はこの個所の記述により有名になり、定家が『明月記』を書き始めた時期の、源平争乱が激化した治承四(一一八〇)年の記事の中に、「九月、世上乱逆追討雖満耳、不注之、紅旗征戎非吾事」とあるところから、すでに十九歳で定家は、政治、軍事から距離を置いて和歌の道に生きる決意を持った証しとされ、六十歳で迎えた承久の乱に際してもこの心であったと理解されていたが、辻彦三郎は詳細な研究の末に、『明月記』の治承四年の個所は、後世、寛喜二(一二三〇)年、七十歳前後の定家自身による追記であるとした²⁴。定家は、立身を熱望する中級公家である自分の右往左往ぶりを『明月記』の全巻に書き散らしており、政治情勢にも敏感に反応していたのであって、政治の世界から超然として「紅旗征戒非吾事」が生涯に及ぶ芸術家たる定家のモットーであったと解するのは贔屓目(ひいきめ)が過ぎるのである。
思うにこれは定家の遁辞、言い訳、負け惜しみである。この時期の定家は、親鎌倉幕府の公家であるので、後鳥羽上皇方の北條義時討伐の謀議には、幕府に密告する恐れがあるので加えてもらえなかったのではなかろうか。それなのに、鎌倉幕府側からは、謀議を知っていたのに黙っていたと疑われ、立場の置き所に困っていたのではないだろうか。もし、本当に政治から超然とした歌人の立場に徹するのであれば、定家としては、「後鳥羽院」は政治的、軍事的には落第生であったかもしれないが、歌人としては優等生であると言わねばならないところである。そうせずに「後鳥羽院」を歌人として全否定して、その作品も完全追放にしているのは、定家なりの政治的な判断であり、「吾が事に非ず」という言葉には大きな違和感がある。
このように、私は、定家による「歌群」の作成には公家社会での生き残りをかけた腐心を感じるのであるが、とりあえず百一首の和歌を集めた「歌群」であれば、先行き、政治情勢が変われば後鳥羽院一派の和歌を追加して増補する余地がないではない。実際に、この「歌群」は、鎌倉時代末期から南北朝期にかけて、鎌倉幕府追討になり、後醍醐天皇を中心に皇室の権威が高まる中で、そういう時代、社会の空気の変化を反映したように、追放されていた後鳥羽院と順徳院の和歌を復活させて加えた歌集の姿になっていったのである。ただし、それをしたのは定家本人ではなく、定家が残した歌道の資産を活用できた後継者の家系の者であろうけど。
百首と言う定員の固定枠を設けて、それを「後鳥羽院」の一味抜きの歌人で埋め尽くすことによって、この「歌集」の編者は、定家が、私は、決して「後鳥羽院」とその一味の和歌を認めているのにそのことを伏せてあなた様に色紙をお贈りしているのではございませんという弁明をしている形を作った。その意味では百人と言う枠は絶対のものであるのであり、「後鳥羽院」派の一味を除外した百人の枠を堅持することが武士による新政権、鎌倉幕府への政治的な忠誠を示している。
ただし私は、定家自身がここまで明け透けに後鳥羽院一派の追放、新幕府朝廷への服従を表現したとは見ていない。「百人」の枠を固定して、後鳥羽院歌壇の歌人の永久追放を確立したのは、後世の者であろう。この辺は、定家は、中級公家らしく政治的な「大人の対応」をしており、宇都宮頼綱もまた、事情を推察の上で「大人の対応」をしていると思われる。なお、ここで念のために記しておきたいが、頼綱は、寛喜(一二二九)元年に本宅にお堂を作り、その障子絵のために定家と家隆が五首ずつの歌を贈った。『明月記』にはこうある「関東入道(頼綱)、本居に於いて作る所の堂(本居の所作堂?こう解するとお堂は新築とは限らない)の障子に大和(国)の名所を描き、予・前宮内卿(家隆)に歌を詠ましめ、色紙の形を押すべき由、宰相(為家)に誂ふ。仍つて今朝腰折れ五首を書き送る。(葛木山・春、久米磐橋・春、多武峰・春、布瑠社・夏、初瀬山・夏。)前宮内卿、(吉野山・春、二上山・夏、三輪山・夏、龍田山・秋、春日山・秋、)秀歌多し。恥づべし。行能朝臣(世尊寺行能)書くべしと」²⁵。つまり、定家と頼綱の間では、百人一首歌の色紙のやり取りよりも六年以前に、すでに和歌色紙の贈呈の先例があったのである。頼綱も、自宅の設(しつら)えに天下の歌人、定家と家隆に和歌をねだり、これまた天下の能筆家、世尊寺行能に書を求めるとは、結構な有力者ぶりであるが、六年後に再度和歌色紙を求めるとは無遠慮過ぎており、懐石料理を振舞われた茶席で亭主に「おかわり」を求める客のようで、純粋に歌人同士の交際としてはいささか諄(くど)過ぎる印象が残る。宇都宮歌壇を主催したほどの歌人、宇都宮頼綱がここまでしたとは思いにくく、ここにはむしろ定家の内心を確かめようとする政治的な駆け引きの臭いがする。なお、文芸史家の辻彦三郎は、この間の経緯を、六年前の依頼が定家に礼を失していたので、それを執拗に恨んで根に持っていた定家に詫びる趣旨で、全編の揮毫を定家一人に託したものと解している²⁶。私の考えとは異なるが碩学の言であり、留意したい。
²⁰ 田淵句美子「『百人一首』の成立をめぐって――宇都宮氏への贈与という視点から」『中世宇都宮氏一族の展開と信仰・文芸』戎光祥中世史論集第九巻、戎光祥出版、令和二年、二五五頁。
²¹ 塚本邦雄「Ⅲ新古今時代の惑星」『新古今の惑星群』、講談社文芸文庫、講談社、令和二年、一五六頁。
²² 田渕句美子『新古今和歌集 後鳥羽院と定家の時代』、角川選書四八一、角川学芸出版、平成二十二年、五一頁。
²³ 塚本邦雄『王朝百首』、一七頁。
²⁴ 森本元子『俊成卿女の研究』、桜楓社、昭和五十一年、二四頁。
²⁵ 田渕句美子『異端の皇女と女房歌人』、角川選書五三六、KADOKAWA、平成二十六年、一三九頁。
²⁶ 辻彦三郎『藤原定家明月記の研究』吉川弘文館、昭和五十二年、九四頁。
²⁷ 高野公彦『明月記を読む 定家の歌とともに 下』、一九八頁、江橋補筆。
²⁸ 辻彦三郎『藤原定家名月記の研究』、吉川弘文館、昭和五十二年、八頁。