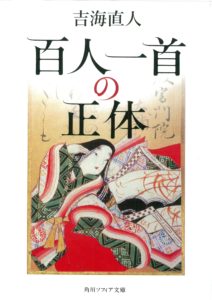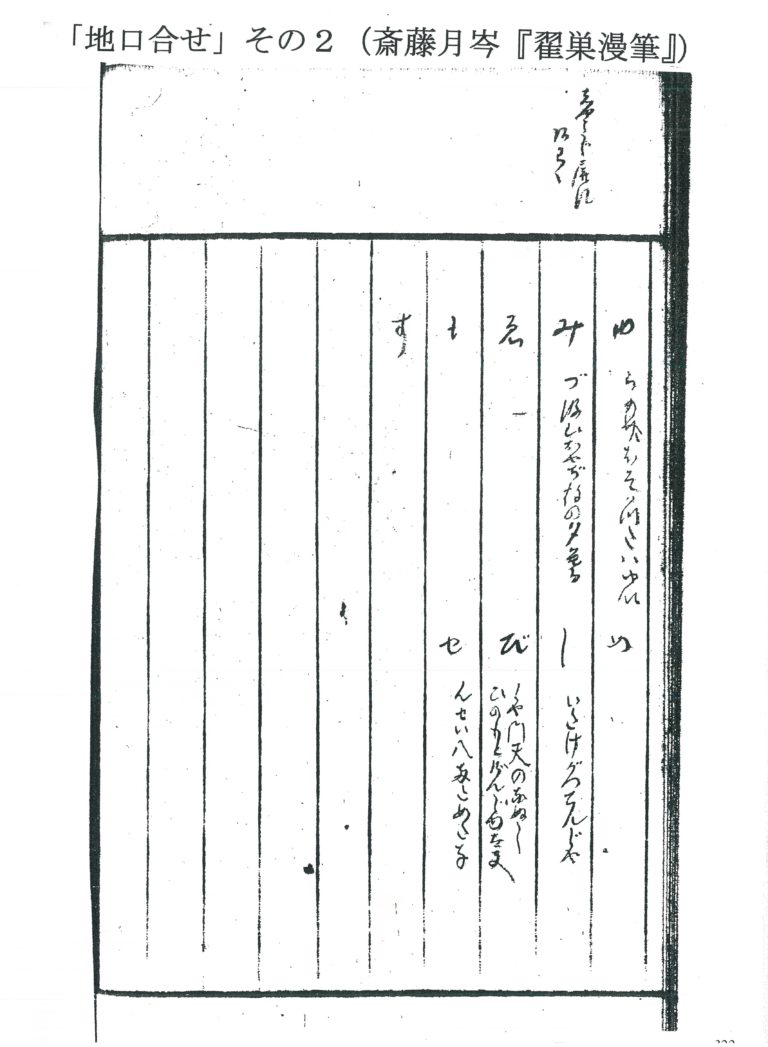花合せかるたは、花の種類が百種で四百枚構成のもの、五十三種で二百十二枚構成のもの、二十五種で百枚構成のもの、十二種で四十八枚構成のものなどが存在していた。『宴遊日記』で柳沢信鴻の家臣儀助が土産としたものがどのタイプのものであったのかは書き残されていない。花の種類が紋標となり、「桜」なり「菊」なりで、一つの紋標に四枚ある札の中で二枚を合わせ取るフィッシング・ゲームが用いられたのであろうと思われるが、江戸時代の遊技法についてはほとんど史料が残っていないので分からない。
木版の「武蔵野」の遊技法も記録が残っていない。ただ、上に紹介した永沼小一郎が『風俗画報』誌上で発表した「古今室内遊戯餘談」がわずかに伝えている。ゲームの勝ち負けは、合せ取って手中に確保したカードを「古實、古歌」などの意を取ってさまざまに組み合せ、その組み合せの多くできた者が勝ちである。そのために、描き出した花鳥草木の選定もできるかぎりこの趣向に叶うように大いに心してある。。そして、そこには、今日の花合せかるた、つまり花札遊技の代表的な「でき役」である「四光」「五光」「赤短」「青短」「七短」「猪鹿蝶」などの「役」に近いものがすでに生じている。しかもそれは、「四光」が図像に日、月、雷光、星と実際に光る天文現象を指していて後の時代のように「桜に幕」が含まれていないこと、この「桜に幕」を「四光」に加えた主牌五種の組は「五光」ではなく「五王」であること、「青短」は「紫短」であること、「赤短」の役は未成立で、十枚の「短冊札」の内で「紫短」の三枚をのぞいた残りの七枚の赤色の短冊札をすべて集めた「七夕」の役であること、「猪鹿蝶」も未成立で、「猪鹿雁」で「野荒し」の役であることなど、微妙に食い違っている点もある。
永沼は、以上を「其創始者の示し置足りと云ふヲ聞くに」として紹介している。ここに示した「役」の一つに七枚の赤色の短冊札を集めた「七夕」がある。花合せかるたの短冊札は、江戸時代中期(1704~89)の手描き札の時期には紫色か白色の短冊を描くものであった。それが紫色の短冊三枚以外はすべて赤色に揃えられたのは木版の「武蔵野」によってである3-3㉒。もともと手描きの花合せかるたの札では、短冊だけでなく、梅では紅梅と白梅、藤では紫藤と白藤、牡丹では紅牡丹と白牡丹、萩では紅萩と白萩、菊花では紅菊と白菊などに花の色が描き分けられていた。それが、木版のものにする際に、白色の彩色の手間を省いて表紙(おもてがみ)の地色のままにするといかにも手を抜いた印象になるので、梅、牡丹、萩では白色の部分を赤色に変えて、紅梅、紅牡丹、紅萩にした。藤では紫色にまとめて紫藤にした。菊では、他の紋標でも使う黄色も使われ、赤黄色の菊花となった3-3㉓。そして、白色の短冊も赤色に彩色されるようになった。牡丹だけは紫短冊だったのでそのままである。永沼小一郎が示した役の一つに「三紅」がある。梅、牡丹、萩の主牌三枚を揃えたときの役である。これらの札の花が赤色になったことが印象深く手この役ができたのであろう。
このような「七夕」や「三紅」などは木版武蔵野になった後でないと考え付かない役である。したがって、赤短冊の札が七枚と言っている「創始者」は、江戸時代前期(1652~1704)の手描きの花合せかるたの創始者ではなく、江戸時代中期(1704~89)の木版花札、「武蔵野」の創始者、松葉屋(井上)家春かそれに近い筋の者ということになる。
ただ、いずれにせよ、この遊技は獲得したカードの組み合せによるいとも優雅な文芸の遊技であるという基本は見えたように思う。つまり、花札固有の遊技法では「役」に最大の関心があったのである。これに、補助的に札の点数を計算に入れたのか否かは永沼の紹介からでは分からない。なお、滴翠美術館蔵品の「武蔵野」では、生き物札に「三十」、短冊札に「二十」という数字が後に墨書されている。「武蔵野」考案当時には点数が付かず、後にそれのある遊技法が流行して書き加えられたものであろう。点数は幕末期、明治前期(1854~1887)に付くようになったのであろうと思われるが確証はない。
幕末期、明治前期(1854~87)の花札の遊技法も良く分らない。ただ、花札は全国的な大流行になり、各地にその需要にこたえる現地のカルタ屋ができてその地方に独特の地方花札を制作するようになった。今日、記録があり、実際に地方花札として実物が確認できているものは、北から、 北海道花、山形花(東北花)、花巻花(南部花)、越後花、越後小花、関東花、横浜花、虫花、備前花、阿波花(金時花) である。明治年間に日本が海外に新領土を獲得し、開発が進むと、その地域の軍人、兵士、軍属、傭員、進出企業社員、歓楽街関係者、さらには現地住民の間に花札が食い込み、 大連花、朝鮮花 などの地方札も開発された。こうした地方花札については後に詳細に扱うが、「東京花」については一言注記を入れておきたい。明治中期の文献にこの言葉があるが、それは東京で独自のデザインの花札が制作されたということではなく、「横浜花」の遊技法から派生した「東京花」という得点の数え方に違いのある遊技法があったという意味である。東京でも安価な花札を制作したが、それは標準的な八八花札の廉価版ということであって、独自の地方的な図像のものではない。私は、これとの混同を避けて、関東地方の地方札を「関東花」と呼んでいる。
地方札を用いた各地の花札の遊技法が同じであったとは思えない。むしろ各地に固有の遊技法があり、固有の役があり、固有の得点計算法があり、そして、簡易な遊技法から複雑なものまでバリエイションがあったと思われるが、記録がほとんど残っていないので、分からない。遊技における札の点数もさまざまであったと思われる。実際、鳥取県や熊本県では、平成期になっても短冊札が十点、生き物札が五点という決まりの場所がある。そして、この中で、横浜花が明治二十年代以降に全国に普及し、八八花として広まった。だが、八八花の遊技法は複雑であり、一般家庭の娯楽では、もっと簡便な遊技法が使われていた。それらは昭和後期まで残存していて、花札の入門書、解説書を飾っている。