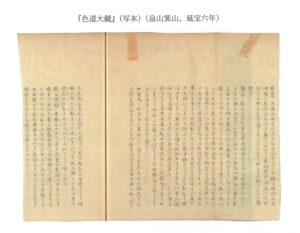その後「歌合せかるた」の遊技法は、「上の句」のカードを場に出すのではなく読み手が独特の装飾音声が加わった「吟誦」[1]、つまり音節の引き延ばしと言葉の節回しを込めた発声で読み上げて「下の句」のカードを探すものに変形されていた。そして、このように変化してみると、以前の沈黙の遊技法よりも遊技の座が賑やかで華々しくなり、この遊技に新しい魅力が生まれた。また、遊技のスピードが上がりスリリングになることも絵合せかるたの場合と同様である。ただ、こうした遊技法が成立するには、かるたに採録された和歌が参加者の間で理解されていなければならない。昭和十三年(1938)に三田村鳶魚は、林若樹が所蔵する貞享三年(1686)刊の『名所和哥百人一首』という書物に、「諸国名所和哥百人一首」「都近辺名所和歌百人一首」「女性百人一首」の三冊を懐中本で出版するとともにかるたに仕立てたが、「歌忘れ」に備えて十種の草木の花絵をかるたの裏面に描き、「上の句」札と「下の句」札が一対になることを示す「目付画」としたと説明されていることを紹介している[2]。十種の花絵は「まつむめやさくら山吹藤あやめきゝやうしらきく紅葉すいせん」である。三田村はこのことから歌合せかるたの成立は貞享年間(1684~88)からあまり遡らないと判断していたようである。
元禄五年(1692)刊の雑俳集『千代見艸』[3]には「吟じとる骨牌は和歌の相撲にて」とあり、正徳四年(1714)初演の文楽の演目で近松門左衛門作の『娥歌かるた』[4]には中宮御所で「歌かるた」が遊ばれる場面がある。そこでは中宮が、いつもと同じでは面白くない。今日は私が入らないで上の句札を出すから下の句札をお取りなさい。さあ読みますよ、と読み手になる。この時期に読み手が吟誦して取り合う遊技法が成立していたことになる。
遊技法の変化にともなって「下の句」のカードの置き方、散らし方も変化した。「下の句」のカードの展開の仕方であるが、現代の遊技法では「散らし」と呼ぶ、遊技の場に無造作に散らし置いて取るものや、現代では「源平」と呼ぶ、遊技者に何枚かのカードが配られてそれを自分の前に並べて取る方式も古くから開発されていた。その際に対戦相手の手元にある札を取ることができて取った枚数を競う遊技法ではそれで良いが、自陣のカードを早く取り尽くした者が勝ちという遊技法であれば、相手の手元のカードを取った場合はその代りに自陣のカードを一枚相手方に渡すことになる。
こうした遊技法では、和歌を暗記しているかどうかなど、腕前の巧拙が決め手になるが、読み上げる遊技法が開発された当初は、もっとシンプルで、自陣のカードは自分しか取れないという決まりの下で、配られたカードを四角形や三角形などの一定の形に並べ、読み上げられたカードを裏返してゆき、近代のビンゴゲームのように、縦一列に、あるいは横一列にカードが揃って裏返しされたら勝ちあるいは一着にするという遊技法であったと思われる。これは、読まれる順番という偶然によって勝負するのであり、多分に賭博性が強く、和歌の教養と無関係の遊技法である。だが、和歌の文学的な内容そのものにはあまり興味がない一般庶民には、優雅な歌合せかるたで卑俗に遊べる魅力が勝っていたのであろう。江戸時代中期はこの遊技法が広く流行した。また、これではあまりに偶然性に偏り過ぎるという意味で、他者の手元のカードを取ることが許されるというルールを付け加えたこともあったと想定されている。
[1] 平野健次「伝統的概念理論用語・歌」『日本音楽大事典』、平凡社、平成元年、九四頁。
[2] 三田村鳶魚「かるたのいろいろ」『愛育』昭和十三年一月号、『江戸の生活』昭和十六年、大東出版社、五〇頁。
[3] 雑俳集「千代見艸」『不角前句付集一』雑俳集成第二期⑤、鈴木勝忠私家版、平成三年、四五頁。
[4] 近松門左衛門『娥歌かるた』『近松全集』第八巻、岩波書店、平成元年、六四三頁。