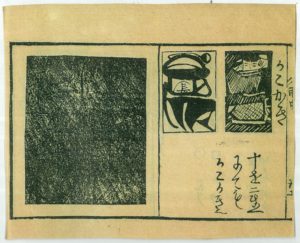近代の百人一首の遊技法では、和歌の上の句のカードが読み上げられ、対応する下の句のカードを素早く取ることが要点になり、ついには「競技かるた」としてもっぱらスピードを競う体育の試合の様相を示すようになったが、江戸時代には、スピードに拘泥しない遊技法があり、とくに、古い時期のものには、他の遊技者に配られたカードに侵略して攻撃する動作がない優雅な遊技があった。例えば、岡山県には「むべ山かるた」と称する百人一首かるたの遊技法があった。そこでは、六人で遊ぶときはひとりに一六枚の下の句札を配り、それを縦横四枚ずつに並べてもらう。あまった四枚は別に分けておいて、一〇〇枚の読み札を読み上げることになる。四人であれば二十五枚ずつ配って、縦横五枚ずつに並べる。読み手に読み上げられた札は裏返される。縦、横、斜めのいずれか、一列の札が全部裏返されれば勝ちである。これは、いうならば百人一首のビンゴゲームであり、普通のビンゴゲームであればディーラーが番号を読み上げるところを、その代わりに読み手が和歌を読むのである。
この遊技法のように、下の句札を自分の前に並べるというのが発祥期の歌かるたの遊技法の特徴である。江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の歌合せかるたの遊技法の説明文章の付図や、遊技風景の図像では札をきちんと並べて描いたものが多い。「散し」は発祥が少し遅いように思われる。
「むべ山かるた」と呼ばれる遊技法には別異のものがある。京都の神官、出雲路家の家系である出雲路敬和は、昭和二十七年(1952)に同家に残る「むべ山遊び」という百人一首かるたの遊技法を記録している[1]。出雲路によると、五人で遊技するときは下の句札を一人二十枚ずつ配り、六人で遊戯するときは十六枚ずつ配って余った四枚は脇にのけて置き、各人が自分の前にそれを並べ、読み手が上の句札で和歌の本文を読み上げてゲームが進行し、自分に配られたカードであればそれを伏せ、早く伏せ尽くしたものが勝利者となる。岡山の「むべ山」は読まれたカードがラインになるように競うものであり、京都の「むべ山」は手札を早く取り尽くすことが目標になる。いずれの場合も、読み手が読むカードの順番によって勝敗が大きく決まる。スピードで相手を出し抜いて状況を切り開くという近代的な発想はない。
京都の遊技法を興味深いものにしているのは「やくもの」とされるカード四十五枚の存在である。下の句に「人にはつげよ」「恋ぞつもりて」「逢坂の関」「傾くまでの月」「わが衣手に雪」「花ぞ昔の」など、「人」「恋」「関」「雪」「月」「花」のある二十八枚に第一首の「秋の田の」と第百首の「ももしきや」、合計で三十枚のうちのどれかであれば、それが自分に配られたカードの中にあった者はそれを伏せるとともに右隣の参加者に手札の中から一枚を送り、下の句に「人の恋しき」「花よりほかに知る人」「恋しかるべき夜半の月」と役になる文字が重複する三枚のいずれかがある場合は二枚を送り、「富士の高ねに」「三笠の山に」「をとめの姿」「と山のかすみ」の四枚のうちのいずれかであれば遊技の参加者全員に一枚ずつ配ることができる。一番劇的なのは「むべ山風を」であり、全参加者に二枚ずつ配ることができるので手札が一挙に大きく減少して勝利に近づく。一方、「泣き」と呼ばれる「悲し」や「涙」がある三枚のカード、「秋は悲しき」「うきにたへぬは涙」「かこち顔なる我が涙」の場合は全参加者から一枚ずつを送り込まれる。さらに「我ならなくに」「友ならなくに」「鹿ぞなくなる」「綱手かなしも」の四枚は「泣く」でも「悲し」でもないがたまたま同音の「なく」や「かなし」があるために「泣き」とされ、合計すると「泣き」は七枚あることになる。このプラスマイナスのカードがほぼ半数を占めるので手札のカードの増減が激しく、ゲームとして面白味が増している。
この遊技法では、文字を憶えるだけでなく、歌の意味まで憶えている必要があるが、文字を読解するスピードは問題にはならない。そこにこの遊技の優雅さが表れていて、こうしたローカルな遊技法には興味深いものがあると思う。
ここで興味ある史料が、二枚の「むべ山」廻り雙六である。一枚は、十返舎一九校、歌川豊国画、東都地本錦繪問屋両國吉川町大黒屋平吉板の「新板百人一首むべ山雙六」[2]である。これは振出しが「天智天皇」で骰子を使って百コマを進み、「順徳院」の次が「上り」というものであるが、各コマに歌人画があり、「雪」「月」「花」の和歌と「むべ山」のコマに「ほうび」の印がある。これは、この双六が、「むべ山」が通常の百人一首かるたを使用する遊技法であった時期、場所のものであった事情を示すのであり、「ほうび」も「むべ山」と「雪」「月」「花」限りと限定的でおとなしい。「ほうび」の内容は分からない。
もう一枚は、名古屋本町十三丁目の〇集堂板の「新板無邊山廻し雙六」[3]である。これについては、似たようなものが東京学芸大学付属図書館にあり、そちらでは「新板無邊山嘉留多廻大雙六」[4]と名付けられている。これも振出しが天智天皇で、順徳院の次が上りである点は前者と同じであるが、各コマには下の句のおどけた歌意図があり、「むべ山」専用札ができた後の時代のものであることが分かる。前者とは時代が違う。「ほうび」が、「むべ山」「雪」「月」「花」に加えて「恋」「関」と増加している。付表によると、「ほうび」には専用の「紙」が用意されていて、「月」は一枚、「雪」は三枚、「花」は二枚、「恋」は五枚、「関」は四枚、そして「むべ嵐」は十枚を他の人からもらい、場に一枚を出す決まりである。これだけの量だと、遊技をスムースに進行させるには、参加者の各人に数十枚の「紙」を持たせる必要がある。多分、「紙」には十枚分の特別な「紙」も用意されたのだと思う。また、「ほうび」の中身も良く分らないが、遊技終了後に獲得した「紙」の枚数に応じて交換されるようなものであるとすると、そうだとすると、これはもう、金銭と交換されるようになった賭博系の「むべ山」遊技の一歩手前である。
この「むべ山かるた」の遊技法は、江戸時代中期(1704~89)に江戸で男性が遊ぶ賭博の遊技として大流行し、それ専用のカードが大坂で制作されて江戸に移出されたが、それについては次項に詳述する。ここでは、百人一首の優雅な遊技法としての「むべ山かるた」の消長に絞るが、江戸では明治年間(1868~1912)まで普通に遊技されていたようである。明治三十四年(1901)刊の大田才次郎編『日本全国児童遊戯法』の東京編には「骨牌取(かるたと)り」があり、この遊技法が説明されている。「春季翫(もてあそ)ばるるものは、上流社会の児童にありては、源氏(げんじ)がるた、伊勢物語(いせものがたり)がるた、百人一首の類なれど、前二種は一般に行われず、ただ百人一首は当時流行を極め居り」[5]である。ただ、百人一首の遊技法が紹介されたのは東京だけで、全国各地の遊戯の紹介には京都、大阪以下、どの地方でも登場しない。基本的には百人一首は大人の遊技具であったようである。
大田によると、かるたの遊技法には「散らし」と「お分け」の二種がある。「散らし」は「数の多く取れし者を勝とし」であり、「お分け」は「総数の骨牌を人員に等分し」であるが、その勝敗については書かれていない。ただ、常識的に考えて配分された手札を早く取り尽くしたものが勝になるのだろう。「お分け」は、一人ひとりが自分の手札を取ることで勝敗を争うものだが、その別種として「源平」という二組に分かれての対抗戦がある。
百人一首には「役牌(やくがるた)」と「罰牌(ばつがるた)」がある。役牌は「雪、月、花、人、恋、乙女、むべ山等」であり、罰牌は「憂き、かこち、涙等」である。この札が出たときは、「定めの如く数札(かずふだ)の他の骨牌を授受するなり」とされている。また、これと別に「お伏せ」といって配分された札の中の数枚を伏せて置きその札が出れば「お伏せ何枚」といって「他の札を次順(つぎじゅん)の者若しくは『源平』なれば敵に送るなり」である。また、「鼻毛抜き」と言って他の者の手札を取ることができて、その場合は定めた枚数の札を送り込むことができるが、「鼻毛抜き」に失敗して他の札に触れたときは「お手付(おてつけ)」となって定めた枚数を送り込まれることになる。
こうしてみると、京都の出雲路家に代々伝承してきた「むべ山かるた」と名古屋の双六遊技、そして大田が紹介する東京の上流社会の家庭での遊技とがいちじるしく類似していることが分かる。また、「伏せ札」については、次項で扱う江戸の遊技法に由来するように見える。こうした、家庭での遊技である「むべ山かるた」を賭博遊技の「むべ山」の蔭に隠して無視するのは、カルタ史の理解としてはいかがなものか、と思う。
[1] 出雲路敬和「歌がるたむべ山遊び」、『京都』、昭和二十七年一号、「京のくらし」(『町人文化百科論集』第六巻)、柏書房、昭和五十六年、一七五頁。
[2] 「新板百人一首むべ山雙六」『百人一首への招待』、平凡社、平成二十五年、一五八頁。
[3] 「新板無邊山廻し雙六」『企画展 百人一首かるたの世界』、大津市歴史博物館、平成二十五年、二四頁。
[4] 「新板無邊山嘉留多廻大雙六」https://library.ugakugei.ac.jp/notice/20100601_1/topm_l/L013.jpg
[5] 大田才次郎編『日本全国児童遊戯法』東洋文庫一二二、平凡社、昭和四十三年、三二頁。