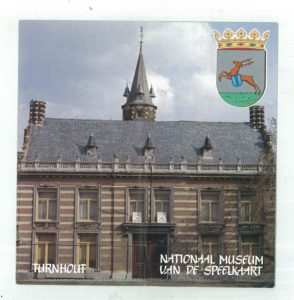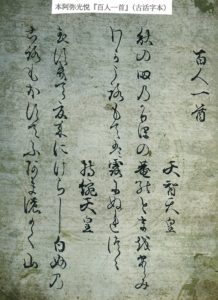『日葡辞書』は、よく知られているように、十六世紀末期に来日したイエズス会の修道士たちによって編纂され、慶長八年(1603)に公刊された木版の日本語、ポルトガル語の辞書であり、約三万二千語を収録している。これは当時の日本語に関する第一級の史料であり、収録されている語を通じて当時の日本社会の諸事情が明らかになる価値も大きい。また、ポルトガル語の研究史上でも十六世紀当時の実際を知る好個の史料となっている。
ところが、この辞書に「かるた」がない。日本ではすでにその数年以前の長曾我部元親の掟書に「かるた」とあり、長曾我部も従軍した朝鮮の役で肥前名護屋に設定された豊臣秀吉の本営では全国から集まった軍勢の間でこの遊技が流行し、秀吉の没後、軍勢が上方に帰還するのに伴って上方でも大流行したのであるから、イエズス会の修道士の耳に届き、『日葡辞書』に日本語の外来語として「かるた」があっても不思議ではない。それが、この語は三万二千語の中に入らなかったのである。謎である。
ここで、イエズス会の修道士が賭博遊技を嫌って、その用語の収録を憚ったのではないかと考えると、同書には、当時カルタ以上に人々に愛好された「すごろく」(盤雙六)という語も収録されていない。賭博遊技の王者であった「さい」や「さいころ」もない。また、カルタと言えば、慶長、元和年間は日本式の「絵合せかるた」や「歌合せかるた」の誕生期でもあるが、「うたかるた」「えあわせ」「かいおおい」「かいあわせ」「こきんのふだ」「ひゃくにんしゅ」などの語は収録されておらず、「げんじ」は関東の武士集団とされ、さらに同音異語として項目を別に立てて小説であるとの説明が収録されているが、そこに和歌が含まれていることも、発祥期の「歌合せかるた」ではもっとも普通の主題であったことも説明されていない。結局、遊技の関係ではわずかに「ご」に囲碁の簡単な説明と「碁を打つ」の例文があり、「しやうぎ」では当時の「中将棋」と「小将棋」(今日の将棋)の区別もないままに、説明抜きで「将棋をさす」の例文だけが載っている。
こうした遊技、特に賭博遊技の関連語の冷遇は、第二次大戦前にそれを嫌悪して資料蒐集の対象から外した柳田國男の民俗学を思い起こさせるものがあり、イエズス会関係者が持っていた賭博行為に対する嫌悪感に由来する歪みであるように見えるが、『日葡辞書』をよく見ると、肝心の「ばくち」は収録されていて、骰子を使ってする勝負事との説明があり、さらに「ばくちわざ」「ばくちうち」「ばくちうつ」「ばくちうった」「ばくちずき」と例文も豊富である。賭博遊技の関連語を排除しようということでもなさそうである。だから、イエズス会の賭博嫌いと即断することは避けたい。
ここまでは以前から私も認識していた。結論が「謎」なので自分のことながら情けないが。ところが最近、藤女子大学の漆崎正人による新しい研究の成果に接することができた。慶長八、九年(1603~04)刊の『日葡辞書』及び文禄四年(1595)刊の『羅葡日対訳辞書』の中でポルトガル語のcartaはどのように理解されていたのかを綿密に調べた研究が相次いで明らかになったのである[1]。漆崎によると、『日葡辞書』でcartaが登場するのは二百か所以上あるが、そのほとんどすべてが文字を載せた紙類、特に書簡のようなものを意味しており、わずかに証書類を示すこともあるが、要するに文章を書いた紙であった。
いっぽう、『日葡辞書』に先駆けて出版された『羅葡日対訳辞書』においては、見出しのラテン語単語に対応するポルトガル語の解説文中にcartaが登場するのは三十二例ある。その主要な内容は『日葡辞書』と同様の「書状」であるが、二か所、「カルタ、さいころ遊びの賭博」という文章になっている箇所がある。だが、この説明に対応する日本語は「Bacuchivchi」(博奕打ち)ないし「Bacuchi, suguroku, bacuyeqinado」(博奕(ばくち)、雙六(すごろく)、博奕(ばくえき)など)であって、この文章で示されているのはポルトガル語のcartaであって日本語としての「カルタ」ではない。また、日本語の賭博に関しては、『日葡辞書』では「Bacuchi」(博奕(ばくち))はさいころ遊びの賭博、「Suguroku」(雙六(すごろく))は駒を用いる賭博、「Bacuyeki」(博奕(ばくえき))はさいころ遊び、駒ゲームなどの賭博と説明されている。つまり、ポルトガル語のcartaには遊技具としてのカルタという意味で使われている例がわずかにあるが、日本語としては、賭博の総称として「バクエキ」があり、それには主として骰子賭博を意味する「バクチ」と、主として雙六を意味する「スグロク」が含まれるが、「カルタ」という言葉は認識されていない。
これは驚くべき事実の発見である。カルタは図像を載せた紙片である。文字が載せてある紙片は四十八枚のセットの中で二、三枚でしかないし、それも主としては図像のある紙片で図柄の一部に添えられたものに過ぎない。こういうカルタがすでに広く出回って外来語にもなっているのに、同音のcartaは別のものを指していた。この奇妙な事態は説明が困難である。カルタをめぐる謎は深まったといわねばならない。
この事態を次のように理解することはできないだろうか。十六世紀後半、カルタは日本の平戸や長崎のような港町の周辺に伝来した。その際には、カルタのカードと遊技法は確かに伝わったが、遊技法はポルトガル船の中国人船員などから口頭で伝えられたものであり、日本人は、その発音の音声を耳にして「カルタ」という表記を行った。したがって、カルタがポルトガル語であるのかそれ以外の言語、例えば中国人船員が使っていたであろう浙江省や福建省の訛りをもった中国語であるのかも不明であったし、日本人はその原語やその綴りにも関心はなかった。そしてその後、ポルトガル語のcartaが伝来した時、それは文書を記載した紙の場合に用いられていたので、日本人は、cartaはそのような紙類を意味する語だと理解した。そのとき日本人は、以前から伝わっていた「カルタ」が新来のcartaと同じ語だとは考えなかったのであろう。多分、すでに日本人の耳になじんでいた福建省あたりの中国人の発する「カルタ」の発音とポルトガル人宣教師の発するcartaの発音が微妙に違っていて、同一の語と認識できなかったのであろう。こういう事態はしばしば生じている。バッハを楽聖と崇拝する日本人が、いやベイクこそすばらしいというアメリカ人と論争になり、実は同一人を話していたことに気付かないというジョークのような話、「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」の世界である。
「カルタ」は実は日本人にカルタの遊技を教えた中国人船員の発した中国語の地方訛りの濃い方言であったのだろう。より正確に言うと、中国語にとっての外来語が中国人船員によって日本にもたらされたのであろう。この仮説が成り立つなら、カルタの中国経由伝来説に立った永見徳太郎は草葉の陰で喜ぶであろう。だが、『日葡辞書』における不在からここまで言ってしまってはあまりに危うい。私の記述も危なっかしい。この辺で打ち切ろう。この点は、「天正カルタ」の発祥を扱う際にもう一度立ち返って検討する。
「カルタ」という言葉の語義のうちで、遊技法という意味とカードという意味では語義の成立時期にずれがあり、『羅葡日対訳辞書』や『日葡辞書』はちょうどそのはざまに成立したのではないかという考え方は、漆崎の論文に触発されるまでは全く思いつかなかった。これまでにかるた史を扱った者の中でも、こういう疑問を表明したものは見たことがない。「カルタ」という語の謎は学術的にはまだ解けていない。
漆崎の周到な研究でありがたいもう一つの点は、それが、慶長年間(1596~1915)にカルタが他のとんでもなく違う別の言葉で呼ばれていなかったことが理解できた点である。たとえば、「札の遊び」、「南蛮札」、「葉子」あるいはもっと飛び抜けて、「悪魔の札」「厚紙」「紋標札」その他、さまざまな可能性が想定できる。当時こういう呼び方をされていて、それが『日葡辞書』に収録されているとすれば、「カルタ」の不存在は全く異なる意味合いを帯びてくる。だが、もしこういう言葉が使われていたとすると、そのポルトガル語の説明文の中に「cartaの遊技」のようにcartaの用例が登場するはずである。しかし、漆崎の悉皆調査ではそういうcartaの用例が見つからないのであるから、日本語で「カルタ」以外の表現が用いられていなかったことが確認できる。漆崎の調査はこういう落とし穴を塞いでくれていてとてもありがたいのである。
[1] 漆崎正人「外来語『カルタ』成立の周辺―『日葡辞書』とcarta―」『藤女子大学国文学雑誌』第九十四号、藤女子大学日本語・日本文学会、二〇一六年、一六頁。同「外来語『カルタ』の成立をめぐって―『羅葡日対訳辞書』とcarta―』『藤女子大学国文学雑誌』第九十五号、藤女子大学日本語・日本文学会、二〇一六年、一三頁。