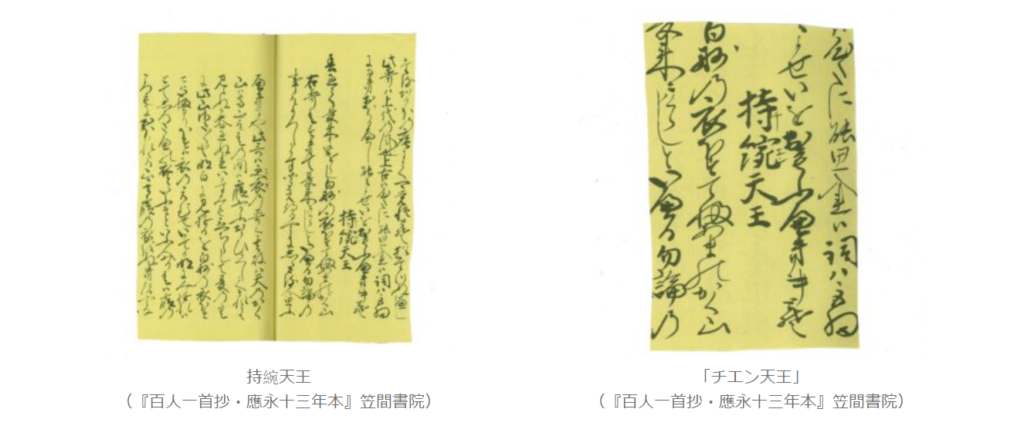日本のカルタの歴史を考えるとき、まず検討するべきなのは、中国のカルタの伝来であろう。もともとカルタの母国は中国で、唐代(七世紀~十世紀)から存在していた紙牌の遊技が十四世紀までにアラビアを経てヨーロッパのアラゴン連合王国の領域に入ってそこから全ヨーロッパに広まり、カルタ遊びとして大いに栄え、十六世紀の大航海時代にポルトガル船によって再びアジアに戻ってきた。この長い期間に、母国中国では当然にカルタ遊技は発展し、改良もされていたと思われる。こうした発達の影響を隣国日本が受けて、中国に古くからあった各種の「紙牌」や「骨牌」が直接に伝来していても不思議でない。だが、その記録はないし、中世の発掘考古学でも紙牌も骨牌も発見された事例はない。日本になぜ中国の紙牌の痕跡がないのか。この不在は何とも不思議であるし、不気味でもある。
享保十五年(1730)に刊行された殊意痴『白河燕談』[1]はその希少な例外の記録で、「加留太」を説明した部分の最後に、「又唐人博奕片札模様所画皆異是也」という一文がある。「また、中国人が博奕する切れ端状の札は画かれた模様が皆これと異なるのである。」と訳される。カルタの本家、元祖、根本である中国のカードなのに、大きく発展したヨーロッパ生まれの子孫と対比して「片札」呼ばわりではちょっと気の毒な気もするが、当時の日本人の正直な感想としてみれば適切な表現であろう。
この記録より少し時期をさかのぼるが、明代 (1368~1644)の中国は倭寇の被害に苦しみ、この有害勢力の分析、対応のために日本研究が進められていて、その一環として日本語辞書が編まれていた。その一つ『日本考』[2]の「巻之四・語音」は十六世紀前半、日本の年号でいえば天文年間(1533~55)に成立しているが、そこに「骨牌 同音 こつはい」と「紙牌 無」という記述がある。日本には、中国語と同じ発音の「骨牌(コツハイ)」があり、「紙牌(チーパイ)」はないということである。この辞書は、中国人が日本に来訪して言葉を蒐集したものではなく、もっぱら中国に滞在中の日本人からの取材で済ませていたものと思われるし、その取材の程度は疎略で、複数の取材先からの情報を比較したり確認したりした痕跡もあまりない。また、「骨牌」を中国語の標準的な発音の「クーパイ」ではなく「コツハイ」と読んで日本語に同音の言葉があるとした理由も分らない。しかしいずれにせよ、中国に滞在していた日本人が、中国の「紙牌」「骨牌」を知っていて、日本国内にもあるとかないとか答えていることが重要である。
中国でいえば明代(1368~1644)、日本でいえば室町時代に日本に伝来していた中国のカルタはどんなものだったのであろうか。もともと明代(1368~1644)の中国には、「葉子」とも呼ばれた紙製の「闘牌」「紙牌」と、「天九牌」と呼ばれた牛骨ないし象牙製でドミノ牌系の「骨牌」とがあった。「天九牌」にはその図柄を細長い「葉子」と似た細長い紙片に写し取った遊技具の「天九紙牌」もある。この「紙牌」と「骨牌」の両者のいずれもが日本に伝来していた可能性がある。だが、「骨牌」に関して言えば、中世日本の発掘考古学によって木製の「将棋駒」や牛骨製の「賽」などの遺物が次々と明らかになっているのに、遺跡からの「骨牌」発掘の報告はない。「紙牌」についても、腐ったり焼けたりして消滅する可能性が「骨牌」よりもはるかに高いこともあって、これまた発見の報告がない。「骨牌」「紙牌」について触れている同時代の日本側の文献もない。そうだとしても、当時の日中の交流、交易の状況から判断すれば、日本に中国のカルタが伝来していたであろうことは十分に推測できる。
『日本考』の記述であるが、私は、日本に「骨牌」があって「紙牌」がないというのは逆ではないかと思っている。日本では、江戸時代に、ポルトガル船に由来するヨーロッパのカルタを「骨牌」と表記して、「こつぱい」ないし「かるた」と読んでいた。この伝統は明治時代にも残っていて、明治三十五年(2002)のカルタ課税の税法は「骨牌税法」と表記して「かるたぜいほう」と読ませた。日本で、紙製であるヨーロッパのカルタがなぜ「紙牌」ではなく「骨牌」と書かれたのかは分っていない。ありうるストーリーは、①単なる誤解、②すでに日本に中国の「紙牌」が伝来していて、南蛮人のカルタはそれとまるで違うので別種であることを強調するために「紙牌(カルタ)」ではなく「骨牌(カルタ)」という表記を選んだ、③ポルトガル船が最初にもたらしたのはドミノ系の牛骨製の遊技具なので「骨牌(カルタ)」と呼ばれ、その呼称が、その後に「紙牌」が伝来しても残った。④日本ではそれ以前から中国製の紙製のカードを「骨牌」と呼ぶ習慣があったのでそれを転用した、等の筋書きであるが、『日本考』を読むと、この中の④、カルタの伝来以前から日本には中国の紙製のカルタを「骨牌(コツパイ)」と呼ぶ奇妙な習慣があったというストーリーが最もありうるもののように思える。中国の港町、泉州であろうか、寧波であろうか、揚州であろうか、マカオであろうか、滞在している日本人が中国人に「貴国に骨牌はありやなしや」と問われて、「有り」と答える。その発音は、カルタという南蛮の音ではなく「こつはい」であった。そして、続いて「しからば紙牌はありや」と問われて、「さような品は聞いたことも無し」と答える。そんな情景が想像されるところである。
中国の「紙牌」は、元来は通貨に由来する「十万」「万」「索(百)」「銭(一)」の四紋標、四十枚で一組であったが、明代 (1368~1644)までに「十万」の紋標に属する十枚を取り除いて「万」、「索」、「銭」の三紋標、三十枚を一組として遊技に用いるようになり、更にデュプリケイションを繰り返して四組分(北京に近い地方などでは五組分)を一緒にして合計百二十枚以上で遊技に用いるようになると、その使用枚数が多いことから、多くのカードを同時に手中に持ちやすいように、細長く作るようになり、黒裏、切り離しのものとなった。ヨーロッパのカルタや日本のカルタを見なれた日本人の目には、「切れ端のようなカード」に見えたことであろう。『白河燕談』の記載はそういうカルタの目撃証言として信頼できると思う。
ここで中国カルタの研究史に触れるのはやや射程外の事項を扱うように思えるが一言しておこう。中国のカルタ史は、唐の時代から始まり、歴史は長いが、信頼できる史料は少ない。そういう中で、大谷通順の「馬掉牌考」[3]は、昭和時代の末期(1985~1989)に、当時明らかになっていた中国の史料に基づいた研究の業績であり、当時判明していた諸事情を丁寧に掬い取っており、中国語の文献をきちんと読解して歴史を明らかにしている。ただ、そこでは中国に固有の紙牌の歴史の解明が主題とされており、十六世紀にポルトガル船によって中国にもたらされたヨーロッパのカルタと、それの中国国内における普及、そして、外来の文化を溶かし込んで消化する中国の強力な文化的な磁場の中で生じたであろう、用語、遊技法、カードの図像などでの中国化については主題の外に置かれている。したがって、日本のカルタ史にとっては最も関心が強い、中国経由でのヨーロッパのカルタの伝来があったのかなかったのかはよく分らない。なお、大谷は平成二十八年(2016)に『麻雀の誕生』[4]を表し、主として二十世紀初めの上海における中国式紙牌の遊技「碰和(ポンフー)」の流行と麻雀骨牌の普及を説明している。引き続き、十九世紀中期の長江沿岸地域における馬吊紙牌の骨牌への変身と、その後に浙江省の寧波市で生じた「中」「発」「白」の三元牌がそろった近代麻雀骨牌セットの成立を明らかにする研究成果の公表が強く望まれる。
[1] 殊意痴『白河燕談』巻一、国会図書館蔵本。
[2] 渡辺三男『譯註日本考』大東出版社、昭和十八年、二六〇頁。
[3] 大谷通順「馬掉牌考」『北海道大学文学部紀要』第三十八巻一号、北海道大学文学部、平成元年、八九頁。
[4] 大谷通順『麻雀の誕生』、大修館書店、平成二十八年。