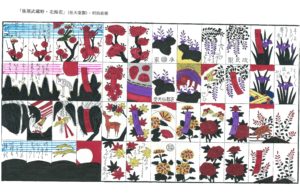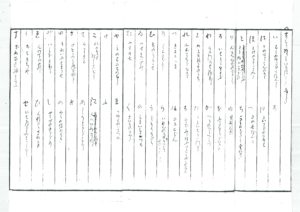こうした詐欺的なカルタの制作は昭和後期にまで続いていて、私もカルタの制作者サイドでわずかに見聞する機会があった。これは、なにしろ取材先の非合法な行為に関することなので、ある時、あるカルタ屋でとしかいいようがないし、読者が実証も反論もする余地のないデータを掲載して良いものか迷ったが、余計な無駄話だと寛大にお考えいただけたらありがたいと思って、本章で扱う昭和前期(1926~45)までの時期とずれる昭和後期(1945~89)の話であるが記載する。
ある廃業した元カルタ屋で詐欺札の作り方を聞いたことがある。そのカルタ屋では、花札のカードの表紙(おもてがみ)と芯紙を貼り合わせた「生地」と裏紙とを貼り合わせる作業工程の日に、注文元からその筋の人が来て、馬の尾の毛を短く切ったものを、「松」はここ、「梅」はここと、表紙(おもてがみ)の図柄に対応させて芯紙と裏紙の間でその人の指示する場所に置いてから貼りつけて縁返しを行った。そうして何組分かの作業が済むとその人は帰ってしまう。その後残った職人がそのカードを乾燥させ、ローラーにかけたり、枚数の誤りや同じ図像のカードの重複などがないように特に入念に品質検査をしたりしてから包装紙に包んで、骨牌税の納税のために収入印紙を貼って、小荷物にして郵便局から発送する。こういう花札のカードは通常の物の販売価格の百倍以上でその筋の人が買い取るので、カルタ屋としては十組も作れば千組以上の売り上げになる楽な仕事だし注文を断ることはない。一方、賭場では、使用するカードに傷が付いたりするといけないので頻繁に新しいものに替えるのであるが、郵便局から届いたままの小荷物として持ち込まれている包みを客の眼の前で開けて真新しいカードを取り出して、客に印紙も改めさせて事前に開封して細工したものではないと確認させてから使用するのだが、実は小荷物の封を切った瞬間に勝負は決まっていることになる。

(田 村将軍堂の札に偽装)」
詐欺札の制作方法を逐一聞いたのはこの時が最初だが、他のカルタ屋でも、それとない話を聞くことはあった。屏風のようになっている「ベカ札」の出来立ての物を分けてもらって、「梅」を「桜」に変える一瞬の手さばきを教えてもらい練習したこともある。カルタ屋にしてみれば制作した札が実際にスムースに作動しなければならないので、それを使う裏技にもある程度成熟しており、私にはとても良い教師であった。手にしたときは紋標が二つの「二」の札が、〇・一秒後に表面に返した時には紋標六つの「六」の札に早変わりし、「三」の札が「五」に変身する「手本引」での裏技も教えてもらい、習得した。玄人が使うガン札を読み取ろうとすると眼の悪い私には難しくて、熱中して顔を近づけすぎてしまい、それではバレていますよと笑われたこともある。あるとき、これも今では廃業した元カルタ屋であるが、店の主人にヒアリングしている間に若い男が注文したカルタを買いに来て、一言も口を利かないのに主人はすぐに立ち上がって注文の品の包みを渡して、無言のうちにその客が帰った後で、今のは特注の品物を引き取りに来た○○組の使い走りの若い衆ですが、最近はこうした特殊札を駆使したカルタ賭博のできる博徒が減って注文が少ないんですよ、と笑って話してくれた。顧客を楽しく遊ばせて、最後は胴元がしっかり頂くにはこういう小道具で仕掛けを演出しなければ、ということで、業界の必需品作りの意識が強く、不正行為のほう助という罪悪感はあまりないように見えた。いずれにせよ、遠い昭和の思い出である。いや、あるいは幻想であったのかもしれない。
こうした注文が続くと、いつしかカルタ屋はどこか特定の博徒の組との関係を深めることになる。まともなカルタ札も大量に買ってもらえる得意先になる。逆に、関係の深い組の衰退はカルタ屋の経営を困難にした。平成年間(1989~2019)の初めに大阪の伝統あるカルタ屋が一軒、ひっそりと店を閉じた。私がその後にその店に遊びに行って閉店に驚き、すっかり暇になった元主人とよもやま話をしていた時に、「なにしろ我が家は一和会の御用達でしたから」と呟いたのが印象に残っている。山口組と一和会の抗争が一和会の敗北、解散で終わった直後のことである。また、京都のあるカルタ屋の倉庫には、明治時代後期(1902~12)のものであるがある博徒組織の総長以下の連名で、自分たちが賭博罪で捕まった際に博奕用品を提供してもらったと自白したためにこのカルタ屋にまで追及の手が伸びて迷惑をかけたことを仁義の道に反したと謝罪する立派な詫び状が残っていた。いくつかの地方札や手本引の札などは、素人はまず買わないから、顧客は博徒集団ということになる。そういう札を自発的に作っているのか、作らされているのかは分からないが、微妙な影が射す話である。
詐欺札としては、遠い昔の江戸時代前期、元禄年間(1688~1702)の井原西鶴の『世間胸算用 巻三』でカルタを買いに行かされた丁稚が帰路に良い札に爪で裏に心覚えを付ける話が掲載されている。こうした「手目カルタ」の歴史はカルタの歴史そのものと同じように古いのであるが、明治期以降には、①特定のカードの裏面に赤点、黒点、爪痕、針刺しの痕などのガンを付けた「ガン付札」、②特定のカードに馬の毛を加えた「毛入ガン付札」、③特定のカードの「生地」の一部を削り取って薄くしてから裏紙を貼り合わせた「削ガン付札」、④ゲーム中、カードを切る際に特定のカードを思う場所に配するようにそれだけを少し長めか広めに仕立てておく「長札」や「広札」、⑤同じくゲーム中の切る動作で選び出せるように特定のカードだけ撥(ばち)のように台形に仕立てる「撥札」、⑥特定のカードの表紙(おもてがみ)に特殊な液体を塗って滑りの良し悪しでどの札かを判断する「粗滑(ざらすべ)札」、⑦特定のカードだけ普通の花札と代える「薄口花」がある。テレビや映画では、伏せられたカードを右側から表にすると梅で左側からすると桜になるいわゆる「屏風札」(ベカ札)が画面での見栄えがいいので使われるが、こういう必殺の仕掛札を使うと常に露見する危険性が伴うのであって、特別の事情がないと使われない。それよりはむしろ、いかにもさりげなく使えて、しかももしペテンが露見しても札を制作したカルタ屋のせいにして言い逃れができるような詐欺札の方が博徒にとってはベターである。
私が不思議だと思っていたのは、昭和後期(1945~89)になっても、大手のカルタ屋が正規の商品として売っていた「薄口花札」である。これは、同じカルタ屋の通常の商品と造りや図柄が全く同じで、ただカードの厚みが微妙に薄いところだけが異なる。花札の扱いに慣れていない人だと、手にしても違いが分からない微妙な違いの細工である。容易に想像できるように、例えばオイチョカブ系の遊技で事前に「二」から「五」までのカードをこの「薄口花札」にすり替えておいて、残りは普通の厚みのカードと組み合わせておき、賭場で素早く操作して賭客に不都合なカードを送ったり、自分に有利なカードを手繰り寄せたりすれば、勝負はとても有利で、まずは負けない。この方式だと、万一、一部のカードが薄いと賭客に苦情を言われても、図柄も細工も違いはないのでカルタ屋の不注意な組み合わせミスとして弁解できる。こういう詐術に使用する以外に使い方が分からない「薄口花札」が堂々と売られているのに驚いて、制作者に聞くと、薄口花札は手が小さい芸者さんなどの女性用ですというとても便利な理屈が開陳された。これも笑える。
また、カードの裏面に印を付けるなどの細工をした「ガン附札」では、使い手の眼の良し悪しに応じて傷(ガン)の大小、深浅、封入した馬の毛の太細などの差があり、ガンが強ければ分りよいが発覚もしやすいのであり、熟達した博徒は、客には絶対に見破れない極細の細かさの仕掛けのカードを使うので、自分の眼の健康管理にとても気を使っていたようである。年を重ねて眼が悪くなったので引退したという元博徒に出会ったこともある。
こうした仕掛けや技を使ったカルタ賭博は、昭和四十年代(1965~74)で衰退に向かった。元読売新聞社会部記者で作家に転じた飯干晃一は、昭和四十年代後半(1970~74)や五十年代(1975~84)にやくざに関する作品を多数執筆した。そこにはカルタ賭博の情景もいくつか表現されている。飯干はまた、詐欺賭博の手口にも詳しくて、それを紹介する文章も書いている[1]。カルタ賭博にのめり込んだ当事者の発言として面白いのは、落語家の月亭可朝のインタビューを吉川潮が文章にした『月亭可朝のナニワ博打八景』[2]で、可朝が京都で「虫花」札を使ったオイチョカブに加わって七千万円の借りを作り、見かねた知人が専門の仕事師を紹介して、その者のワザで全額を取り返すまでが事細かに書かれていて当時の状況が良く理解できる。
なお、最後に研究者としての弁解をさせていただく。私は、賭博系のカルタ札の歴史を調査し、史料を蒐集する中で、何回か、「花札の遊び方に詳しい人」を紹介されたことがある。そして、実際にその人に会って話を聞き、地域で人気のある、腰の低い世話役の人が実は博徒であったり暴力団の構成員であったりしたことも何回かある。彼らはとても親切で、「これから先は実際に見学にいらっしゃいませんか」と誘ってきた。この言葉で初めて話し合っている人が賭場の元締めだと分かったこともある。それはもちろん、自分の賭場に客としてこないかという誘いである。気が付けば、素人を誘い込むやくざの表情になっている。
私は、賭博系のカルタの歴史を調べ出したときに、その筋の人からの取材はしないと決めていた。警察の保安課の知人も、それがよい。でも何かトラブルに巻き込まれたらすぐに警察に連絡してください。私たちが先生をお守りします、と言っていた。私としてはとても惜しいと思うこともあった。その地方札を使っているおそらく最後の賭場の関係者に出会い、そこを調べればその遊技法が分かり、今この機会に調べなければ間もなくその賭場が終わってもう誰にも遊技法が分からなくなると予測できるのに、調査、取材から撤退するのであるから苦痛でもあった。だが、この一線を超えて親しくなれば、当初は貴重な情報を得られるであろうし、多少の小遣い稼ぎになるであろうけれども、いずれその先には地獄しか待っていないのだからと、賭博系カルタの遊技法に関する生きた情報の宝の山を目の前にしているのに断念して撤退するのが常であった。でも、これが研究者として守るべき一線だと思っている。尾佐竹猛や三木今二のように、司法関係者として賭博犯を取り調べて情報を得る権力を持たない民間人の私なのであるから、取材の壁が厚かったし、今、ここで記述していても、微妙にぼやかしてある箇所もある。こういう取材の事情をご理解いただければ幸いである。
[1] 飯干晃一「昨今いかさま噺」『別冊太陽いろはかるた』一六五頁。
[2] 吉川潮『月亭可朝のナニワ博打八景』竹書房、平成十年。