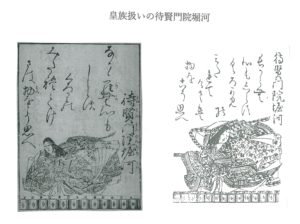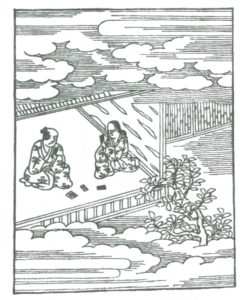こうして貝覆の伝統を引き継いで成立した絵合せかるたであるが、数十年後の貞享年間(1684~88)や元禄年間(1688~1704)になると、図像は二枚が対をなすものから二枚とも同一の図像の、制作が簡便で安価なものに替わり、ただ札の図像の主題を説明する文字が、一枚では漢字で、もう一枚では平仮名で書かれている点で、前段階のかるたの様式を受け継いでいるものに変化した。漢字で書かれたものを「漢字札」、平仮名で書かれたものを「仮名札」と命名したのは山口吉郎兵衛であり、私もそれを踏襲している。これが第二段階である。同じ図像の札を合せるのだからゲームとしては簡明になるが遊技具としては単調であり、また、文化の香りは薄くなる。
ところで、貝覆の遊技に由来する江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)の絵合せかるたや歌合せかるた、譬え合せかるたなどは、本来的には対をなしているはずの二枚の札で、事情があってばらばらに分かれているものを再結合させるのが遊技の基本である。この二枚絵合せかるたでは、たとえば「鶏」の絵札は「鶏」の絵札と合せる。「雄鶏」の絵札と「雌鶏」の絵札を合せるタイプのものと、同じ「雄鶏」の図像の絵札二枚を合せるものがあるが、「鶏」と「鳩」を合せることはないし、「鶏」と「鶏卵」を合わせて「親子丼」という役にするなどということもない。「鯛」は「鯛」と合せるし、「蕪」は「蕪」と合せる。能合せかるたや狂言合せかるたの場合は、同じ曲目の「シテ」と「アド」の図像の札を合せる。文字で合せる歌合せかるたでは、「春過ぎて」の上の句札は百枚ある下の句札の中で唯一「衣干すてふ」と合せるのであって、「衣かたしき」と合せることはない。譬え合せかるたでは、「地獄の沙汰も」は「金次第」なのであって、「地獄の沙汰も異なもの」ではないし、「縁は」は「異なもの」であって「縁は金次第」では、社会的には真実であるかもしれないが遊技としては微妙に合わない。言わばこのタイプの「合せ」かるたは、前世からの契り、赤い糸で結ばれている二枚のかるた札に運命的な再会をもたらす遊技である。合せる相手の札を何枚かの候補の中から選択するのではない。このタイプの遊技法をマッチング・ゲームと呼んでいる。
ところが、元禄年間(1688~1704)以降、特に江戸時代中期(1704~89)のかるた遊技ブームの中で生じた四枚絵合せかるたでは、絵合せかるたの遊技法に根本的な変化が生じた。この変化をこれから見ていきたいが、その前に断っておきたいのは、四枚絵合せかるたの出現は二枚絵合せかるたの廃絶を意味するものではないことである。江戸時代中期(1704~89)、後期(1789~1854)にも、二枚一組の絵合せかるたは健在であった。
京都の門跡寺院には、江戸時代中期以降のものであるが、上質な絵合せかるたが大事に保存されている。 また、これら上流階級向けの高級品とは別に、一般の社会に出回っていたであろう、「草花合せ」かるた、「虫合せ」かるた、「鳥合せ」かるたなどで、二枚の札のおのおので、上部に和歌の上の句と下の句が分かち書きされて一対をなすかるたが残されている。ただ、ここで注意するべきなのは、和歌はあくまでも絵合せかるたの添え物だということである。和歌が記載されていることで、そのかるたは文芸色を帯びるが、それはあくまでも文芸テイストを加味したということである。実際の遊技で、掲載されている和歌が読まれて対応するかるた札を探すという遊技法があったことを想像させるような史料は知らない。例えば花合せかるたの場合、江戸時代中期に木版の「武蔵野」が考案された際に、「松」「梅」「藤」「菖蒲」「芒」「紅葉」のカス札に和歌が書き込まれたが、実際の遊技では、和歌を解読したりすることがゲームの帰趨に影響することはなく、遊技者は、絵と絵を合せる、あるいは絵と字を合せるのであって、そこに和歌があることで、上品な文芸の遊技をしているという雰囲気が作られただけのことである。この点は、こういう和歌の文字が付いている各種の合せかるたや、譬えの文字が書かれている譬合せかるたが、和歌の鑑賞を母体とする歌合せかるたとは決定的に異なる点である。
この辺の理解が不十分で、いろは譬えかるたは歌合せかるたから派生した亜流のかるたであるとか、花札は歌合せかるたの亜流であるなどと強弁する者[3]がいるが、遊技の成り立ちを知らないファンタジーである。この論者は、譬合せかるたは、「上の句札」と「下の句札」を合わせ取る歌合せの遊技だと主張するが、「犬も歩けば」が上の句で、「棒に当る」が下の句だという前代未聞の珍解釈になる。「マッチ一本」が上の句で「火事の元」が下の句だとか、「地震、雷」が上の句で「火事、親父」が下の句だとか主張する日本文学史の専門家というのも前代未聞であるが、「月夜に釜抜かれる」の場合、「月夜に釜」と「抜かれる」に分けることもあるし、「月夜に」「釜抜かれる」と分けることもある。この譬えの「上の句」は、「月夜に」なのか「月夜に釜」なのか、凡人には判定不可能である。「歌人は居ながら」「名所を知る」なのか、「かじんは」「居ながら名所を知る」なのか、これも二通りあるが、どちらが正しいのか当の歌人でも決めかねるであろう。「蟷螂(とうろう)が斧」は、これで譬えとして完結しているので、「上の句」札だけで「下の句」札はなしという不思議な作品である。これではさすがにまずいと思ったのか、「歌かるたの亜流」とする者の中には、「下の句」は「を振って竜車に向ふ」だとする向きもあるが、さていかがなものか。「蟷螂が斧」という譬えにさらに続きがあるなどと知る者は知らないし、「下の句」が「を」という助詞で始まる和歌も聞いたことがない。カマキリが斧を振るって立ち向かうのは、鈴木棠三編『故事ことわざ辞典』によれば「隆車」、大きな車であり、これなら弱者が強者に立ち向かう譬えとして意味が通じるが、「竜車」とする譬えは存在しない。「竜車」という言葉自体が稀語で、天子の乗る「竜駕」(りゅうが、りょうが)の訛りであるが、いくらカマキリでも天皇の乗る車に斧を振るって立ち向かっては不忠、不敬の極みで譬えにも洒落にもならない。これもいかにも考察が足りない手抜きの強弁である。
くどいようだが強調しておこう。「いろは譬えかるた」は、江戸時代前期(1652~1704)までに成立した、譬えの上半分と下半分を分かち書きして、その内容を示す図像を配した二枚のかるた札を合わせ取る遊技法の「譬え絵合せかるた」が、江戸時代中期(1704~89)に、文字だけの文字札と文字に図像の付く絵札で構成される「譬えかるた」に変化し、字札を読んで絵札を取り合う遊技法になり、次に、絵札から文字が消え去る「古道斎かるた」の様なタイプのかるた札も誕生し、さらに、天明年間(1781~89)頃に活発になった、物事をいろは順に揃える風潮の盛り上がりによって、譬えをいろは順に揃えて、絵札に譬えの頭文字を丸で囲って入れる流行を取り入れて成立した、江戸時代後期(1789~1854)のかるたである。そこに「歌かるたの亜流」を見る様な理解は、歴史の誤解であり、このファンタジーを強弁して、とりとめのない史料でそれを強調するようになれば、それは単なる歴史の誤解の域を超えることになる。
[1] 吉海直人『「いろはかるた」の世界』、新典社、平成二十二年、四一頁。