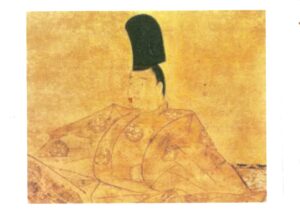村井の書を読むと、『名月記』から見えてくる、定家の長男光家(みついえ)への冷遇、迫害と、後妻との間に生まれた為家(ためいえ)への溺愛が通奏低音のように流れている。よく家庭内のドメスティックバイオレンスの父親を見て育った子どもは長じて自分でも同じようなDVを繰り返すと言われるが、為家もまた父定家の示した実子の間でのえこひいき、偏愛を再現するかのように、家督は長子の爲氏(ためうじ)に残したものの、後妻の阿仏尼(あぶつに)とその子、三男の冷泉為相(ためすけ)を溺愛し、所領の一部とあまたの「歌書」「歌学書」を、阿仏尼を経由して冷泉家を創家した為相に渡し、子孫間での紛争の種を蒔いてしまった。二條家を構えた爲氏と、冷泉家を創設した為相及びその母親の阿仏尼との争いは熾烈で、所領争いは鎌倉に下向しての訴訟にまでなった。その席で、冷泉家側が、家督を継いだはずの二條家に対して、「爲世(ためよ・爲氏の息)卿ニ文書傳ハルニ不ラズ口傳受ケルニ不ラズ」と、「家記」の『明月記』も、あまたの「歌書」「歌学書」「史資料」も相続しておらず、為家からの「口伝」も受けていないので、宗家である資格はないとまで罵倒した争いの根深さはすさまじいものである。

そしてその後、南北朝の対立時に南朝方に付いた二條家は勢いを失い、室町時代には直系の血統を失い、傍流の家系の者が中心になるほどに零落したが、その後、三條西家、中院家、細川家などに支えられて盛り返し、朝廷に浸透することができた。その過程で二條流は『百人一首』を重要視して、定家の残した「歌群」、のちの名前では『小倉山庄色紙和歌』を工夫して、歌順も、歌人名もあり、「後鳥羽院」、「順徳院」の和歌も加えられた歌集『小倉百人一首』として世に出すとともに、「古今伝授」と並ぶ「百人一首伝授」を創設して天皇が自ら口述する「御所伝授」を秘儀化し、朝廷内外で指導権を確保して、今日の『百人一首』文化の基礎を作った。
他方、為家から歌道の資産を受け継いだ冷泉家は、南北朝の対立時には北朝方につき、その後も諸々の歌書、歌学書、諸資料を門外不出の聖典として秘蔵して伝えた。それは、あまたの乱世、戦乱、天変地異を潜り抜けて京都の冷泉家屋敷内の「時雨亭文庫」に保存され、明治維新時には御所の留守居を命じられたので東京移転に追従することなく、それによってその後の関東大震災、第二次大戦時の東京空襲の焼失被害も免れて、今日、数多くの国宝を含む日本歌道史の最重要な史料群として伝わるとともに、冷泉家の歌道の宗家、家元としての信望の基礎となっている。そして、その中に、『百人秀歌』もあれば、『百人一首』もあったのである。
『百人一首』という歌集の成立については、私の感じた多くの謎は解明されていない。そこで、ある種、開き直って、この歌集が何であるのかの探求をいったん中止して、これが何でないかを考えてみた。次のように考えられる。
1.まず、これは和歌史の全体を理解する概説的な歌集であるか。『百人一首』には、『萬葉集』に始まり、『古今和歌集』以降の勅撰和歌集、『八代集』の各巻からの和歌が万遍なく収録されている。これを読めば、この時期までの日本の和歌史を一通り見たことになる。御子左家の書庫には、こうした歌集の写本は満ちていたのであるから、定家にはそれを作成することは可能であった。だが、定家による撰歌を辿ると各歌集の代表的な名歌を選んだとは思い難いし、定家には、後世に改作されているものについて、ある時は改作後の表記のものを採用し、ある時は改作以前の元歌の方を採録するなど一貫性を欠き、歴史を正確に編むという意図は感じられない。『百人一首』は和歌の歴史を示す歌集ではない。
2.次に、この歌集はなぜ百人の歌人なのか。百人と言う数は、『百人一首』が日本和歌史上の代表的な歌集と考えられるようになって人口に膾炙(かいしゃ)したのちにはごく当たり前に考えられるが、「百選」のような発想はむしろ後代のものであり、和歌集を編む際には、百人の歌人、百首の和歌、百と言う数を区切りにするのが良いと考えるのは、むしろ『百人一首』という先例の影響と考えられる。これ以前から「百首歌」と言う観念があったことはすでに見たところであるが、それは一人の歌人が百首の和歌を詠んで自分で歌集に編むというものであり、百人の歌人の和歌を各人からわずか一首だけ編者が勝手に選ぶと言う考え方とは相当に距離が離れている。それはさておき、定家が和歌の名手を百人選んだとは思いにくい。常識的に考えて当然に入選されるべき人が多く抜け落ちており、逆に、評価の定まらなかった凡歌の作者が入っており、中にはここに採録されて初めて和歌史に名前が浮上した無名の歌人さえある。『百人一首』は百人のベストメンバーの和歌集ではないし、和歌史上の代表的な名歌の詞華集、アンソロジーでもない。
3.『百人一首』は、標準的な和歌集のように、和歌をテーマ別に集めたものではない。そこには標準的な和歌集に見られる「春の部」、「夏の部」、「恋の部」、「旅の部」と言うような編成もない。あるのは、おおざっぱな年代順の整理であり、それも、冷泉流と二條流で二通りの異なった順序のものが伝承されていて、定家が慎重に年代順を考えて選んだとも思えない。これを、冷泉流のもののほうが定家の作成したオリジナルな「歌群」に近く、二條流のものは、室町時代中期にこの歌集を再発見した際に加工に失敗した痕跡であると理解できないことはないが、根拠となる史資料に欠ける推測に留まる。いずれにせよ、ごくおおざっぱな編成の仕方であり、歌集の在り方としては違和感が残る。『百人一首』は主題を展開する歌集ではない。
一体、これはどういうことであろうか。定家の選んだ「歌群」は、王朝和歌史のダイジェスト版ではない。王朝の優れた歌人百人の顔見世でもない。王朝の和歌の名歌中の名歌をえりすぐった名歌集でもない。第一、「歌群」には明確な主題別の編成もない。これはいったい何であるのか。『百人一首』は、それがどういう歌集であるのかという問いに答えることは困難であるが、どういう歌集ではないかという問いには容易に答えが見えてくる。そしてそうした答えを積み重ねてみると、そこに全く別の姿が見えてくる。これをまず結論的にいえば、『百人一首』は「歌集」と言うよりも御子左家の「家歌書」、つまり「歌の家」「歌家」の奥義を伝える教材の「歌群」ではないのか、と言うものである。
ここでもう一度、定家による、「百人一首伝授」の様子を想像してみたい。定家の眼前には為家一人が座り、余人は皆遠ざけられている。公家の家らしく、定家はまず、皇室との関わり方を口述したであろう。それは大きく二点に分かれる。第一は、「後鳥羽院」、「順徳院」とその関係者の扱いである。「後鳥羽院」は、承久の乱で敗北して、乱の首謀者であったのに、北条義時討伐の試みは臣下の勝手な振舞であって自分はあずかり知らないとみっともない弁解をして免罪を乞い、死罪あるいは病死を装う毒殺を免れて流罪に処せられたのであり、生前の京都帰還は許されず、歿後も不名誉な扱いを受けたのであって、そこに一片の敬意も憐憫も示してはならないのが、もともと「後鳥羽院」の寵愛を受けていた御子左家が公家社会で生き残る戦略の基本であった。定家は、「後鳥羽院」、「順徳院」親子の無視に加えて、「後鳥羽院」朝の女房、「俊成卿女」や「宮内卿」に至るまで、関係の深い歌人たちを黙殺するべきことを教えたのであろう。なお、為家は「順徳院」に天皇在位の当時から気に入られて寵愛を受けており、佐渡への配流の際にも同行を求められたがそれを辞退して京都に残り、親鎌倉幕府の新朝廷に仕えて活躍して勅撰和歌集の選者に選ばれており、「後鳥羽上皇」一派を完全に切り捨てて親鎌倉幕府の旗幟を鮮明にするという乱後の御子左家の政治スタンスは確かに受け継がれていた。
もう一点は、王朝の歴史の中で問題のあった天皇たちの扱いである。「崇徳院」は優れた歌人であり、崇徳歌壇の中心であったが、保元の乱で敗北して讃岐に流され、京都への帰還を願って果たせず、怨念を抱いて寂しく流刑地で没した天皇である。京都にいた頃には「新院」と呼ばれていたが、讃岐に流された後は廃帝であって院号も与えられずに「讃岐院」という通称で呼ばれていた。「崇徳院」の生涯を語る定家の教えは、当然だが、いかに和歌の道に優れた帝であっても接触には十分に注意せよというものであったことだろう。
繰り返し説明してきたように、『百人一首』は御子左家の秘伝であり、定家が息子の為家に歌道の奥義を口述で伝える際の教材であったと思われる。後世、二條流の血筋で唱えられた同家に伝わる伝説の「百人一首伝授」が、まったくの後世の偽作、創造物ではなく、内容は途絶して理解できないが、定家が一子相伝の秘伝の口述を為家にしたという史実を反映していたとするならば、その失われた秘伝とは何だったのだろうか。定家は、「陽成院」、「河原左大臣」、「光孝天皇」と言う、歌人としての評価が必ずしも高くなかった人たちを並べて、何を教えようとしていたのだろうか。定家は、当然、この並びの説明では、妖雲が漂ったと言われる時期の皇室の異変に触れ、中級の公家の家としての皇室との細心、慎重な関係の確保を説き、歌学の人としては、これらの歌人の和歌を鑑賞、解説する際にこういう背景事実にも気を配るよう説いたのであろう。そのためであれば、「陽成天皇」、「河原左大臣」(源融)、「光孝天皇」と直截に事変関係者の歌を並べた不気味に暗い編集の意図も理解できる。
残るのは「三條院」と「崇徳院」である。「崇徳院」についてはすでに述べた。「三條院」は即位時三十六歳、在位五年で病を得て退位し、眼病で失明したうえで死去した。いずれも悲運の天皇である。こうして見ると、『百人一首』に収められた天皇は、神のような「天智天皇」、「持統天皇」は別にして、収録された平安朝以降の天皇は、いずれも悲運の帝であり、宮廷歌人の家としては、取扱注意の者である。こういう天皇を選んでいる定家には、「伝授」の口伝を通じて、歌人としての天皇についてだけでなく、皇室の怪しげな歴史をリアルに伝え、そこに仕える際の心構えについても教示するとともに、これらの問題のある帝の和歌の解釈に際しての特別の留意点も示しているであろう。こういう面で取り扱いに注意が必要な天皇を選んでいるように思えてならない。歌人としてはもっと優れた実績を残している天皇もほかに多いのに、そこを外してこれらの悲運の帝たちを取り上げた趣旨はこの辺にあったのではないかと思うのである。
次に、この「歌群」を見ていると、皇室への忖度の他に、なお二点の忖度、配慮が感じられる。一つは、公家社会内部のことで、定家は主筋に当たる九條家に縁の深い人々を多く取り上げている。定家は生涯九條家の家司(けいし)を務めたのであり、この主筋の力添えがあってこそ初めて御子左家は公家社会の中で栄達が可能であったのであるから、そこを忖度して重視するのは当たり前であろう。そしてさらに、定家は、親鎌倉幕府の公家らしく、鎌倉武士の歌人、和歌も積極的に採用している。「鎌倉右大臣」、源実朝はその代表であろう。ここにも定家の自分の立ち位置からする権力者への追従、忖度がある。
堀田善衛は、元久二(一二〇五)年に、定家が、当時京都で厳格な守秘の下で編纂の作業が進行していた『新古今和歌集』の草案の内容について、弟子の鎌倉武士内藤朝親を介して源実朝に漏洩した疑惑を指摘している。²⁷これは、自ら先頭に立って歌集の切継ぎを行っている後鳥羽院への極めて深刻な裏切り行為であるが、『明月記』では一切言及されていない「秘事」であり、『吾妻鏡』の記述から始めて暴露されている。堀田はここで、定家嫌いの折口信夫が書いた「此流の者は、皇族を大檀那とする事によつて歌道の正統なる事を示し、中央、地方の武家階級の信用を固めて、私福を獲ようとするまでになつた。定家が既にさうであり、其子、孫皆、其方便に従うた」という言葉を引用し、さらに、「かかる私事あるいは秘事を書き記さない定家という人間をもしかと認識しておかなければならないであろう」と定家に冷ややかに記述している。実際に、定家は、幕府の要人との人脈を活かして、御子左家の荘園での収益を現地で管理している武士たちが横領する悪習を防止して、家計の好転を果たしている。権力者への忖度は実益を生んでいたのであり、折口、堀田の酷評は当たっている。
こうしてみれば、問題なのは「百人一首伝授」の中身、口伝の内容である。百首の和歌は、観賞するべき名歌ではなく、改善の余地のある素材である。定家は、為家に口述で伝授する機会ごとに、そこで取り上げた個々の和歌について、歌と作者に関して社交辞令を排除したリアルな解説を述べるとともに、本歌取、縁語、懸詞、枕詞などなどの作歌の技巧も教示して、その和歌を「直してみよ」と迫ったであろうと思われる。そして為家の改作が意に添うたならば、良く気付いたと褒めたであろうし、意に添わないときは、それは違う、先日教えたところを忘却したか、と厳しい叱責が飛んだことであろう。
こうして、私は、和歌の道に暗い素人であるが、私なりの一応の理解にたどり着いた。そこでは、まず、昭和末期に「百人一首歌かるた」の蒐集とその歴史の研究から見えてきた、『百人一首』には冷泉流と二條流の二流があるという発見がある。これは、その後、「時雨亭文庫」の公開が進むなどの研究条件の改善によって、数本の『百人秀歌』が発見されたことで裏付けられて、今では否定しがたい指摘になっていると思う。
次に、私は、『百人一首』との接触を繰り返した中で感じた、この「歌集」は不完全であるという感想を放棄することなく、様々な論点からの検討を重ねて、それが「歌集」としては不可解のものであり、未完成な「歌群」であるという認識に達した。ここで最も私の発想を刺激されたのは塚本邦雄の仕事である。塚本は、『百人一首』を完成した「歌集」と前提したうえで、それがいかに不満足な、不本意な「歌集」であるかを批判して、「私自身の目で八代集、六家集、歌仙集、諸家集、あるいは歌合集を隈(くま)なく經(へ)巡(めぐ)つて、それぞれの歌人の最高作と思はれるものを選び直し、これを百首に再選して『王朝百首』と名づけてみた」²⁸と述べるように、歌人の選抜からやり直した「歌集」を構想した。そして、次に果たしたのが、「『王朝百首』に先立つ時代の作、これに續く近世の詞華の發掘と顯彰」²⁹であり、それは、日本の和歌史を縦断する齊明天皇から始まって森鷗外に及ぶ『珠玉百歌仙』に結実した。さらに塚本は、今度は『百人一首』の歌人百人の和歌を各個人ごとに全面的に再検討して、各人の代表歌を数首選び出して、その中から最も代表的な歌一首を切り出す作業を進め、定家の枠組みの中での選歌の優劣を定家編の『百人一首』と競った。「ともあれ、百首、撰の不當と缺陷を論じてゐるだけでは不毛であらう。そしてまた假に百首が必ずしも凡作ではないとしたところで、その一人一人に、他に、これこそ代表作、一代の絶唱と目(もく)すべき歌が、現に殆どある。例外は「沖の石の讃岐」くらゐだらう。また、百人一首歌以外にその作の傳はらぬ安倍仲麿と陽成院は、選擇の餘地がない。それを考慮に入れ、その制限にやむなく從つて、この度私は、九十八人の、これこそかけがへのない一首を撰び上げた」³⁰ということである。『百人一首』を歌集と見た場合、それの最も徹底した解読、評価、批判はこの塚本の、一生を懸けた仕事に尽きると思う。だが、塚本は真正直すぎる。ひねくれ者の私には、これだけの塚本の業績に接してもなお、『百人一首』は「歌集」というより教材の「歌群」ではないかと言う疑念は消えないのである。
ここで大きく振り返れば、定家は、承久二(一二二〇)年に後鳥羽院の勅勘を受け、翌承久三(一二二一)年に承久の乱が起きた頃には写本に集中しており、その後も写経、写本を繰り返した。身近な人々の相次ぐ逝去に加えて、承久の乱で敗北して処刑された多くの公家や旧知の人々への鎮魂の思いもあったのであろう。この活動は寛喜年間(一二二九~三二)まで十年、定家の年齢で言えば六十歳から七十歳の十年間続き、膨大な量の成果が生まれた。この情報群を保有することが、歌道の本家、家元の権威の証しであり、定家は、あまたの和歌集にとどまることなく、作中に物語歌を含む『源氏物語』などの物語の写本にも熱心であり、その成果である「時雨亭文庫」は、八百年後の今日に至ってもなお、冷泉家の権威を支えるとともに、王朝文化の時代の文芸史をあらわにする日本国内最良の史料群となっている。
だが、その一方で、定家の作歌活動は低調であった。定家は「〈詠む人〉から〈写す人〉に変貌していった」³¹のである。そして、定家七十一歳の貞永元(一二三二)年に後堀河天皇から『新勅撰和歌集』の撰進を下命されて果たしつつあったが、翌年に後堀河院の中宮、藻壁門院が死産で母子ともに死亡し、定家は出家して「明静」と名乗り、その翌年の天福二年(一二三四)に後堀河院本人も死去するという大事続出であった。定家は作成中の和歌集の草稿を焼き捨ててしまった。その時の定家の心境は想像するより方法がないが、 後堀河院は、鎌倉幕府の勢いが強く、朝廷は恐怖に慄(おのの)いていた中で、まだしも、定家を理解してくれていた数少ない人であったのに、その支柱を失った定家が選歌した『新勅撰和歌集』を奉呈しても退けられる恐れがあり、逆心を秘めた歌集を作成したという非難を浴びることを恐れたのではなかろうか。実際、定家の主筋で庇護者の九條道家、道実父子はこの歌集を編集しなおして、後鳥羽院一派の和歌を排除して鎌倉方の和歌を多く採択しなおして完成させ、定家に仮名序を書かせて形を整えて奉呈した。これでかろうじて定家の名前は生き残ることができた。これが七十三歳の時である。定家はその翌年、七十四歳の年に『百人秀歌』を選んだとされているが、こういう経過を見ると、この時期の定家に、歌人としての制作欲、和歌の美を極める「歌集」、とくに名歌撰を編もうという意欲が残されていたとは思えない。実際、残されている『百人秀歌』の巻末には定家の識語があり、そこでは名歌を選んではいないのだからあれこれ言わないで欲しいという弁解が書かれており、百人の名歌を集めた「秀歌」という題名はこれと食い違っている。歌人の数も「百人」ではなく「百一人」である。私には、『百人秀歌』という題名は、後世に写本を残した人が付けた、定家の意図を勘違いした題名だとしか思えない。そして、晩年の定家としては、今なお蹴鞠の遊技を好んで熱中する息子の為家に心を痛め、何とか歌道の本家、家元としての体面が維持できるように秘伝を伝えようする老いたる父親のひたすらな気持ちしか見えてこない。そして、頼綱への「色紙形」の贈呈から六年後に定家は死去した。この短い期間に、『百人秀歌』の基になった「歌群」を再検討して『百人一首』の様に変則的な歌集を完成させたとは考えにくいのである。
『百人一首』は定家によって着想され、その子為家らによって完成された「歌集」であるという前提を排除して、歌道の本家に伝わるべき教材の「歌群」であると考えると、不自然な歌人の選択、奇妙な歌順、凡歌の集積、表記の基準の不統一、「後鳥羽院」、「順徳院」の和歌の出し入れなど、この「歌群」にまつわる「歌集」としての不備の多くは、そもそも「歌集」を目標に編まれてはいないのだから解決のしようがないという点に落ち着く。私の到達点は「幽霊の正体見たり枯れ尾花」であった。そして、本来は不即不離で一体化していたはずの定家の口伝、一子相伝の秘儀が失われてしまった以上、この百首の和歌教材の活用の仕方は分かりようもない。ただ、揣摩臆測(しまおくそく)の種になるだけである。
さて、ここまで、『百人一首』という歌集の誕生に関する「かるた」史研究者の私からの見解を述べてきた。だいぶ複雑なので、ここで最後に、その見解の要点を整理してまとめておこうと思う。『百人一首』の誕生は、次の十の段階を経ているのではなかろうか。
第一に、そもそもの始まりは、定家が歌学の殿堂、御子左家を相続させる息子の為家に行った、一子相伝の奥義の伝授とそこで教材として用いる「歌群」の作成にあると思われる。この「歌群」は採用された和歌の数も百首以上ということで百数十首なのか、二百首を越えるのかも定かではなく、この「歌群」の題名の有無も分からない。第二に、この「歌群」の存在は定家の息子、藤原為家の舅、宇都宮頼綱の知るところとなり、頼綱の求めで、邸宅の障子(襖)に貼るべく色紙の形で定家から頼綱に贈られた。その際の題目は、『明月記』によれば「嵯峨中院障子色紙形」であった。「嵯峨中院」は頼綱の邸宅の名称である。第三は、為家が、定家と頼綱の双方から遺産の相続を受け、二軒の邸宅を併合して「嵯峨山庄(荘)」と呼称した時期である。為家の手元には、頼綱の邸宅にあったであろう定家自筆の和歌色紙数十枚と、定家の邸宅にあったそれの控えの巻子、『嵯峨山荘障子色紙形』の双方が集まったと考えられる。そして為家は、これが御子左家からすれば弟子筋の岳父からの相続であるよりは、歌道の家の当主、「歌群」の編者で実父の定家からの直接の相続であることを示したかったのか、「嵯峨中院」という頼綱寄りの名称を嫌って「嵯峨山荘」を使い、また、定家からの相続品は邸宅内に張り巡らせた物ではなかったので「障子」も削ったのであろう。なお、この段階で、為家が歌集としての形を整えたという伝承が今日まで残っている。ただし、この巻子には残存例がなく、収録された和歌の数、内容なども明確には分かっていない。ただ、いずれにせよ、この段階で、「歌群」は「歌集」らしく編集しなおされたと思われる。
第四の段階以降は冷泉家が主役である。冷泉家の始祖、冷泉為相は、生母の阿仏尼ともどもに実父為家の寵愛を受け、定家に由来する歌道の基本的な資産をほぼすべて相続した。冷泉家では、『嵯峨山荘色紙形』は御子左家の歌道をつたえる奥義の書として秘蔵され、百一首の和歌を載せた巻子も作られて、ある段階で兄の京極為教に貸し出され、秘蔵に固執しなかった京極家の筋から、『嵯峨山庄(荘)色紙形、京極黄門撰』という題名のものが公にされて多少広まった。一方冷泉家では、幾度か写本が作成され、その中の一冊には新たに『百人秀歌』という題名が付けられた。実際には百一人であったが。これが第五段階である。第六段階は、鎌倉時代末期から南北朝期にかけて、斜陽だった二條流を復興させた頓阿の時代であり、ここに、百人で百首の形が決まり、また、『百人一首』という題名も定まった。第七段階は冷泉家の側で、室町時代に、二條流の『百人一首』に対抗したいのだが、『百人秀歌』の封印を解いて公開することもでき兼ねるので、それを基に、二條流の『百人一首』に似せた冷泉版の『百人一首』が考案された。これが鎌倉時代後期から南北朝期にかけての時期における『百人一首』の成長の跡である。
第八段階は、安土桃山時代、江戸時代初期の頃で、社会的には冷泉版の『百人一首』が盛んに用いられたが、宮中では細川幽斎らの働きかけで二條流の表記のものが用いられた。そして、第九段階は、京都の御所で後水尾天皇自身が「百人一首伝授」を行うなど、ここを拠点とした二條流の攻勢が強まり、ついに、元禄年間に二條流が冷泉流を凌駕(りょうが)して用いられるようになり、今日まで続く標準型の『百人一首』の時代になった。なお、この江戸初期から前期にかけて、『百人一首』を遊具に用いる「かるた」遊びが京都の遊郭から始まって次第に市中にひろがり、この「歌集」の普及には大いに役立った。そして第十段階は、元禄年間以降のことで、冷泉流の表記の「かるた」札を二條流の表記のものが上回り、歌人の画像でも京都の土佐派のものよりは江戸狩野派のものの方が評判が高まり、今日まで続く「小倉百人一首歌かるた」の時代が始まった。私は、このことをもって歌集『百人一首』と「百人一首歌かるた」が、誕生期からの卒業を果たしたと考えている。
もし、室町時代中期に、二條流の流れの人々が、宗家復興のために『百人一首』と言う歌集を発掘して加工の上で公表しなければ、そこに、「百人一首伝授」と言う儀式を復興して、代々の当主が免許を付与し続ける本家、家元の地位を構築しなければ、あるいは三條西家、中院家、細川家などによって宮中に持ち込まれ、天皇自身が「御所伝授」を行うという権威付けに活用されなければ、そしてもう一つ、もし「かるた」という遊技が海外から伝来していなければ、この「歌群」はこれほど有名にならず、もっと穏やかな歴史を刻み続けることができたであろう。正岡子規も、折口信夫も、塚本邦雄も、もっと穏やかにこれに接することができたであろう。
村井康彦は、『藤原定家「明月記」の世界』をこの文章で閉じている。「最晩年の『明月記』には「金吾」(為家)の文字ばかりが目につき、為家が来宅――時には一日に二度も――するのを何よりも楽しみにしている様子が窺われる。為家が来ないと「世事聞かず」とぼやく日々であった」。これで村井による一冊の挑戦的な書物の著述が終わっている。このなんともぶっきらぼうなエンドロールを私風に脚色するとこうなる。「最晩年の定家は、山荘の居室に張り巡らした自筆の和歌色紙を眺め、過ぎ去った年月を思い、多くの歌人との競争と交流の日々を思い、後鳥羽院との格闘の日々を思い、一つ対応を誤れば御子左家の廃絶になった承久の乱を何とかしのぎ切った経緯を思い、そして、この乱の後に、親幕府の新皇室のために後鳥羽院とその一味を削除した和歌の道を創出し、御子左家にそうした歌道の本家、家元の地位を残し、為家にその地位を維持し得る秘儀を口述で伝授しえたことを思い、中級の公家の家を守り抜いた満足感、そうした自分を褒めながらまどろむ日々であった」。
²⁹ 堀田善衛『定家明月記私抄』新潮社、昭和六十一年、二一五頁。
³⁰ 塚本邦雄『王朝百首』講談社文芸文庫、平成二十一年、一九頁。
³¹ 塚本邦雄『珠玉百歌仙』講談社文芸文庫、平成二十七年、一五頁。
³² 塚本邦雄『新撰小倉百人一首』講談社文芸文庫、平成二十八年、一九頁。
³³ 高野公彦『明月記を読む 定家の歌とともに 下』、一八六頁。