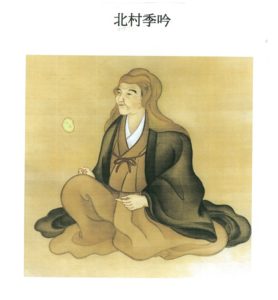天明二年(1782)に市場通笑作、鳥居清長画の『花の春上手談義』(研究室の表記では単純に『上手談義』)が出版されている。内容は善心坊という僧が説話をして「思ひのほかの大入」になったが、最後に不始末をして「百日の説法屁一つ」で終わるという笑い話を挿画付きで面白く展開するものであるが、後半部分にカルタの意義をこじつける説明文と遊技場面の図像がある。
この史料をカルタ史の史料として最初に活用したのは江戸カルタ研究室だと思う。私がこれを初めて見たのは研究室のサイトの「カルタ資料展示室」であった。この例を含めて、私は、研究室が多くの図像史料を丹念に発掘して提示した業績を高く評価している。ただ残念なことに、個々の図像の理解、評価については問題がある。何よりも、研究室は「めくり」「読み」「かぶ」等の遊技法別に整理して展示しているが、そこに「合せ」、あるいは研究室の用語でいえば「元技法」の類型がない。その結果、「合せ」の遊技図は行き場所を失って妙なところに置かれることになった。もう一つの問題は、遊技の種類の見誤りである。「読み」を「めくり」と見誤る。「合せ」を「読み」と見誤る。研究室による『花の春上手談義』の理解にはこのタイプの誤りがある。これは、絵画史料を見る際の基準の問題であるので、どういう基準で観察し、判断するのが学術として妥当であるのか。参考までに私の判断基準を提示しておこう。
まずこの図像であるが、男三人、女一人の合計四人で遊技している。私は、江戸時代のかるた遊技図を見る際には、①その史料が成立した時期によって大まかな判断をした上で、②参加者の数が三人描かれていれば「めくり」の遊技である可能性が高く、四、五人だと、「読み」「合せ」等の可能性が高いと考える。このほかに「かぶ」系の遊技では人数は不定である。次に、③参加者の持つ手札がほぼ同数に描かれていれば「合せ」の可能性が高く、手札の枚数に差があり、特に一枚を握りしめている者がいるような場合は「読み」の、それももう一枚出せれば上れる終盤戦の可能性が高い。次に、④参加者の膝周りに裏面を上にした取札が積まれて描かれていればそれはトリックであるから「合せ」を描いた可能性が高く、膝周りの取札が表面を上にして広げられていれば「めくり」の可能性が高い。「読み」の場合は札を得るということがないので膝周りには札は描かれないし、もしそれが描かれていれば決して「読み」ではない。例えば、研究室が「カルタ資料展示室」で扱った『御伽新二重謎』であるが、研究室は「よみ」の遊技場面であるとしている。だが、三人の遊技者のいずれの膝周りにも裏面を上にしたカルタ札の塊が描かれており、これは獲得したトリックの札であり、私には「読み」には見えない。これは「合せ」であるが、そもそもこの「カルタ資料展示室」では「合せ」という遊技法の類型が否定されているのであるから、こうしてありえない「読み」の類型の中に置かれることになるのである。
図像史料の識別法に戻ろう。次に、⑤場に裏面を上にした山札が積まれて描かれている場合は「めくり」である。「読み」も「合せ」もすべての札を参加者に配分してから始められる遊技であるから、山札というものはあり得ない。そして最後に、⑥場に展開されている札の数であるが、「めくり」は場札であるから多い時も少ない時もある。「読み」の場合も枚数不定であるが、「読み」の場の雰囲気を出そうとして多くの札が場に投じられた場面を描く例が多い。普通は、参加者の人数よりも場に広げられている札の数が多ければ「読み」の遊技場面と判断される。これと対照的に、「合せ」の遊技場面では人数を超える数に描かれることはない。原理的にあり得ない。
私は、カルタ遊技の図像を見るときは、こういういくつかのポイントでどの遊技法を描いているのかを判断している。ただし、これは画家がカルタ遊技場面をリアルに描いたときの話で、そうではなく、カルタ遊技に通じていないのに手本の絵を適当に写したような場合は、どういう遊技の場面であるのか、描写が矛盾していて判読不能になる。なお、⑦版本の場合は、文章内容を示す挿画であるから、本文の記述も参考になるが、こうした周辺的な文字情報に頼りすぎる危険性についてはすでに『繪本池の蛙』で具体例を扱った際に述べた。
そこで『花の春上手談義』に戻ろう。研究室はこれを「めくり」遊技の図だと説明する。研究室は、私と違って、本文での記述が図像を説明しているので「文字通り」に理解することを大事にしているので、その流儀で図像上部の本文を読んでみよう。すると、右から二行目に「三百年もさきによみといふものがはやり」と書いてあって、以下は善心坊による、カルタがいかに道理に適っているのかというこじつけの説話になる。最後は「だんぢうろう」(團十郎)という役と「てら」(テラ銭=場所代)をもじっている。だが、ここでは最初から最後まで「読み」が扱われていて、「めくり」については全く触れられていない。研究室がこの頁の文章を読んで、どうしてこの図像が一言も言及されていない「めくり」の遊技場面だと「文字通り」に判断したのか、「文字通り」を大事にする判断基準がどう機能しているのかが全く分からない。どうも、新史料の発見に気分が昂揚して、文書成立の時期からしてこれは「めくり」の遊技図だという思い込みが先にできていて、文章も良く理解できないままで、絵画そのものを先入観なしに見ることができていないように思われる。
そこで、私の流儀で、図像そのものを虚心に見てみよう。参加者は四人で、手札は各々五、六枚持っている。場には四枚の札がある。山札も各人の取札も描かれていないから「めくり」ではない。「読み」か「合せ」ということになるが、人数分の札が場に出ているのに誰もそれを取りに行っていないのでトリックを取り合う「合せ」の可能性は低く、逆に、左端の喫煙している男がもう一枚、五枚目の札を出そうとしているので「読み」の可能性が高い。左端の男のセリフ「八のあたり」、右の男のセリフ「ないない」も「読み」の遊技らしい。
以上であるので、これは「めくり」の遊技図ではなく、「読み」の遊技図だと判断される。この本が出版されたのは天明二年(1782)、江戸では「めくりカルタ」の全盛期であるが、そういう一般知識で図像を理解してはいけない。この絵の場合は、同頁の本文をきちんと読めば「読み」カルタを説明しており、鳥居清長も「読み」カルタの遊技場面を描いているだけの話である。これをもって「めくりカルタ」の遊技場面の描写例とすることはできない。



-300x224.jpg)