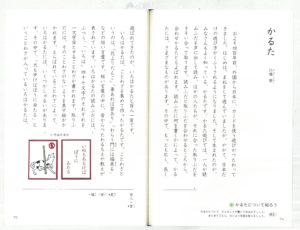もう一つ、近代の日本での「百人一首かるた」というと見過ごせないのが、明治二十年代(1887~96)以降に、もっぱら子どもを対象にして「教育玩具百人一首」などと名付けられた粗略なカルタが制作、販売されるようになったことである[1]。それは新時代の西洋紙、機械印刷技術を活用したもので、当初は草書体のものであったが、後に活字印刷のものになり、収納箱もボール紙を使って鋲止めされるだけの安価な製法で、「教育玩具」として大量生産され、広く販売された。
もともと、和歌のかるたは、大人も子どもも入り混じって遊ぶ家庭遊戯の典型であったが、この時期に、大人抜きでもっぱら子どもが遊ぶ「子供手遊美術百人一首」という一回り小ぶりの百人一首かるたが現れたのである。これは、百人一首かるたの歴史の上では特筆すべき事件であった。それまで、雛飾り用のミニチュアを別すれば、子ども用の小ぶりの百人一首かるたは制作されることがなかったからである。
いうならば、明治二十年代(1887~96)は、百人一首かるたの遊び手としての子どもが発見された時期なのである。百人一首の書が学校で教える書道の題材になる。百人一首かるたは国語の教材である以上に美術科の教材とされたのである。書道手本であるから、これは当然に崩し字のかるたである。明治二十年代(1887~96)は、書道教育に対応した子ども専用の教育百人一首の登場期といってよい。
従来の百人一首かるた研究では、この時期における子ども用の、崩し字の百人一首かるたの考案というポイントは、まったく眼中になかったようである。確かに、一見すれば、この時期の子ども用の「百人一首かるた」は、大人が用いるものと比較すれば安価で粗末な造りであり、あえてそういうレベルのものを制作して商品化した趣旨への理解がなければ容易に見逃してしまうであろう。百人一首かるた史の研究者は、近代教育史と関連する子ども用の百人一首かるたに注目することはなく、それを分析する視点も持たないままであって、子ども用の百人一首かるたが眼前にあってもそれの存在意義に気づかずに見逃してしまう。そのために子ども用の百人一首かるたに関するデータは少なく、未整理の状態であって、時たま現れる展覧会や雑誌の特集号などでも無視されている。
そうした中で、大牟田市立三池カルタ・歴史資料館はこうしたかるた札の存在に着目して蒐集と研究を進めた。今日では、この資料館に、明治中期(1887~1902)、後期(1903~12)の子ども用百人一首かるたのコレクションを見ることができる。だが、史料がなお不足しており、子ども用の百人一首かるたの第一号と特定できるものがないなど、より豊かな実証性を持って説明できていないのが残念である。しかし、大きく見れば、明治二十年代(1887~96)、とくにその後半に、こういう百人一首かるたが成立したと見て間違いはないと思われる。
もう一点、これもまた仮説として指摘しておけば、この、子ども用の百人一首かるたの考案と、読み札に和歌の三十一文字をすべて書くようになった変化とがほぼ同時期に起きていることには注目すべきである。もともと、和歌のかるたは合わせ取る遊びのかるたであり、通常は、上の句札と下の句札に分かたれている。例外は北陸の加賀版百人一首かるたであり、この地方では、江戸時代末期(1854~67)までに、遊び手の便宜を考えて、読み札に、上の句だけでなく下の句も書き添えたかるた札を使用する習慣があった。そうした北陸のかるたの地域的な特徴が、大阪の木版百人一首かるた絵にも影響し、さらに明治二十年代(1887~96)までに全国化したのである。だが、なぜこの時期にこうした変化が起きたのか。これはいまだにきちんと研究もされていないし、単に指摘されたこともない。私は、百人一首かるたの表記の変化は、そこに登場する百首の和歌への理解、記憶のレベルが低下したことに由来するのではないかと推測している。つまり、従来は、読み手が上の句の札を読んだときに取り手が札を取ることができなかった場合は、読み手は、記憶している下の句を唄い上げたのであるが、時代が下がるにつれてその理解の程度が低下し、下の句を十分に記憶していないので誤って発声したり、「下の句は何だっけ」と告白して遊技の緊張感を一気に失わせたりするので、そういう事態を避けるために、記憶が不十分でも読み手が務まるように和歌の全文が読み札に登場したのであろう。寺子屋教育が学校教育に変化し、読み書きの教材から「百人一首」が消えたのに応じて、子どもたちの理解も低下していったと思われる。
なお、子ども用の百人一首かるたの成立は、明治後期(1903~12)以降に、子ども用の雑誌の付録としての和歌のかるたという新しいジャンルを成立させる。『女學世界』などが発行した未裁断の歌かるたのシートは、今日でも数多く残されている。中には、読者の家族が仕立てたのであろうか。美麗なかるた状になっているものも発見されている。そして、これが多数残されているということは、それが実際には読者の子どもたちによって遊技に使われることが少なかったことを意味する。子ども用の「百人一首かるた」は、明治中期(1887~96)に児童遊具として登場し、間もなく衰退していったのである。
「百人一首かるた」では、明治三十年代(1897~1906)後半に、洋紙を使い、活字を印刷し、紙箱に収納した「競技かるた」が登場した。これによる「百人一首かるた」の復興には目覚しいものがあり、明治後期(1903~12)末期から昭和前期(1926~45)にかけては、大人用の豪華なかるた、カチッとした競技かるた・公定かるた、そして子ども用の安価だがかわいらしいかるたの三種が並存した。昭和前期(1926~45)には、戦地の兵隊への正月の慰問品としての簡略なかるたもできた。この「競技かるた」については以下で扱う。
もうひとつのエピソードは、裏紙が黒と赤の二色に分かたれる明治後期(1903~12)以降の百人一首かるたである。この時代であるから、当然に崩し字のままである。札の作りが堅牢で人気がある。このかるたは、読み札と取り札を識別しやすくする工夫をしているのだといえばそうなるが、実際は、百人一首かるたの需要が急増すると、その製造に花札を制作するカルタ屋が参入し、その際に、花札の赤裏、黒裏の二種類の裏紙を活用して仕立てたという事情である。花札作りの職人と百人一首作りの職人とでは制作の手順が多少違っていて、特に縁返し(へりかえし)の順序では、花札作りでは上下に角を出すのに対して百人一首作りは「回し貼り」で角を出さない。だから、裏が赤、黒で、札の四隅に角が出ていると、「お里が知れる」と笑われたそうである。
しかし、いずれにせよ、和歌が子どもの教育で活用された江戸時代の伝統は途切れてしまった。もともと日本という国は、列島の内部に敵対する国家を持たないという稀有な幸運の星の下にあった。そして、日本列島のうち、どこまでが日本という国の領域で、どこからが「化外の地」であるのかは、明確な国境線があるわけではなく、文化的に、和歌の通用する範囲が日本と考えられていた。和歌には、歌枕という風光明媚な場所、あるいは名物のある場所がある。古い時代の歌集には、その歌枕を詠んだ和歌がある。つまり、歌枕がある名所は、古くから日本であったことになる。そして、後世の歌人たちは、実際にその地を旅して歌枕を発見して古歌の鑑賞を深め、あるいは自身も一首をものしてその伝統を強化する。あるいは「歌人は居ながらにして名所を詠む」で京都に居りながら遠い遠国の歌枕を想像して和歌を詠む。例えば、「末の松山」は東北地方に六か所あるなどと言われる。北へ、北へと日本が蝦夷の地を侵略し、日本人が進出し、その地の支配を確立すると、そこにいかにも「末の松山」らしい風景があり、歌人がそれを和歌にすることでそこは古来歌枕として詠われてきた日本であって蝦夷ではなく、したがって、日本の政権がその地を支配することは侵略ではなく古来の領土の回復であって正当であるとされる。こうして、日本では、和歌が詠まれ、和歌が通じてきた地域が母国の地であると理解されるのであり、この教育効果が和歌の学習に期待され、百人一首を知ることはその入り口になる。百人一首を知れば、そこに現れている世界が日本なのであり、日本の文化であることがぼんやりとしてではあるが理解できる。
こうした和歌を通じた教養教育の効能は、しかし明治年間(1868~1912)の学校教育では失われた。ちなみに、それが再評価され、小学校の国語の指導要領が改定されて国語教科書に百人一首が載るようになったのは、実に一世紀以上も後の平成年間(1989~2019)であった。そこでは和歌の伝統、ことわざの慣習を知ることを通じて日本の文化的な伝統への気づきが促される。そして興味深いのは、最大手の教科書会社が、和歌とことわざを教える具体的な形として、百人一首かるたとイロハかるたを選んだことである。小学生にとっては、和歌やことわざの中身を正確に理解して鑑賞することはまだ困難であり、百人一首かるたで遊ぶことを通じて、五、七、五、七、七という文芸の形、読み上げられるときのしらべを漠然としてではあるが理解し、そこに、江戸時代の寺子屋の児童もそうであったが、勘違いした記憶や怪しげな故事や噂話の聞きかじりなども重なって、漠然と理解される程度であるだろうけれども、それが日本文化の伝統理解への入り口になるのである。これは、明治以来の国家的教育への復古ではなく、江戸時代の寺子屋教育への復古である。珍しい例である。
[1] 江橋崇、「明治二十年代における近代カルタの成立」『人形玩具研究―かたち・あそび―』第十六号、平成十七年、一六七頁。