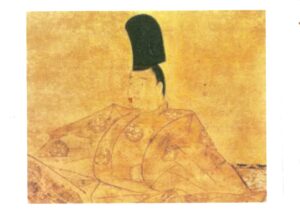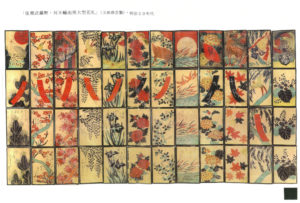『百人一首』の成立の研究に関して私が疑問に思っているのは、従来の国文学者の『百人一首』成立論では、まず、藤原定家という人間が、和歌を家業とする中堅の公家で、父親の藤原俊成の努力によって和歌の道の本家、家元となった御子左家を継承した者として、それを次の世代の後継者、為家に引き継ぐことに生涯、腐心し続けたという事実が軽視されていることである。彼が生涯書き続けた『明月記』も、御子左家が守るべき宮中での所作、儀礼、有職故実を書き連ねた、他家の者に盗み見されないように絶対に秘蔵されるべき「家記」である。それを書き残して、子孫に宮中での作法などを教示するのが、公家の家の家長の勤めであり、『明月記』はそれを生涯実直に果たした成果であった。そしてそこに見えてくるのが、いかにして歌道の家の権威を後継者の為家に師資相承、一子相伝で継承するのかという定家の家長としての課題意識であり、そのための行動である。定家は承久の乱での政治的な挫折と失意の後は、歌人としての創作意欲も減退し、歌論書の執筆が増え、あるいは古典籍の筆写が増えている。いずれも子孫、後継者の為家に相続させることが予定されているものである。『百人一首』の発端は、そういう段階の定家の周辺で起きたことであるのに、そこに、後継者育成という晩年の定家の意思、希望を見ない議論はいただけない。
もう一点は、『百人一首』が、もし定家の作成によるものだとしたら、最晩年ですでに歌人としての意欲も活動も衰えているのに、あたかもその活動に熱心であった若い頃の定家像のままでいることを前提にして制作意図を推察していることである。『百人秀歌』や『百人一首』には、『古今和歌集』以降の平安時代の勅撰和歌集から多くの和歌が採取されている。藤原定家という一私人が、勅撰歌集の和歌を採点して、自撰の和歌集への採否を決めている。それは歌道の主としての皇室の権威よりも自分の歌道を上に置くきわめて不遜、傲慢なものであろう。若い日の定家であれば、こういう不遜、傲慢な所為を避けなかったかもしれないが、最晩年、承久の変によって生じた新皇室での自分の立場も極めて危うい定家にそのような歌学の指導者としての意欲があったのだろうか。老齢の者の芸術的な創作意欲の減退と、それに反比例するように膨れ上がる若年者に対する訓育意欲、昇進意欲、自我の発散意欲を見ない議論もいただけない。
『百人一首』は、もしそれが和歌集であったとすれば、きわめて前衛的な集歌の方針で編まれている。それまでの歌壇には、「百首歌」というものがあった。すでに指摘したように、それは元来、一人の歌人が百首(時に五十首)の和歌を詠んでまとめたものであり、そこから変じて、百人の歌人の和歌を複数ずつ集めて、あるいは百人ほどではないが複数の歌人の各々から百首ずつの和歌を集めて、さらに極端には、百人の歌人の和歌を百首ずつ集めて合計一万首以上の和歌集として一冊の歌集に編むものも「百首歌」と言われた。しかし、百人の歌人から各々一首だけを選んでコンパクトな歌集にしたのは、この定家撰と言われる『百人一首』が最初である。そして、それまでの「百首歌」の歌集と『百人一首』の編集方針が決定的に違うのは、前者は百首を詠った歌人の側で選んだ自作の和歌を集めたものを提出させて編集したものであるのに対して、『百人一首』は編者の側で一方的に選歌して編集しているというところにある。晩年の定家にこういう革新的、前衛的な試みを敢行する意欲があったのか。『百人一首』の成立を書き記した『明月記』は残されていないが、数年前までの残されている晩年の日記の記述を読んでも、晩年の定家にはそういう情熱の残り火は感じられない。
ほぼ同じ指摘は、歌人の選び方、その歌人の和歌の選び方、百首の和歌の並べ方についてもいえる。『百人一首』を論じてきた「国文学」史研究者たちは、多くの者が、定家による歌人の選び方、和歌の採り方、歌人の配列に困惑しているし、中には、そこに定家の仕掛けた「謎」を感じ取ってその解明に取り組んだものも多い。だが、多くの場合、当時も今も選ばれた歌人の代表作という世評が安定している和歌ではなく、凡歌と批評されることも多い和歌が採択されていることの説明に四苦八苦してさしたる結論に至っていない。だがそれは、『百人秀歌』や『百人一首』が和歌集としての完成品であるとみるから苦しまねばならないのであって、定家にはそういう意図も情熱もないとすれば無用の心配であったことになる。
私は、『百人一首』の基になった定家撰の和歌群は歌集ではなく「歌群」であり、その「歌群」は、定家が息子の為家に口伝で秘儀、定家流の歌道の真髄を伝える際の「教材」であったであろうと想定している。それは本来、為家一人にしか見せない秘密の先例集であり、だからそもそも対外的に歌集として発表する体裁になっていないのであり、余人を遠ざけた場での口伝の説明があって初めてその百首を集めた趣旨が判明するものであったであろう。したがって、それは歌集としては完成させていなかったし、随時に追加することも逆に削除することも可能であった。
ところが為家はその父、定家からの秘儀の伝授儀式の辛さを舅の宇都宮頼綱に漏らしてしまい、不審に思った頼綱が自分にも見せよと迫ったので、やむなく定家は、歌集の形に設えて内容を漏らした。それが世にいう『百人秀歌』かそれに近い別本であろう。だが、定家は頼綱に歌集の説明はせず、むろんのことだが秘儀については伝えていなかったであろう。そういう記録はないのである。
ここで一歩引いてみて、『百人一首』という「歌群」は、主題なき歌集であり、歌人なき歌集であり、歌順なき歌集であると割り切ってみよう。つまりここでは、こうした情報をそぎ落として、各々の和歌の作品としての美しさ、定家の選抜と補正によって名歌へと化身するその手際だけが際立って見えてくるように編集されていると理解される。これはたまたま「歌群」として残っているが、そうある必要性もないのかもしれない。和歌の技法を学ぶ教材、もしそうであったとすると、それは教育的な観点からの編成物であって、そこに、歌集としての文芸的な、あるいは思想的な編集意図を探そうとすること自体が無意味なのではなかろうか。定家没後の後世の人士は、この「歌群」が室町時代以降に完成した歌集として再編集され、江戸時代初期に挿画付きの木版本が広く普及し、また宮中でも完成した歌集として解釈、観賞する「百人一首伝授」が行なわれるなど、二條流復興の旗頭として珍重された経緯もあって、鎌倉時代中期、定家が編集した際の原始の姿を「歌群」ではなく「歌集」としてイメージする根本的な誤解をしているのではないか。これが私の抱いた大きな疑問である。
それでは、この「歌群」はどのような性質のものとして編集されたのか。繰り返しになるが、素人の私が考えたことを説明しておきたい。まず、この「歌群」の制作意図は、和歌の道の宗家、家元としての御子左家に代々伝わるべき、「家記」である『明月記』と並ぶ「家歌記」の制作であった。その内容は大まかに言えば『萬葉集』以降の日本の和歌史を縦断するものであり、各時代を代表する『萬葉集』と勅撰の和歌集を十分に読み解いた定家が、これらの歌集から選び出した歌に、そこに定家ならではの華麗な作歌の技巧、仕掛けを駆使する予定で加えたものである。つまりこの時定家は、日本の全和歌史を高みより睥睨(へいげい)し、秘かに、溢れる才能の技を用いて、魔術のように凡歌を名歌に転換させようとしたのである。これができるのが、勅撰和歌集の編纂を命じた歴代の天皇さえ凌(しの)ぐ和歌の道の宗家、家元としての権威であり、誇りであろう。
ここで、ほんの一例だが、定家の作歌の技巧を見ておこう。建仁元(一二〇一)年、後鳥羽院は『院句題五十首』を編んだ。作者は、後鳥羽院、九條良経、慈円、俊成卿女、宮内卿、定家の六名であり、各々が五十首、合計三百首の歌集となった。ここで定家が詠んだ歌の中に、「寄雨恋 あまそそぎほどふる軒のいたびさし 久しや人めもるとせしまに」がある。高野公彦はこう解説する。「『あまそそぎ』は雨だれのこと。上句は『久しや』を引き出すための有意の序詞である。…『ふる』は『降る』と『経る』の掛詞、また、『もる』は『目守る』と『漏る』の掛詞であり、さらに『降る』『漏る』は『あまそそぎ』の縁語である。そして『板びさし』が『久しや』を引き出す序詞となっている」¹⁵。これがきらびやかな定家の世界である。
かつて、島内景二は、後世の凡百の「歌人」による『百人一首』からの安直な「本歌取」を評してこう皮肉を述べたことがある。「これが『百人一首』の力である。『たった百首さえ暗記できれば、あなたは、もう立派な歌人です』と言うお墨付きが、得られるのである。『百人一首』は、どんな人をも、たちどころに「歌人」にしてくれる」¹⁶。確かに、『百人一首』風の歌を作れば、どれほどの凡歌であっても、和歌を詠んだことになる。だが、それだけでは、名手、宗家、家元にはなれない。だから御子左家の子孫が家元としての権威、信頼を得るには、そこをカバーするものとしての、定家に発して代々の当主に受け継がれる、和歌作りの技法を説明している秘伝が必要である。それは口述されるものなので記録されていないが、この技巧を用いて改訂を施せば、『百人一首』は全和歌史を縦断する名歌の集積になるのである。
定家が口述で伝えた秘伝は、定家の基準で見て優れた技法の作品の解説であり、それから学ぶべき点の説明であった場合もあるであろう。そして、それとともに、あるいはそれと別に、この和歌は凡歌であるが、私、定家の技法をもって改善すれば、ほれこの通り名歌になったものを惜しいことをしているという、失敗作の教訓話があり、あるいは、陽成院のように、故あって歌壇から追放され作品を抹殺されて、わずかにそれを免れたたった一首の和歌しか残されていない歌人の消息や背景事実の説明があり、もしかしたらその席では、定家が記憶している、抹殺を免れて秘かに口伝えされてきた、どこにも記録されていない幻の陽成院作の和歌何首かの口述があったのではなかろうか。あるいはまた、承久の乱の勝者である新興の武士の詠む和歌への冷徹な評価と、それにもかかわらず必要な忖度の指導があったりしたことだろう。公家社会の歌壇で、特に配慮するべき公家の説明もあったのだろう。主筋の九條家関連の公家への配慮も申し付けた事であろう。承久の乱の敗者、後鳥羽院の側に付いた歌人たちの和歌の説明やその取り扱いの注意点についての教示もあったことだろう。
そして、この「歌群」は、一子相伝、師資相承で宗家の御子左家の奥深くに仕舞われて、その内容、解釋は宗家の当主だけが知りおくものである。そこには定家が漏らす口伝がついており、当主だけが先祖の定家の学恩を享受できるのであり、それを通じて、宗家、家元の地位は揺るぐことなく御子左家の家系に受け継がれてゆくはずであった。
日本の文化史を見れば、どのような芸能の場合でも、家元、宗家の権威は隔絶しており、一門の門下生は皆この権威に従う。茶道において然り、華道において然り、能狂言において然り、歌舞伎において然り、剣道において然り、柔道において然り、相撲道において然りである。そして、定家という人間は、村井もいうように、栄達への欲望、野心が強い人であったが、それは定家個人の栄達というよりは、御子左家という家の「歌道」家としての栄達の望みであった。和歌の道の宗家、家元となる。この欲望は晩年の定家にあってもなお衰えず、いや、眼前の子孫を見るにつけての焦りにもなっていたのではなかろうか。
村井は定家晩年の『明月記』には為家関連の記事の頻出(ひんしゅつ)が見えるという¹⁷。村井はそれを定家の為家への、父親としての愛着と説明しているが、私は、それに加えてそこには、御子左家の当主として、後継者への思いがあるように思える。定家は、自分の人生の締め切りが近づくのを自覚しつつ、御子左家の後継者の訓育に集中していったのではなかろうか。
¹⁷ 織田正吉『絢爛たる暗号―百人一首の謎を解く』、集英社、昭和五十三年。
¹⁸ 塚本邦雄『珠玉百歌仙』解説、講談社文芸文庫、講談社、平成二十七年、二五〇頁。
¹⁹ 村井康彦『藤原定家「明月記」の世界』、二五八頁。