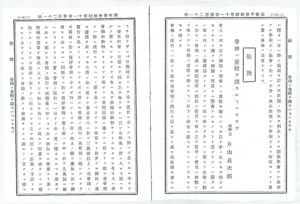こうした事情は、1970年代以降に劇的に変化した。1965年の日韓基本条約の締結を境に日本の経済力に頼った「漢江の奇跡」と呼ばれるような経済の復興、高度成長の続いた韓国社会で、「花闘(ファトゥ)」は大いにもてはやされ、遊技の用具では、硬く、札に反りのないプラスチック製のカードが溢れ、紙製のものは姿を消した。遊技法では、植民地時代に盛んだった日本でいう「八十の馬鹿花」の韓国バージョンである「ミンファトゥ」よりも、「ゴーストップ」、別名「五鳥(コドリ)」が好まれるようになり、日本よりも盛んに遊技されるようになった。
ここで、伝来以来の朝鮮半島での花札の認識を示す「花闘(ファトゥ)」の図柄の変遷を整理しておこう。まず、紋標「松」であるが、これは日本の花札では若松を表現しており、老木は意味していない。だが、21世紀になって、韓国では、「花闘(ファトゥ)」に、成長した松の樹形を加えるものが出現した。韓国では、「松」は幼木から老木まで、松の木全般の意味で理解されていたのであろうか。また、「花闘(ファトゥ)」では、「松」「梅」「桜」の短冊札で、赤い短冊の上に「紅丹」とハングルで書くのがふつうである。もともと日本の花札では、これらの札の短冊に「あかよろし」「みよしの」などの文字があったので、それを写したのであろう。この点では、ハングルへの転換は第二次大戦後に国内で制作が始まるとすぐに起きている。文字もおしなべて「紅丹」である。ただし、紙製の「花闘(ファトゥ)」の中には、「松」と「桜」の短冊札は「紅丹」であるが「梅」の短冊札は「紅帯」というものもある。この札は、三枚の赤短の彩色が微妙にずれているので、何組かの「花闘(ファトゥ)」札を寄せ集めたものであるかもしれないが、それでも、どこかで、「紅丹」を「紅帯」と表現する制作者があったことは確かである。韓国では、わずかに、札の図像の短冊を「帯」と理解した例が残されており、これと符合する。なお、紋標「梅」の札の鳥が鶯からカササギに変化した例があることもすでに指摘してある。
紋標「藤」が「黒萩」に変化したことはすでに何回も指摘している。もともと日本から伝来した「朝鮮花」では、制作コストの軽減を図って、本来は紫色の顔料を使うべき藤の花を黒色で済ませていた。これで印刷過程も一つ短縮されるが、朝鮮半島の人々がこれを黒萩と見たのはごく自然な理解であり、それに伴い札の上下を逆さにした理解も自然である。日本人は、こうした理解を不自然であると冷笑しているが、私はむしろ昭和前期の「日本骨牌製造」など日本のカルタ屋の手抜きが誤解の原因を作ったと思っている。花を黒く彩色しておいて、これを藤の花と理解せよという方が無理なのであり、きちんと紫色に彩色したかるた札を提供していればこういう誤解は生じなかったのである。なお、21世紀になって、「黒萩」を「竹」に改めるものが出現した。紋標「杜若」が「蘭」と誤解された経緯も繰り返し述べた。日本でも「杜若」を「ねぎ」と誤解した花巻花札の例もあるからあまり驚くべき事柄でもないのだが。
朝鮮半島では紋標「芒」が「山」「空山」に理解されている。花札の芒の図像は、元来は大名庭園で茶室の横などに植えられた一群れの芒に花が咲く景色であったのが、木版の「武蔵野」では草原、一面が芒で埋まる野原の景色になり、そのうちに芒の紺色ないし黒色の彩色が濃くなって骨刷りの芒の描線が見えなくなり省略され、それがこんもりと盛り上がって山にみえるようになったという経緯であった。昭和前期までの「朝鮮花」はすでにこう変化した後だったのだから、朝鮮半島の人々が「芒」と理解することは困難であったし、「山」「空山」と理解したの自然である。なお、三羽の雁の最下段の一羽が赤く彩色されていることについてもすでに扱った。紋標「菊」では、盃に「寿」の文字があり、これは第二次大戦後も一貫して維持されている。ごく稀に「福」とした例はあるがいずれの場合も漢字が残っていてハングル化は生じていない。なぜこの漢字だけが生き延びているのかは知らない。
紋標「紅葉」では、もともと近代日本の「八八花札」では、京都風の鹿と大坂風の鹿は異なっていたが、朝鮮に移出されたものは京都のカルタ屋の「朝鮮花」が多かったので、「花闘(ファトゥ)」の鹿は京都風の鹿である。大阪のカルタ屋も大勢に従って京都風の鹿の札を制作していた。紋標「柳」では、小野道風が両班に変化したことはよく知られている。この変化に伴い、柳の枝に飛びつく蛙が犬や亀に変わった例のあることは知られていない。また、「柳に小野道風」の札で、道風の背後を流れる小川が、京都風の花札では左上から道風の背後を通って右手前に流れており、大阪風の花札では右奥から道風の横を左手前に流れている。「花闘(ファトゥ)」は京都風の小川の流れの表現を受け継いでいる。「柳」のカス札が上下逆さに理解されていることも知られていない。最後に紋標「桐」であるが、「花闘(ファトゥ)」では鳳凰が鶏と理解されていた例がある。もともと「鳳凰」は天空の「星辰」を表し、松に太陽の「日」、芒に満月の「月」と合体して「日、月、星」で天空に光るもの、「光物」と理解されて「三光」という役札になり、そこに「柳」の雷光が加わって「四光」になり、さらに「桜に幔幕」が加わり、桜は光らないので「五王」であったが、いつの間にか「五光」になり、その後に朝鮮に伝播したのでその地では最初から「五光」と理解されていた。だが、鶏では桐は光らない。
以上であるので、類型学的に言えば、「花闘(ファトゥ)」は京都製の近代的な「八八花札」の亜種と言える。倒産した地方の中小のカルタ屋の残品には「武蔵野」タイプのものもあったと思われるが、それはごく初期に売りつくされ、あとは京都のカルタ屋の制作した安価な大量生産品のかるた札が流通したのだろう。
以上のような次第で、日本の花札と朝鮮半島の「花闘(ファトゥ)」では、訳あって図柄が相当に異なっているのである。遊技の文化が伝播した例としてはなかなかに興味ある事であるが、私には、日本側の過剰な本家意識も、韓国側の、「花闘(ファトゥ)」が花札の地方札の一種であることへの過剰なアレルギーも、同調しがたいものがある。日本でも、京都のカルタ業界には本場意識が強く、それがカルタの研究者にも伝播して、日本国内の地方札を軽視する傾向の研究が長く続いていた。韓国の「花闘(ファトゥ)」に対するものと同根の偏見である。それに対して、1970年代以降に世界規模で生じた新しい研究の潮流は、地方札を、中央に対する辺境の二流、三流の遊技具と軽視するのではなく、遊技を楽しむ人々の現場に近いところで制作、供給され、人々に遊技具として愛好された、その地域の特徴を持った遊戯文化の重要な要素として正しく理解し、そこに、かるたの文化に現場で親しんだ人々の息吹を感じ、その楽しみや喜びのぬくもりを共感を持って実感しようとするものであった。こうした現場性(ローカリティ)の重視がシルビア・マン学派の研究姿勢の基本であり、その一員であった私の研究姿勢でもあった。
昭和四十年代(1965~74)、五十年代(1975~84)に、日本では、「日本かるた館」などで本格的な遊技史研究が始まったのであり、当然に、韓国での動向も関心を呼んだが、それを本格的に研究し、あるいは成果を公表する動きは鈍かった。少し遅く、平成年間(1989~2019)の初期に活動を始めた研究者世界でのセンター、「遊戯史学会」でも「日本人形玩具学会」でも、カルタに関する報告は、ほぼ私のものに限られており、それも、同志社女子大学の吉海直人が次々と繰り出した事実無根の雑音論文への対応に忙しく、日本のカルタ・かるた史に関するものが多く、韓国の花札文化への言及は少なかった。
そうしたなかで、大阪商業大学アミューズメント産業研究所の研究員であった梅林勲は、アジアのカードとカードゲームの研究を志した。当時は画期的な試みであり、私は、その研究を奨励する趣旨で、私が中国各地で蒐集してきた中国の紙牌コレクションの活用を認め、カルタ札を提供した。ただ、同研究所から出版された梅林の著書『アジアのカードとカードゲーム〈中国はカードゲームの故郷か〉』[1]は、中国や東南アジアについては周到なものであったが、韓国については手薄で、ドミノ牌のコルぺ、錢牌のテジョンはあるものの、「花闘(ファトゥ)」については遊技法に筆が及んでいなかった。
この欠落を補ったのが、平成二十年(2008)に刊行された、伊藤拓馬の『アジアゲーム読本第1集中国骨牌・天九牌/韓国花札・花闘』[2]である。伊藤はここで、韓国及び日本国内での実地調査を基に、「ミンファトゥ」「ゴー・ストップ」「ソッタ」「トリヂッコテン」の遊技法を紹介した。私はこれを、今日では最も信頼できる文献の一つであると思っている。何よりも、実地に飛び込んで調査してそれをまとめて書くという姿勢が敬服に値する。
なお、韓国に旅行した日本人が現地で「花闘(ファトゥ)」に遭遇して驚き、あれこれと考えた印象記風の文章には時々出くわすが、私は『月刊しにか』平成三年(1991)十一月号に掲載された戸田郁子「中国・韓国ものモノ百話 韓国花闘(ファトゥ)(花札)」[3]が面白いと思う。
また、韓国には、花札を自国の文化の産物と理解する花札韓国起源説が繰り返し登場する。花札の図柄がいかに韓国文化の「恨(ハン)」を表しているかを熱弁する著作を読んだこともある。李御寧『韓国人の心[増補恨(はん)の文化論]』[4]は、花札と西洋のトランプを比較して、排日思想の強い韓国人は、すぐ隣国であっても、日本の風俗を容易に取り入れようとはしなかったが、花札に限っては、日本人以上にそれを愛用し、大衆化していった、と理解した。その根底、人間意識より自然意識が、社会意識より風流の精神が韓国では支配的であり、花札が韓国人の感情と呼吸に一致するものがあるの、というのである。
また、世界のカルタの祖国は韓国で、それがヨーロッパに伝わってトランプになり、大航海時代に日本に伝わり、そこから花札が生まれて韓国に伝わったのだから、花札の祖国は韓国だとする地球規模のトンデモ本もある。直接読んだことがないが、花札は旧日本陸軍の慰安物で、第二次大戦中に徴兵あるいは徴用された朝鮮人男性がそれを見習って知ったところから韓国に伝わったとする反日トンデモ学説もあるそうだ。いずれにせよ、「花闘(ファトゥ)」好きの気持ちと日本憎しの気持ちが重なるとこういう発想が生まれやすく、図柄でも、「柳に小野東風」の札が「雨に両班」になり、「梅に鶯」の札が日本では見かけない「梅にカササギ」になり、四君子(梅、竹、蘭、菊)を重視する考えから、「藤」が「竹」にかえられ、「杜若」が「蘭」と考えられ、「柳」は「雨」になった。こうした改変を経て、花札は韓国の自然風物を表しており、だから「花闘(ファトゥ)」・花札の文化は韓国が発祥の地であるという主張につながる。
その後、特に21世紀に入ると、指摘が徐々に政治的な色彩を強め、「松」「梅」「桜」‥‥と展開する日本風の花を排除して、韓国の花で埋め尽くそうという「純韓国風花闘」が続々と提案されるようになる。そして提案者は、「花札には日本帝国主義者が意図した民族精神抹殺と皇民化政策が染み込んでいる」ので「大衆的な花札をわれわれの文化の絵に変える事業こそが植民地時代の残滓清算法だ」[5]と主張するようになり、ついには、政治色の強い「独島花札」[6]までが現れた。一方で、実は日本人も多いのだが、外国人観光客向けの、観光土産色の強い「釜山花札(海雲台花札)」[7]のように、その地のローカルな風物一色に染める花闘札も現れた。ただ、こうしたものは、一時的には興味を惹くが、遊技具としては使い勝手が良くないので実際の遊技では使われることが少なくて、しばらく経つと忘れられてしまう。
もう一つは、花札の図柄の中に日本が滅びる不吉の印を見つけ出して快哉を叫ぶ日本憎し本もある。野平俊水、大北章二『韓日戦争勃発!?韓国けったい本の世界』[8]には、チョン・ヨンモという韓国人の書いた『神仙が残した東洋画』という日本けったい本が紹介されている。内容は省略するので、興味のある人は直接にこの野平・大北本を読んでいただきたい。
大分、余話が続いた。本筋に戻ろう。平成三十年(2018)に、韓国花札史の研究史上の画期的な論文が発表された。魯成煥(ノソンファン)「韓国で栄えた日本の花札」[9]である。この論文は、小松和彦を核とする共同研究の成果物、『文化を映す鏡を磨く――異人・妖怪・フィールドワーク』の一環として発表された比較文化史のものである。これは、日本から入ってきた花札、花札の源流と伝来、花札の受容と展開、韓国人が見た日本の画像、排斥と需要の間で作り出された代案花札、韓国に定着した日本の花札を扱っており、韓国における「花闘(ファトゥ)」の歴史やそれの先行研究について、すでにこの私の文章でも使わせてもらっているように、数々の新情報が提供されており、周到な観察が披歴されている。そして、何よりも嬉しいのは、まっとうな研究者の本格的な研究論文が現れたことであり、これまで孤独に手探りを続けてきた私としては、後事を託せる研究者を発見できたのではないかという印象をもっており、この水準を維持して後続の研究を公表し、韓日両国の研究をリードすることを念願している。
今回、徴用工問題に関する奇妙な主張を知ったことを契機に、こうして私の知る限りの「花闘(ファトゥ)」の歴史をまとめて見た。これで、昭和後期後半(1966~89)、平成期(1989~2019)のかるた史研究者として、歴史への責任の一端を果たせたかと思うところがある。しかし、「花闘(ファトゥ)」の歴史は分からないことだらけである。今後の研究の進展を期待している。
なお、朝鮮には伝統的なカルタ「闘牋」(或は「闘錢」「闘箋」)がある。ここでは、花札、花闘を主題としているので扱っていないが、朝鮮のカルタ文化史としては最重要なテーマである。これについては、大谷通順「朝鮮式カルタ『闘牋』のもつ意味(上)(中)[10]」、伊藤拓馬「朝鮮の紙牌遊戯・闘錢の歴史[11]」がもっとも信頼に足りる研究成果であることを紹介するにとどめて、別の機会を待ちたい。
[1] 梅林勲『アジアのカードとカードゲーム〈中国はカードゲームの故郷か〉』、大坂商業大学アミューズメント産業研究所、平成十二年。
[2] 伊藤拓馬『アジアゲーム読本―第1集―中国骨牌/韓国花札・花闘』、株式会社グランペール、平成二十年。
[3] 戸田郁子「中国・韓国ものモノ百話 韓国花闘(ファトゥ)(花札)」、『月刊しにか』平成三年十一月号、大修館書店、一一二頁。
[4] 李御寧『韓国人の心[増補恨(はん)の文化論]』、学生社、昭和五十七年。
[5] 中央日報電子版、2006年8月3日。https://japanese.joins.com/JArticle/78532
[6] 中央日報電子版、2005年9月15日。https://japanese.joins.com/JArticle/67709
[7] ASIA GATEWAY 2017年1月12日。http://japan.busan.com/jp/news/sub1.asp?num=338
[8] 野平俊水、大北章二『韓日戦争勃発!? 韓国けったい本の世界』、文藝春秋、平成十三年、二八三頁。
[9] 魯成煥「韓国で栄えた日本の花札」『文化を映す鏡を磨く――異人・妖怪・フィールドワーク』、株式会社せりか書房、平成三十年。
[10] 大谷通順「朝鮮式カルタ『闘牋』のもつ意味(上)」『北海学園大学学園論集』第七十一号、同大学、平成四年、三一頁。同「朝鮮式カルタ『闘牋』のもつ意味(中)」『北海学園大学学園論集』第七十四号、同大学、平成四年、三一頁。
[11] 伊藤拓馬「朝鮮の紙牌遊戯・闘錢の歴史」『遊戯史研究』第三十号、遊戯史学会、平成三十年、七〇頁。