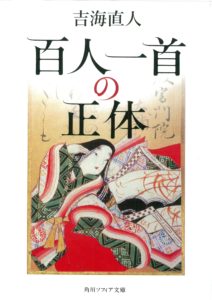「上方屋」前田喜兵衛の冒険が成功して花札の販売の合法性が確認されると、たちまちのうちに広く全国で花札の遊技が大流行した。もちろん、その背景には、それ以前の時期から人々の間ではこの遊技が密かに楽しまれていて、遊技法であるとか、カードの取り扱いとかに習熟している人が多かったという事情がある。この時期の大流行は、つまりは花札の遊技が自由化されて陽の目を見たということである。
日本の歴史上では、それまでに一度、賭博の文化が大いに栄えた時期があった。江戸時代中期(1704~89)である。江戸に集まった武士たちには閑人が多く、その暇つぶしの娯楽が盛んになった。武家は身分を棚上げして町人と共に娯楽に耽った。本名とは別の戯名で戯作、川柳、浮世絵、音曲、舞踏、芝居などの遊芸に加わることもあるし、盛り場、寺社の縁日、芝居小屋、相撲などをぶらついて観る娯楽も盛んであった。男女の性的な娯楽も遊廓から出会い茶屋までさまざまにあった。遊廓は衣装、料理、音曲、芸事などの情報の発信地となった。一方、江戸の町民の間では、もはや従来の農業社会のように労働力として働くことが予定されなくなった嫁や娘が消費社会の旗手となって呉服店や小間物店での買い物に走った。この娯楽過多な世相[1]では、囲碁や将棋などの勝負事やサイコロ、カルタなどの賭博も盛んになる。幕府は享保の改革で博奕禁止の緩刑化を図り、また、江戸の町奉行所は、享保年間(1716~36)に小間物商の「三拾軒組」の営業品目として賭博のカルタも販売を許したのであり、そこで、博奕の専門家が関わる高額で本格的な博奕は依然として厳禁であったが、一般に行われていた少額の賭博行為は自由化されていた。また、芝居見物や相撲見物のような観る娯楽の発展に歩調を合わせるように、「富くじ」のような観る賭博、現代の言葉でいえばギャンブルも盛んになった。
こうした動きは、十八世紀のヨーロッパ諸国での賭博規制と同じ方向性をもっていた。人間は、どのように厳しく罰しても賭博をやめない。そして、この賭けるという精神のありようは社会の発展の原動力でもある。それならば、生活を破壊するような高額の博奕は許さないにしても、一般に日常の楽しみとして行われる賭博行為は認めるし、それに用いる器材は、プロの賭場でも用いられるかもしれないが自由化する。それとともに、競馬が典型的な、観て賭けるギャンブルも公認する。これは、紳士、淑女の交際の楽しみであり、イギリスのアスコット競馬場は王室の所有物であり、またエプソム競馬場で行われるダービー・ステイクスには国王(女王)も臨場して賭けに参加する。これがヨーロッパ諸国の近代における対賭博政策の基本であったが、余り面倒に考えなくても、トランプを販売することが全く自由であっても何も不思議に思わないということだと書けば理解が早いであろう。江戸時代中期(1704~89)の日本もまたこういう近代化に向けた流れに乗っていたのであるが、寛政の改革はそれから大きくかじを切って政策を変更し、大坂の儒学者で懐徳堂の当主であった中井竹山の進言もあって賭博行為やその用具の製作、販売の規制を強化し、その後、規制が緩んでは天保の改革や明治前期(1868~87)の新政府の法制度改革、さらには明治十七年(1884)からの「賭博犯処分規則」の拡大適用などによって規制の再強化を図るという繰り返しの中で日本は世界に例の少ない賭博厳禁国になっていた。それを再度転換して、先進国のヨーロッパ諸国のように市民の余暇の楽しみとして小規模な賭博行為は認めるようになったのが明治二十年代(1887~96)であり、この賭博取締政策の近代化という歴史的な転換を誰にもまして目に見えるものにしたのが前田喜兵衛の挑戦の意味するところだったのである。ここに開かれた新しい時代の景色は従前の社会とは大きく異なっていた。
花札は、上は華族や政府高官、司法界、経済界に広まり、花柳界、学校、軍隊など、明治社会を彩る組織の中に浸透し、下は、一般庶民、その家族、子どもたちの間でも盛んに遊ばれるようになった。そしてそれは、明治二十年代の風俗・文化現象と呼びうるほどの流行ぶりであった。当時、いくつもの文学作品がこの状況を活写した。三宅花圃は明治二十三年(1890)の「八重櫻」[2]である家の家族がその家の書生や女中と花札を遊び、主人公の女性がそれに誘い込まれる情景を描いている。尾崎紅葉は明治二十五年(1892)の『読売新聞』の新聞小説「三人妻」[3]で、花見の宴のあとで、接待に当たっていた三人の女性が、主人が手鞄から持ち出した黒塗り蒔絵の小匣入りの花骨牌で主人と四名で夜遅くまで花札をする場面を描いている。巌谷小波は明治二十五年(1892)の『暑中休暇』[4]で、夏休み前の学校での校長の夏休み中の注意の訓示として「此頃流行の花歌留多、トランプ、またわ彼の面子とか云ふもの、‥‥あれらの遊楽わ、つまり博賭の卵で、耽り易い物ですから、可成手に触れんようにしなければなりません」と述べさせている。内田魯庵は明治三十五年(1902)の『社会百面相』[5]で成り上がり者の貴婦人が徹夜で花札をして大敗したがウイスキを呑んでまたパチパチと始める情景を描いている。小杉天外は明治三十六年(1903)の『魔風恋風』[6]で東京駒込の千駄木林町の下宿屋の女主人が若い男と花札をしながら会話を交わす場面を描いている。徳田秋声は明治四十五年(1912)の『足迹』[7]で夫人公の母親と叔母が会社の小原という男と自宅で花札を始め、叔父もそれを覗きに来る場面を描いている。
[1] 中村幸彦「江戸の娯楽について」(『中村幸彦著述集』第十三巻、中央公論社、昭和五十九年、一五五頁。
[2] 三宅花圃「八重櫻」『都の花』明治二十三年四・五月号、明治二十三年。『明治文学全集八 明治女流文学集(一)』筑摩書房、昭和四十一年、一一八頁。
[3] 尾崎紅葉『三人妻』春陽堂、明治二十五年。『明治文学全集一八 尾崎紅葉集』筑摩書房、昭和四十年、八三頁。
[4] 巌谷小波『暑中休暇』博文館、明治二十五年。吉田書店出版部小波お伽全集刊行会『小波お伽全集十五巻立志篇』吉田書店、昭和九年。
[5] 内田魯庵『社会百面相』博文館、明治三十五年、一一五頁。
[6] 小杉天外『魔風恋風前篇』春陽堂、明治三十六年、二九頁。
[7] 徳田秋声「足迹」新潮社、明治四十五年。『明治文学全集六八 徳田秋声集』筑摩書房、昭和四十六年、二八〇頁。




像への転用(右:源公忠(業兼本)、右より、三條院、後鳥羽院、順徳院(素庵本))-300x127.jpg)