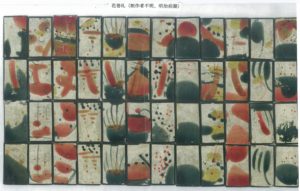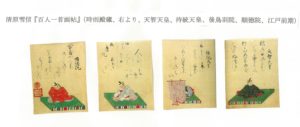花札は日露戦争とその後の満洲の支配においても活用された。新たに租借地となった関東州には骨牌税の適用はなく、また、それに代わるローカルな法令も作られなかったので花札は無税で販売されて有利だった。この地でも、またここを根拠地として北に広がって行った満洲各地でも花札は盛んに遊ばれた。そのうちに、図像にささいな変化が起きた。この地では「八八花」が盛んだったが、「八八花札」の短冊札で、白く空白で残されていた背景の部分に点描、斜線、西海波などが入るようになった。このタイプの札を後年「大連花」と呼んでいるが、カルタ屋ではこれは「八八花札」の亜種としか認識されていなくて、短冊札の背景の部分に点描を施した日本国内向けの「ゴミ入り八八花札」の一種と考えられている。
関東州の花札が日本国内で有名になった理由は、骨牌税法の適用がなかったので日本国内で販売されているものと同じ品質、同じブランド名であっても販売価格が安いことである。骨牌税の重圧がないので、日本国内でも販売されている花札が安価で購入できる。そこで、関東州に旅行する者は、観光客も会社の出張者も修学旅行生も花札を購入して日本への土産にした。こうして日本にUターンで戻ってきた花札には、箱に税関の輸入許可印が捺されているので分りやすい。ただし、第二次大戦が激しくなると昭和十七年(1942)に関東州骨牌税令(勅令第二百五十八号)が発せられて骨牌税法が課せられることとなり、花牌は一組二十銭、その他の骨牌は一組七十銭、麻雀牌は一組五円と定められた。課税の実績からすると、韓国としては、一年間に花札が百五十万組程度輸入されていたようである[1]。
日本の花札は、その後、中国の各地にも広まるようになった。満洲の各地や中国国内の租界では花札が使われたが、独自の発達を遂げるほどではなかった。日本と中国のカルタ遊技との関係は、近代では、骨牌化した麻雀遊技の伝来と流行が主であった。他方で、日本のカルタ屋は中国の紙牌類の製作と輸出を始めたが、それほど盛んにおこなったものではない。
なお、日本からは、明治時代からオーストラリア北部の農業労働者や同国領トレス海峡諸島の木曜島で真珠貝を採取する潜水漁民が大量に移民して、最盛期には同島の住民の七割が日本人だったとも言われている。真珠貝では、洋服のボタンの材料になる貝殻を得るのが主目的で、真珠玉は付録のような扱いであった。彼らの多くは串本などの紀伊半島南部の出身で、故郷で行っていた潜水漁法の技術を使って貝を採取して優秀な成績を上げたが、潜水病などの犠牲者も多く出た。この地では、日本人漁民による賭博、とくに花札と紀伊半島南部のかぶカルタの一種である「入の吉」カルタを用いる賭博が広く行われていた。これはその後も広く普及して、第二次大戦後のオーストラリアでは、民族学者によって、オーストリア本土北部の地域でアボリジニが中国のカードゲームka:buまたはkarbuを行っているという報告[2]がある。報告では実際にこれを行ったときの遊技のスコアが詳細に残されているが、それを見るとka:buは「入の吉」のような一組四十八枚のカルタを使う「カブ」のことである。報告ではアボリジニとされているが、必ずしもオーストラリアの先住民族の人々だけではなく、マレー人、中国人、日本人などの出稼ぎ労働者やその関係者、子孫なども区別されることなくこれに含まれていたものであろう。
第一次世界大戦の結果日本の信託統治地になった南洋諸島でも花札は活発に使われていて、第二次世界大戦後でも、たとえばパラオで、現地の人々によって日本語の用語のままで花札が遊ばれている[3]。
このように、大日本帝国が膨張するにつれて、その最前線で、兵隊や軍隊の関係者、あるいは建設土木や鉱業の出稼ぎ労働者によって植民地支配が実体化する中で、花札が安易な慰安として、また、現地の人々を懐柔する手立てとして、大いに活用されたのである。花札は大日本帝国の標準装備であった。
[1] 『関東州租借地と南満洲鉄道附属地 後編』外務省条約局法規課『外地法制誌』第六部、昭和六十三年、二一頁。
[2] Ronald M. Berndt, Catharine H. Berndt “CARD GAMES AMONG ABORIGINES OF THE NORTHERN TERRITORY” OCEANIA Vol.17, 1947, p.248.
[3] 秋庭武美『南洋の嶋めぐり』朝日新聞社、昭和四十二年、二一一頁。