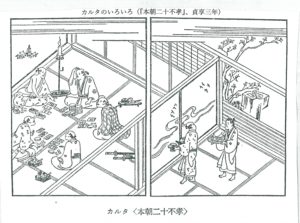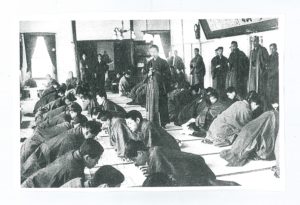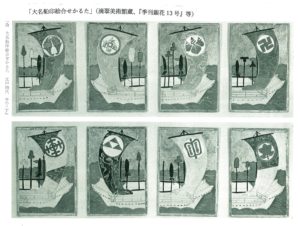麻雀ブームはその後東京にも移ってきた。大正十三年(1924)、まず『婦人画報』に麻雀を楽しむ女性たちが紹介され、林茂光の執筆になる競技法が掲載された。婦人画報社は、中国から麻雀牌を輸入し、林茂光の『麻雀の遊び方』を添えて売った。ついで、大阪で編集されていた『サンデー毎日』に麻雀の競技法が紹介された。同好の士のグループとしては、神奈川県鎌倉市に久米正雄らの鎌倉麻雀倶楽部ができ、東京に空閑緑らの四谷倶楽部ができ、麻雀が流行するようになった。その後、麻雀ブームの中で倶楽部が乱立して遊技にも各団体の異なる主張が矛盾となって争いを生んだので、各団体を統合するべく、昭和四年(1929)に日本麻雀連盟を中心に実業麻雀連盟(代表・杉浦末郎)、本郷麻雀会(代表・高橋緑鳳)、昭和麻雀会(代表・前田清)、銀雀会(代表・榛原茂樹)等、各地の麻雀団体が合併して、新生の日本麻雀連盟が発足した。初代の総裁は菊池寛である。
これに着目したのが東京銀座のカルタ屋「上方屋」と系列店である浅草の「下方屋」で、麻雀牌などの用具を大々的に販売した。蕎麦屋が出前の配達に使った岡持風の小型収納箱に入ったこの時期の麻雀牌のセットはもはやほとんど消滅していてどのようなものか分からなくなっていたが、私は、平成前期(1989~2003)に完全な状態の一組を東京で発見して入手し、いまでは、麻雀博物館の所蔵物となって展示されている。
上方屋は、明治十年代(1877~86)末期にトランプや花札の販売が解禁されるようになると、いち早く情報を得て銀座に開店して大ブームを引き寄せ、日本一のカルタ屋に成長した実績がある。その際には、トランプや花札のゲーム法を載せた小冊子を添付して販売したのが大ヒットの決め手になった。そこで同店は、麻雀牌の販売開始にあたっても同様のことを考えた。また、麻雀の世界でも、これを欧米に紹介したバブコックが、赤い表紙のルールブックを添付して販売したという先例がある。これは、「レッド・ブック」という通称で広く普及し、欧米の麻雀ルールの基礎となった。そこで、上方屋は、『婦人画報』の麻雀競技法の執筆者であった林茂光が、「華昌号」という会社の名前で自ら発行した、表紙もバブコック並みに赤色の小冊子『支那骨牌 麻雀』を添付して麻雀牌を販売した。この小冊子は、一応一円という定価がついているが、自分で出版しているのだから「著者検印」も省略されており、実際に書店で売られるよりも、麻雀牌の付属品として使われることが多かった。こういう事情で、この小冊子は他のものを圧倒して広く普及し、「赤本」と呼ばれて日本の麻雀ルールの基礎となった。
上方屋に次いだのは文藝春秋社であった。自身が熱心な麻雀愛好者であった社長の菊池寛の肝入りであろうか、同社は出版社であるのに「麻雀部」が立ち上がり、麻雀牌や遊技卓その他の関連用具が販売され、麻雀牌の輸入品に奢侈税が課税されて一層高価になると、中国から麻雀牌の彫刻以前の半完成品を輸入し、他方で大連の中村徳三郎(本名金澤熊郎)の助言を得て、あるいは中村が自分から売り込んで(藤浦洸説[1])、中村が経営する 大連の千山閣書房が上海で監督製造させていた麻雀牌の彫工を日本に呼んで、東京、北品川の作業場で彫らせて、国産品として売り出すことで高額の課税を回避してコストの軽減を図った。これが国産一号牌と呼んだ麻雀牌であり、当時の日本で 大好評であった。藤浦洸によれば、文藝春秋社では中村が遊技法を説明し、里見弴、久米正雄、菊池寛が中村と囲んで麻雀を教わり、それを藤浦洸、永井龍男、池谷信三郎らが後から見ていたそうである。
だが、この文藝春秋社牌は、消費され尽して全く残存品がなく、これもまた幻の歴史史料となっていた。そんな中で、私は、東京の骨董市でこれが売られているのを発見し、驚愕、驚喜しながら購入した。その後麻雀博物館に寄贈して、『麻雀博物館大図録』に掲載できたので、その情報はすでに公開されている。牌は華北系のもので想定の範囲内であったが、収納箱は全く想像もしていなかった形状で、そちらの方に驚いた。『麻雀博物館大図録』の掲載写真を見ると、箱に小さなシミがある。私がこれを発見した骨董市の日には、路上で露天商たちが開店した後に雨が降り始めて、皆が一斉に商品を仕舞い始めた時に私が通りかかり、片付けを急ぐ骨董商が早く商談を終えたいので値引きしてくれた思い出につながる。私の到着が五分遅ければ店仕舞いした後で入手できなかったであろうと幸運に感謝した。そしてよく、この雨粒一滴ごとに安くなったと研究仲間にコレクション自慢をしていた頃の記憶がよみがえる。いずれにせよ、これが、私の知る限り唯一の残存する文藝春秋社牌である。
話がわき道にそれた。元に戻そう。林茂光の赤本、『支那骨牌 麻雀』は、こういう事情で日本最初の標準的な麻雀書となったのであるが、これは日本国内でのことであり、それより早く、中国の各地に日本語で書かれた麻雀の解説書がある。上海には、大正六年(1917)刊の肖閑生『百戦百勝、日支親善の鍵、麻雀詳解』、大正八年(1919)刊の井上紅梅『支那風俗 賭博研究』があり、北京には、大正十二年(1923)刊の三澤黙笑『竹林のしをり』があり、山東省濟南には大正十二年(1923)刊の麻生雀仙『麻雀軌範』や大正十三年(1924)刊の日華山人『支那加留多ノ取リ方』があり、天津に大正十二年(1924)刊の林茂光『支邦骨牌 麻雀』、同年の高橋哲雄『支那が生んだ世界的遊戯 麻雀の遊び方』があり、大連に大正十三年(1924)刊の中村徳三郎『麻雀競技法』、広東に大正十四年(1925)刊の山川宗彬『廣東法に據る麻雀の遊び方』、東京に大正十三年(1924)刊の北野利助『麻雀の遊び方』がある。中国の香港、広東などの華南の麻雀(現地表記では麻将)や東南アジアの華人社会でのそれがこの時期に日本に伝来した記録は華北、華中と比べれば乏しいが、朝鮮の釜山には、南中国の影響を受けた、昭和二年(1927)刊の米澤章『標準麻雀競技法とその作戦』があった。つまり、黎明期の日本には、上海麻雀、北京麻雀、天津麻雀、山東麻雀、広東麻雀、満洲麻雀、朝鮮麻雀の伝道者がいて、各々が我こそ本家と称する入門書、解説書を現地で日本向けに、あるいは帰国後に日本国内で出版していたのである。この他に、アメリカ式など西欧の遊技法が適切だとする主張もあった。
おかしいのは、大正十三年(1924)に朝鮮、京城(現在のソウル)の「家庭娯楽研究社」によって刊行された蒲池良介の『支那が生んだ世界的遊戯 麻雀の遊び方』である。京城に在住の著者は、かねてより「一、我が國民(こくみん)は萬世(ばんせい)一系(いつけい)の皇室を奉戴(ほうたい)し、世界に誇(ほこ)るべき權威(けんい)を有する國民なれば、苟(いやしく)も、大詔(しよう)を遵奉(じゆんぽう)し、我國軆(こくたい)の精華(せいか)である、家族制度(せいど)の美點(びてん)を益々發揮(はつき)せしむるに心掛け、弊害(へいがい)多い民衆娯樂(みんしゆうごらく)より、有効なる家庭娯樂を採用(さいよう)する事に留意(りうい)せねばならぬのである。」と考えており、「一、輸入(ゆにう)骨牌(こつぱい)は今度、奢侈(しやし)品(ひん)中に編入(へんにう)され重税を課(か)せられたから、勤儉(きんげん)貯蓄(ちよちく)を奨勵(しようれい)し、國力涵養(かんよう)を絶叫(ぜつきゆう)せねばならぬ秋、成るべく廉價(れんか)である紙札の使用を御(お)勸(すす)めする。」という次第で、自身で考え出した紙麻雀の採用を訴えている。その牌は「寶札」が「天」「地」「人」の三種、「四季札」が「春」「夏」「秋」「冬」の三種と、「一菱形」~「九菱形」、「一短冊」~「九短冊」、「一萬」~「九萬」が四枚ずつ、合計百三十六枚であり、遊技用語もすべて日本語化されて、「自取り上り」「両待上り」「撃ち上り」「終へ札上り」「一色上り」「混ざり一色上り」「三組暗札上り」「總暗札上り」「七ツ對札上り」「九連上り」「四季札上り」などである。日本国内の緩さと対照的な、植民地特有のピリピリした愛国主義の雰囲気であるが、ここまで突っ張るのに、なぜか遊戯の名前は「麻雀」のままで、用いる札の名前も「麻雀カード」(計算札百枚付函入 特價金貮圓)である。蒲池はこれが「京城日報」と「毎日申報」に連載されたことが自慢で、この書の表紙でも自慢しているが、ここまで行くのであれば、「麻雀」という国籍不明の言葉の使用と、せっかく「札」という立派な日本語があるのに「カード」という不浄なアメリカ語の使用は止めて何か他の日本語に改革してほしかった。
[1] 藤浦洸「大正よもやま話」『太陽』昭和四十九年五月号、平凡社、昭和四十九年、八九頁。