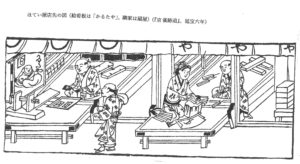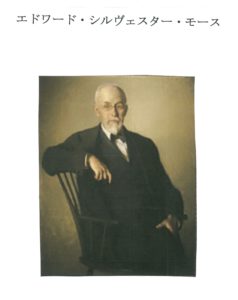続いて第二文節の「凡賀留多有四種紋、一種各十二枚通計四十八枚也、一種紋謂伊須、蛮國稱釼曰伊須波多、此紋形似釼、自一數至九、第十画法師之形是表僧形者也、第十一画騎馬人是表士者也、第十二画踞床之人是表庶人者也、一種紋稱波宇、蛮國稱青色曰波宇、此紋自一數至九数、第十第十一第十二同前、一種紋謂古津不、蛮國酒盃謂古津不、是表酒盃者也、一種紋謂於宇留、蛮國稱玉謂於宇留、是表玉者也。」の解読に進む。
この文節以降で、黒川道祐は、カルタの札を「紋」と「數」(「数」の旧字)で体系的に理解し、説明している。「紋」と「數」はこの文章の基本単語である。かつて、『うんすんかるた』の著者山口吉郎兵衛は、黒川の言う「紋」と「數」を分かりやすいように「紋標」と「数標」に言い換えた。私は、「紋標」は山口に従って使っているが、「数標」はやや誤解を生みそうな言葉なので、ここでは内容を明確に示せる「紋標数」という言葉に言い直して使っている。
黒川は、一組のカルタ札四十八枚には「イス」「ハウ」「コツフ」「オウル」の四種類の「紋標」があるとして、各々が、剣、青色、酒盃、玉であると説明した。「イス」が剣であるというのは正しく、「ハウ」は青(緑)色に塗られた棍棒の誤解であり、「コツフ」が酒盃であるというのは、宗教儀式に用いる聖杯にほぼ合致しているが、「オウル」は金貨である。この辺は当時の京都での一般的な認識を受け継いだ記述であろう。誤解は黒川の責任ではないと思う。
一方、各々のカード上の「紋標数」については、四種類の「紋」のいずれでも数札が「數一」から「數九」まで九枚あり、それに絵札が三枚あり、第十は法師の形を描いて僧形を表わしており、第十一は馬に乗る人を描いて士を表わしており、第十二は(高)床に座る人を描いて庶民を表わしている、と説明している。黒川はここで絵札の名称を説明していないが、当時の一般的な理解でいえば、第十は「ソウタ」で、女性の従者を描くものが多く、それがこの頃に僧侶の姿とされるようになった。第十一は「カバロ」で、騎士の乗馬姿であったが比較的に早い時期から「馬」、「ムマ」と呼ばれていた。第十二は縁側のような高床に座る王で、古くは「レイ」、その後は「コシ」とか「キリ」と呼ばれていた。「王」を「庶人」とした黒川の説明は、これも当時の一般的な誤解に従ったところであろう。