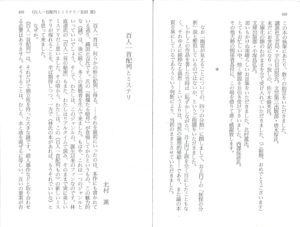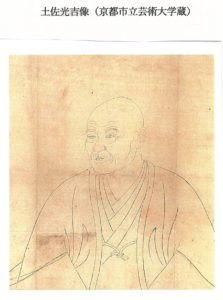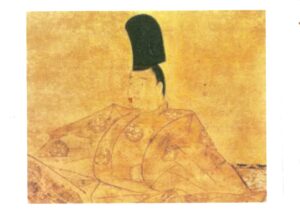この、「蝙蝠龍」と「火焔龍」の違いが示す、うんすんカルタ制作地が二箇所であったという理解は、このかるたのもう一つの謎、「ソウタ」の問題にも関係してくる。研究室は、文献史料では、延宝年間(1673~1681)頃から天正カルタの遊技でも「ソウタ」という表記が消えて「坊主」と呼ぶ場合が増えることを指摘している。そのことは興味深い発見であり私に異論はない。寛文年間(1661~73)から延宝年間(1673~1681)頃に、カルタブームでカルタ札の需要が急増し、寛永年間(1624~44)頃から営業していた「松葉屋」や「ほてい屋」などの六條坊門(五條橋通)の絵草子屋が本格的に庶民向けの安価な品を売り出すようになったと思われるが、それは、図像を木版で彫り、摺った紙に上から赤と紺の二色で簡単に手彩色したものであり、ここに賭博系のカルタの現在まで踏襲されている図像の原型が確立した。このカルタでは、「ソウタ」の札は骨刷りの図像の上から赤と紺で手彩色したのであるが、その骨刷りの図像が手彩色される箇所からはみ出して、僧侶の姿に見えるのである。つまり、延宝年間(1673~1681)以降、六條坊門(五條橋通)で制作された安価な普及品のカルタでは、「ソウタ」は「坊主」になったのである。「坊主」の中でも「ハウ」の「ソウタ」は図像から「釈迦十」と呼ばれ、「イス」の十は彩色の特徴から「すだれ十」と呼ばれた。
だが他方で、うんすんカルタでは「ソウタ」という語が用いられ続けていた。そして山口吉郎兵衛は、既述のようにすんくんカルタの「ソウタ」が弁財天に似た着物姿であることからうんすんカルタ史の初期(貞享~元禄、1684~1704)からすでに女性の「ソウタ」の図像があり、それは中期(宝永~宝暦、1704~1764)を経て末期(明和~寛政、1764~1801)まで広く通用していたものと考えた。山口は、男性の「ソウタ」が元禄年間末期に女性の「ソウタ」と共存していたことについては注意を払っていないが、それにもかかわらず、カルタ史の研究者としてすんくんカルタの好個の史料を発見し、それを自身の研究の上でも有効に活用し、またそれを広く公開して後進の研究の便宜を図っていることには大きな敬意を表したい。