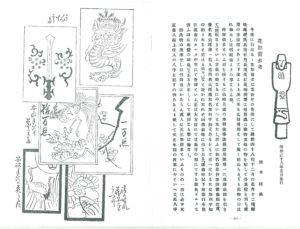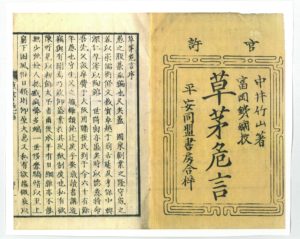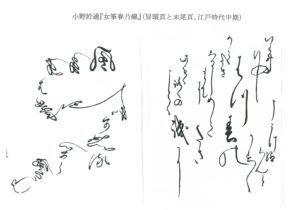花札の歴史研究にとって重要な明治期の文献の一つが、雑誌『風俗画報』に掲載された、永沼小一郎の「古今室内遊戯餘談」という論文[1]である。永沼は「花カルタ」の由来、創始者が残した古い遊戯法、「合駒骨牌」という遊戯法について述べている。私は『ものと人間の文化史167 花札』で永沼の生涯と事跡について詳しく論じたので、ここではこの論文の中身、それも前二者に限って検討しておきたい[2]。
まず、「花カルタ」の由来は、次のように説明されている。
①「花カルタ」の創始は天保年間の頃である。②当時は「点附かるた」つまり「めくりカルタ」が大流行して、「良家の子女」までが賭博として興じていた。③「花カルタ」の創始者はこの風潮を嘆いたある上流階級の者である。④創始者は、カルタの絵柄を以前からある「花合」に借りて花鳥をあしらった。⑤遊戯法も賭博心を自戒できるように優雅なものを工夫した。⑥この企画は大当たりして人々は「花カルタ」を愛好するようになり「めくりカルタ」は博徒の専用カルタになった。⑦ところが「花カルタ」の「性質」が幾分か「めくりカルタ」に似ていたので博徒が賭博にも転用するようになり、「花カルタ」は「めくりカルタ」同然のものと理解されるようになった。⑧そのため識者が恥じてこれに触れることがなく、当時の記録に記載がない。
以上の永沼の指摘は、論拠を示してはいないが、清水晴風らの所説に従ったもので、特に独創的ではない。花札の創始を天保年間の頃と主張しているが、その論拠は明らかでない。ただし、すでに清水晴風が「花加留多考」で「思うに天保年間に初りしものならん。‥‥花加留多に至りてうんすうかるたと相合し、遂に賭博の用具となり了りしなり。」と指摘し、「日本社会事彙」も「文政天保の間なるが如し。」と指摘していたのであるから、他に異説を見なかった当時であり、永沼もそれに従ったのであろうか。
ただ、ここで永沼は、「花カルタ」の創始者が、その遊戯法についても「めくりカルタ」とはまるで違う優美なものを開発したと指摘して、「創始者の考案した遊戯法」を詳細に紹介した。このことによって、この論文は花札史研究の最重要文献の一つに押し上げられた。それをこれから検討するが、理解の良さを考えて、原文に換えて私が要約したところを紹介しておきたい。
永沼によると、創始者の技法では、遊技法は現在の花札と同じように、三人の競技者の各々に七枚ずつのカードを配り、場に六枚の場札を散らして始まる。競技者は順番に自分の手中の手札を一枚場に出して、同じ紋標のカードと合せることができたらその場札とともに釣り上げて手中に収める。それができない時は出したカードも場札として残す。次のその競技者は二十一枚残されて場の中央に裏返しに積まれた山札から一番上部のカードを一枚表に返して、それが場札(自分が直前に出した手札も含む)と紋標が合えばその場札とともに獲得する。場に二枚同じ紋標のカードが晒されているときは競技者は手札や山札と場札のうちでいずれを合せて獲得するのかの選択権があり、ゲームの開始時に場札として三枚同じ種類のカードが晒されている場合は、残りの一枚を手札として持っているか山札から引き出した者が一度に三枚全部を獲得する。こうしてゲームが展開されて、手札の合計が二十一枚で、山札も二十一枚なので数が合い全部を使い切って一回のゲームが終了して勝ち負けの計算に入ることになる。なお、四人で競技するときは、手札を五枚ずつ配って場札を八枚まくこともできるし、六枚ずつ配って場札なしで始めることもできる(その場合、最初の競技者は釣り取る場札がない状態ではじめることになる)。
ゲームの勝ち負けは、合せ取って手中に確保したカードを「古実、古歌」などの意を取ってさまざまに組み合せ、その組み合せの多くできた者が勝ちである。そのために、描き出した花木鳥獣の選定もできるかぎりこの趣向に叶うように大いに心してある。出来役の組み合せのうち、二枚組は一点、三枚組は二点、四枚組は四点(ただし、後掲の「藤壺」「桐壷」「梅壺」「八橋」は四枚役だが一点)で、五王(今日の五光札)と七夕(七夕=七赤で、赤色の短冊七枚)は全勝というからそれができれば勝負決まりということなのであろう。
永沼は、こうした役を順次に紹介している。永沼は、草木に動物や器材の付いたカードを「主牌」、短冊の付いたカードを「短冊」と呼んでいるのでそれにしたがって説明しよう。役は、「表菅原(松、梅、櫻の主牌)」、「裡菅原(松、梅、櫻の短冊)」、「大鳥の組(松、芒、桐の主牌」、「小鳥の組(梅、藤、柳の主牌)」、「野荒しの組(萩、紅葉、芒の主牌」、「三光の組(松、芒、桐の主牌)」、「四光(松、芒、柳、桐の主牌)」、「五王(松、櫻、芒、柳、桐の主牌)」、「菊桐(菊、桐の主牌」、「月の宴(別名:月見)(芒、菊の主牌)」、「花の宴(別名:花見)(櫻、菊の主牌)」、「紅葉の賀(別名:紅葉見)(菊、紅葉の主牌)」、「月ホト(藤、芒の主牌)」、「蝶花(桜、牡丹の主牌)」、「獅子牡丹(牡丹、萩の主牌)」、「高砂(松、牡丹、菊の主牌)」、「鞠懸(松、櫻、紅葉、柳の主牌)」、「紫短(牡丹、菊、紅葉の短冊)」、「七夕(松、梅、櫻、藤、菖蒲、萩、柳の短冊)」、「三紫(藤、菖蒲、桐の主牌)」、「三紅(梅、牡丹、萩の主牌)」「桐壷(桐四枚)」、「藤壺(藤四枚)」、「梅壺(梅四枚)」、「八ツ橋(菖蒲四枚)」である。
以上が永沼による初期の技法の紹介であるが、一見して分るように、ここには、今日の花札の代表的な出来役である「四光」「五光」「赤短」「青短」「七短」「猪鹿蝶」などの役に近いものがすでに生じている。しかもそれは、「四光」が実際に光る天文現象を指していて「桜に幕」が含まれていないこと、「五光」は「五王」であること、「青短」は「紫短」であること、「赤短」の役は未成立で赤色の短冊札をすべて集めた「七短」の役であること、「猪鹿蝶」も未成立で「野荒し(猪鹿雁)」であることなど、微妙に食い違っている。こうした点から、これは花札固有の役の構成で、しかも相当に古いタイプのものと考えられるのである。
この技法では獲得したカードの組み合せによる勝負という基本は見えたように思う。つまり、花札固有の技法では役に最大の関心があったのである。これに、補助的に札の目数を計算に入れたのか否かは不明であるが。
問題は、こうした役が花札固有の役か、それとも「めくりカルタ」の役の翻案であるかにある。たとえば「めくりカルタ」には「団十郎(あざ、青二、釈迦十)」、「上三(釈迦十、青馬、青キリ)」、「下三(あざ、青二、青三)」、「仲蔵(青七、青八、青九)」、「赤蔵(赤七、赤八、赤九)」、「海老蔵(あざ、釈迦十、海老二)」の六大役があった。これを花札の古い名古屋風の順序によって対応するカードに翻案してみると「団十郎(松、柳、紅葉の主牌))」、「上三(紅葉、牡丹、梅の主牌)」、「下三(松、柳、桜の主牌)」、「仲蔵(萩、芒、菊の主牌)」、「赤蔵(萩の短冊、芒に雁、菊の短冊)」、「海老蔵(松と紅葉の主牌、柳に鳥)」となり、花札の役にはこれらに対応した組み合わせたものがないことが分る。念のために今日の順序で翻案してみると、「団十郎(松、梅、紅葉の主牌)」、「上三(紅葉、柳、桐の主牌)」、「下三(松、梅、桜の主牌)」、「仲蔵(萩、芒菊の主牌)」、「赤蔵(萩の短冊、芒に雁、菊の短冊)」、「海老蔵(松の主牌、紅葉の主牌、梅の短冊)」となり、「下三」以外はこれまた対応する役がない。したがって、永沼の紹介する古い遊戯法の役は「めくりカルタ」の役の翻案ではなく、花札固有のものであるといえる。このように、肝心の役が違っているのだから、花札は禁止時代の「めくりカルタ」の脱法的な代用品として始まったという説は成立しにくかったのである。
以上の永沼の指摘は、花札の遊技法の発祥についての最も重要な証言である。というよりも、体系的な説明をしたものは、これが唯一であると言っても良い。永沼は貝類研究の学者であり、論拠のないことは言わない。その永沼が「創始者の考案した遊戯法」とするのであるから、何か紙に書かれた史料があっての話だと思う。それが具体的に示されていないのは残念であるが、永沼の記述は信頼できると思う。
[1] 永沼小一郎「古今室内遊戯餘談」『風俗画報』三百八十壱号九頁、三百八十三号十頁、三百八十四号五頁(いずれも明治四一年)。
[2] 永沼のこの論考はほとんど忘れられているが、小宮豊隆編『明治文化史10 趣味娯楽編』、原書房、昭和五十五年、五〇五頁以下はこれをほとんどそのままに紹介している。