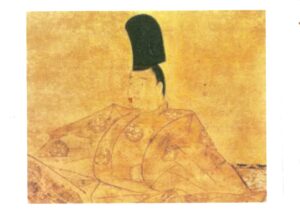こうして、「三池カルタ」の復元は完成した。開館後の「三池カルタ記念館」では、やはり来館者の注目はこのカルタに集まり、江戸時代初期のカルタのイメージを明確に伝えることができた。数百万円の高額の費用を要した事業であったが、取り組んでよかったと思っている。
しかし、反省するべき点ももちろんある。最大の反省点は、平成十四年(2002)に新たに 天正カルタの版木 、一組三十二枚分が発見されたことによる。三池カルタ記念館は購入を検討したが、まだバブル景気の余熱の残る時期であり、売り手が強気の価格を提示しており、一方、市は財政難で折り合いが付かずにあきらめた。その過程で私は実物を手にして調査することができた。その際の記録、三池カルタ記念館への鑑定報告書が残されているのでそれを元に説明する。すでにん上述した部分と重複するがお許しいただきたい。
これはカード四枚分を縦に並べて彫り込んだ版木を八枚、合計でカード三十二枚分のものを用いた硯箱で、元来は、残りの版木四枚を用いたもう一段の箱がある重ね箱であったと思われた。上蓋にはカード四枚を縦長に彫り込んだ版木が四枚並べて用いられていた。左から右へ、「イス」の「ソウタ」「ドラゴン」「キリ」「ウマ」の版木、「イス」の「九」「八」「七」「六」の版木、「ハウ」の「ソウタ」「ドラゴン」「キリ」「ウマ」の版木、「イス」の「五」「四」「三」「二」の版木である。底箱の四周には同様の版木が用いられていた。長方形の箱の側面には「コップ」の「二」「三」「四」「五」の版木と、「コップ」の「六」「七」「八」「九」の版木、上下の面には「オウル」の「二」「三」「四」「五」の版木と、「オウル」の「六」「七」「八」「九」の版木である。但し、寸法を合わせるために「オウル」の「六」と「オウル」の「二」は切り取られていた。このほかに失われたもう一組の底箱には「コップ」の「ソウタ」「ドラゴン」「キリ」「ウマ」の版木、「オウル」の「ソウタ」「ドラゴン」「キリ」「ウマ」の版木、「ハウ」の「九」「八」「七」「六」の版木、「ハウ」の「五」「四」「三」「二」があったと思われる。
版木に彫られたカード一枚の大きさは、縦七・四センチ、横四・一センチである。これは、滴翠美術館の「三池カルタ」の「ハウのキリ」のカードや神戸市博物館の「天正カルタ版木重箱」のカルタの大きさ(縦六・三センチ、横三・四センチ)と比べて十五%程度大型でやや縦長であるが、「南蛮文化館」蔵の手描き天正カルタとほぼ同じ大きさである。
これは実に衝撃的な新史料の発見であった。まず、何よりも、これは当時実際に使用されていた版木をそのまま転用した再利用品であることが明白であった。ここでは、版木は縦長の板で、数札についていえば、縦に四枚のカードが彫られており、その並び方は、紋標によって、あるいは「二」「三」「四」「五」と「六」「七」「八」「九」であり、またあるいは、「九」「八」「七」「六」と「五」「四」「三」「二」であった。神戸市博物館の「天正カルタ版木重箱」については以前から、幕末ないし明治前期に改作されたのではないかという疑いがあり、とくに数字を横一列に並べるのが江戸時代のものの考え方と違っていかにも近代臭いのが気になっていたが、江戸時代の日本での数字の並べ方にかなったこの縦並びの「版木硯箱」の出現によってこの疑いが裏付けられた。
次に衝撃的であったのは大きさである。私は、日本に伝来した「南蛮カルタ」は大判のもので、それが小型化して天正カルタになったと理解していたが、「南蛮文化館」所蔵の手描き天正カルタは一回り大きいので、その違いが気になっていた。それが、こうして版木の状態で「南蛮文化館」所蔵のものと同じ大きさの木版のカルタが想定されるようになると、小型化は段階を追って起きるものであるから、「南蛮文化館」所蔵のものとこの版木のカルタが初期の天正カルタのサイズであり、復元した「三池カルタ」は第二期、中期のものと考えられることになる。復元かるたの制作当時はこれが大牟田市三池地区で制作した初期の「三池カルタ」であろうと考えていたのであるから、この新発見は大きなショックであった。中期の「三池カルタ」であったとすると、復元したものは、大牟田市三池地区で制作されたカルタではなく、三池出身の職人が京都に進出したのちに制作した「三池カルタ」ということになる。これは一種の神話の崩壊である。幸いなことに、新発見の版木の図像は、復元カルタと変わりなく、したがって、「三池住貞次」のカードが京都製だとしても、それ以前に三池地区で制作されていたであろうカルタも同じ図柄であったことがはっきりした。復元品のミスはカードの大きさの誤解だけであって図柄はほぼ同じであったのがこの失敗の中での救いであった。ただし、用紙については九州の八女和紙を用いたので、京都に進出した後に制作されたとすると、遠隔地の筑前、八女の紙を用いたというよりは身近の越前や美濃の紙を使う方が自然であり、滴翠美術館の鑑定は再検討される必要性がある。残念である。