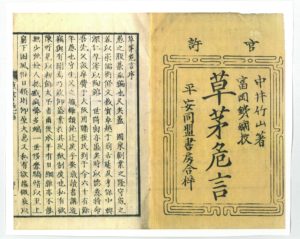貞享三年(1686)刊の『鹿の巻筆』[1]「三人論議」では、主役の一人三郎兵衛は「カルタをすきて、讀(よみ)の、合(あわ)せの、かうなどゝいふ事のみ深(ふか)く望(のぞ)みけり」であり論議の中でカルタを弁護して「讀(よみ)のかるたは壹枚のこり、上(あ)がられぬ事八つの善(ぜん)ありながら、壹つの悪(あく)にひかさるゝ心なり。‥‥合(あわ)せにては人の善悪(ぜんあく)をしり、かうにては人の運否(うんぷ)をしる。三枚まくは三くじの心なり」という。もちろん、強引なこじつけでありそれを笑う場面であるが、かぶカルタの遊技が盛んであったこと、それはまだ読みカルタや合せカルタと比べて特に遜色のない品性の遊技とされていたことが分かる。多少気になるのは最後の「三枚まくはみくじの心なり」であり、「かう」の説明なのか、「かう」とは別の「三枚」という遊技法の説明なのかが明確でない。また、「三枚まくのは御籤のようなもの」というからには、相当に偶然性が強い遊技法であろう。参加者には三枚目の札の配分への拒否権はなく、ひたすらに良い札が来ますようにと祈るのであろうか。
この時期の『露新軽口はなし』[2]も興味深い。寺の庭にある大きな銀杏の木に雷が落ちて根こそぎに破壊された。寺の長老が僧を二人連れて見に来て、こんなことをするのは神鳴(かみなり)ではなくスリだといった。これを上空で聞いていた雷がスリではなく神鳴りだ、坊主が三人出たのかという。長老は、無礼な奴だという。ここから話はカルタ勝負の話になってオチに進む。雷が、自分は大きな銀杏に落雷したのだからオイチョウ(八)だ。根こそぎ取るのは、お前たちが三人の坊主で、これは三枚坊主でブタ(ゼロ)で大負けしたからだ、とからかう。これに対して長老は、何でお前が上成り(かみなり・上回って勝つこと)なのか。自分は大銀杏(八)と大銀杏(八)の間に三人(三)だ、自分の勝ちだ、といった。このオチで笑えるには、話を聞いたときに瞬時に「オイチョウとオイチョウと三寸」で足して十九、つまりカブだから雷のオイチョウに勝つという「かう」の遊技法に明るくなければならない。逆に言えば、これで笑える程に当時の人々はかぶカルタの遊技に通じていたのである。この時期のかぶカルタの流行のほどが分かる。
貞享年間(1684~88)といえば、カルタが大好きな井原西鶴が活発に執筆活動を行い、カルタに関連する表現が現れる時期でもある。貞享三年(1686)の『本朝二十不孝』[3]の「先斗(ぼんと)に置(をい)て来多(きた)男」では、「京カブ」で多額の賭金をして破産し、悲惨な人生の終わり方をした男の話があり、翌貞享四年(1687)の『懐硯』[4]の「照(てる)を取昼船(ひるぶね)の中 祈れどきかぬカルタ大明神(みやうじん)の事」では淀船の船中で遊びで始めたカルタ遊技に夢中になり、賭金の額も大きくなり、「アトサキ」「浄土カブ」「三番マキ」等のかぶカルタ系の遊技で大損をする話がある。
元禄年間(1688~1704)では、浮世草子作家の西沢一風がカブ好きで、その作品中には、元禄十一年(1698)の『新色五巻書』[5]に「なさけなやすそびんぼうのはりぞこなひ。打まくる三枚がるた。是まだるしと四三五六(読みいらう)。」で、伏見で為替の金二十両を請取り、帰り道に道草してわずか十八歳なのにこの金でかぶカルタ賭博の胴を取って勝負する肝の太さだが、天運尽きて金をとられ、店に帰って主人への言い訳がうまくいかず、結局主殺しをして逐電し、東海道の見附で捕まり人生極まった男の話がある。「三枚」がまだるっこしく、「読み」に切り替えて弄ぶというのだから、この場合の「読み」は相当に高額の賭けであろう。元禄十三年(1700)の『御前義経記』[6]では船中で「片肌脱いで四十八願の絵合せ、後には三枚がるた」の開帳になり、つきにまかせ銭の有たけを跡さきにはる者、かしらに十文、跡張り卅の銭の者、跡先なしに一貫の銭をホントにはる者、三十の銭を負けて落胆する者などを面白おかしく描写している。この他、西沢の作品には、元禄十五年(1702)の『女大名丹前能』[7]、元禄十六年(1703)の『風流今平家』[8]などにもカルタ遊技の場面が登場する。
西沢以外にも、元禄八年(1695)以前の『役者絵づくし』[9]に「捻って遊べ三枚がう」という表記が有ったり、元禄十六年(1703)刊の雨滴菴松林(馬場信武)『風流夢浮橋』[10]に播磨から大坂に向かう乗合船の船中で船頭の主導で「三枚かるた」が行われる場面が描写されていたりするなど、カブに触れる文献は多い。尾崎久彌が発掘した好色本『好色梅花垣』[11]の「カルタのたたき鳥追節」にはさまざまなカブを詠み込んだ鳥追いがあるが、一五三の「御かぶ」、二三四の「のぼりがぶ」、三三三の「今みやがぶ」、五五九の「でつくがぶ」、七五七の「二条蔵人あいごがぶ」などとともに八八三の「雷公がぶ」があるのが上記の寛文年間(1661~73)の『露新軽口はなし』とつながって興味深い。『ものと人間の文化史173 かるた』では、やや時代のさがる近松門左衛門の作品での「ひつはりぶた」「鎌倉ぶた」「のぼり九寸(がう)」等も紹介したが、ここでは対象を江戸時代前期に集中するので江戸時代中期(1704~89)の事例の検討は省略する。
[1] 「鹿の巻筆」『江戸笑話集』日本古典文学大系第一〇〇、岩波書店、昭和四十一年、一六九頁。
[2] 「露新軽口はなし」『噺本大系』第六巻、東京堂出版、昭和五十一年、二〇〇頁。
[3] 井原西鶴「本朝二十不孝」『対訳西鶴全集十』、明治書院、平成五年、一五三頁。
[4] 井原西鶴「懐硯」『対訳西鶴全集五』、明治書院、平成四年、七六頁。
[5] 西沢一風「新色五巻書」『西沢一風全集』第一巻、汲古書院、平成十四年、一八頁。
[6] 西沢一風「御前義経記」『西沢一風全集』第一巻、汲古書院、平成十四年、二一〇頁。
[7] 西沢一風「女大名丹前能」『近代日本文學大系』第四巻、国民図書、昭和三年、二八九頁。
[8] 西沢一風「風流今平家」『西沢一風全集』第二巻、汲古書院、平成十五年、一九一頁。
[9] 武井協三「役者絵づくし」『歌舞伎とはいかなる演劇か』、八木書店、平成二十九年、二五四、二八一頁。
[10] 雨滴菴松林(馬場信武)「風流夢浮橋」『初期浮世草子二』古典文庫五六八、古典文庫、平成六年、三三一頁。
[11] 「好色梅花垣」『国文学解釈と鑑賞』第三十二巻第五号、至文堂、昭和四十二年、三九頁。