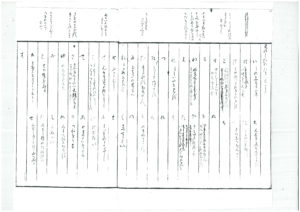さて、斎藤月岑の記録により、江戸のいろはかるた史の大まかな道筋が見えてきた。江戸時代中期(1704~89)に、上方で、それまでの「譬え合せかるた」をいろは順の四十八対に整序する考案があり、その新型のカルタが江戸に波及し、その後、文化文政期(1804~30)に江戸固有の「いろはかるた」になったということである。
この変化をもたらした原因はさまざまに考えうるが、私は、かるたの材質に注目したい。上方の「譬え合せかるた」は、他の種類の絵合せかるた類と同様に、伝来のカルタ札の制作方法で作られていた。江戸時代中期(1704~89)には木版、合羽摺り、表紙(おもてがみ)と裏紙で硬い芯紙を挟んで切断し、裏紙を縁返し(へりかえし)て制作されており、その方式は、明治年間(1868~1912)以降にも、「譬え合せかるた」の後身である「道斎かるた」の制作方式に引き継がれている。こうしたかるた札の制作方法に関しては、京都、大坂が卓越しており、日本一であった。
これに対して、江戸の「いろは譬え合せかるた」は木版印刷の手法で制作されており、制作者の側で芯紙、裏紙と貼り合わせて、切りっ放しの手法で仕上げられた。京都のかるた札と比べると柔軟な仕上がりであった。これが、簡略な帯封にくるまれて売り出された。多色摺りの木版印刷では江戸が最も盛んで、技術水準も最高であったから、日本一の木版かるたを作ることができた。また、これと別に、木版摺りの表紙(おもてがみ)だけが裸で売り出され、購入者の側で芯紙、裏紙と貼り合わせて使用したものもある。いずれにせよ、上方の、木版骨摺り手彩色、縁返し(へりかえし)、木箱入りのかるたに対する、江戸の、多色木版摺り、切りっ放し、たとう包みというかるたの技術革新があったのである。
この多色摺りの木版印刷という制作方法の革新は、容易に想像できるように「譬え合せかるた」に限られるものではない。広くは、庶民向けの書物、浮世絵、瓦版、遊び道具などがあり、かるたの世界でも、江戸出来の多彩ないろはかるたが、役者かるた、忠臣蔵かるた、お化けかるた、武者かるた、なぞなぞかるた、お伽かるたなど、さまざまに考案され、市場に登場した。また、さらに広く理解すると、だまし絵、千代紙、折り紙などの児戯の具が成立するということは、それまでの、大人のかるた遊びに子どもが混ぜてもらうという遊技から、女性と子どもの遊びが独立して成立するようになったと言っても良い。市場では、確かに、女子どもの児戯の具であって、購入者は保護者、男親であるかもしれないが、それを実際に使う消費者は女子どもである。だから制作者は、最終消費者の女子どもたちが興味を感じて、それを使用する意欲を持つような、女子ども向けの、その好みに合わせた遊技具を制作、販売することになる。これは、日本における市場での消費者としての「女子どもの発見」である。ヨーロッパでは、十八世紀に「子どもの発見」があったと言われる。日本でも、ほぼ同じ時期に、木版摺りの文化の世界で女子どもが発見されているのである。
話を「いろは譬えかるた」に戻そう。この種類のかるたは多様に考案されていたが、その中で「犬棒かるた」が有力になり、その覇権が確立した時期は、江戸時代後期の後半(1830~54)、幕末期(1854~67)に近い辺りではないかと思われる。そして、ここに成立したいろはかるたについて、上方の町人文化と違う江戸の町人文化を鋭く指摘したのが、森田誠吾の研究であった。上方と江戸のいろはかるたが各々四十七対・九十四枚、それに江戸かるたにはおまけの「京」の札一対・二枚を加えて九十六枚の紙片に見入り、そこに流れる町人気質の文化を解析して描き出した研究は広く共感を呼んだ。私も共感するところが多い。ただ、いろはかるた史の研究としては、何点か書いておかねばならないところがある。
まず第一に、森田も含めて、多くのいろはかるた史研究者が、鈴木棠三の影響もあって、「いろは譬え合せかるた」の前身、「譬え合せかるた」は江戸時代後期(1789~1854)には姿を消したと理解したのが誤解であったことである。これはすなわち、上方の町民文化の結晶が、森田たちが考えていたよりも長期間、江戸でも愛好され続けていたことを意味する。森田の、上方文化と江戸文化をシャープに対置させる理解はやや理想形に傾き過ぎていたのではなかろうか。
第二に、森田の東西比較論は採用されている譬えの分析に基づくものであるが、絵札の図像を見ると、歌舞伎芝居との結びつきが目立つ。これは古くは戸板康二『いろはかるた』が指摘していた点であり、後に伊藤高雄も同様の指摘を繰り返して、それが「いろは譬えかるた」は元来は大人向けの遊技具であった事実の証拠になるとする[1]。
なお、北村孝一は「犬も歩けば棒に当る」が「ゐぬもあるけばぼうにあたる」となっている國周画の芝居絵を研究して、これは「容姿に優れ、品もよかったといわれる音羽屋、板東彦三郎(四世)の荻野屋八重桐(演目は「嫗山姥(こもちやまんば)」)で、上演は慶應三年(一八六七)、錦絵は翌年新春の版行のようだ」と鑑定している。この歌舞伎芝居では、「夫を探し、あちこち歩き回っていた八重桐が思いがけないことから夫に巡り合うという展開であり、それゆえ「犬も歩けば棒に当る」にあたるとみたててよいのではないだろうか」というのである[2]。
こうした北村の立論は注目されるのであるが、前提とする事実の認識に誤りが目立つ。まず、北村はこれをいろは譬えかるたの絵とするが、それは時田昌瑞が見誤り、吉海直人が模倣して拡大した誤解の追随である。この國周(正確には國周と落合芳幾)作の錦絵のシリーズは、慶應卯年(三年)に版行された芝居絵であり、画面上に譬えがいろは譬えかるたの札のように描かれているが、実際には思いついた譬えをかるた札風に描いただけで、実在するかるた札を転写したものではない。したがって、ここに「ゐぬもあるけば‥‥」とあるからと言って、そういう表記の譬えがあったとは言えても「いろは譬えかるた」があったとは言えない。参照できる史料が少なかった時田の場合は同情できるが、その誤りを踏襲した吉海も、又吉海に追随した北村も研究の実証性に欠けている。さらに、北村は、吉海が萩野屋八重桐を荻野屋と誤読したものに追随している。また、錦絵の版行は慶應卯年(三年)四月と画面上に明記されているのになぜ慶應四年新春としたのか理解に苦しむ。なお、この木版画では役者名と演目の表示はないので北村の解釈になるが、北村が指示した板東彦三郎は四世ではなく五世であるし、「嫗山姥(こもちやまんば)」は浄瑠璃の演目であり、その一部を切り取って上演した歌舞伎の場合は、演目は「八重桐廓噺」である。
第三に、これは森田も述べているところであるが、いろはかるたの地方色を強調して、名古屋中心に「中京かるた」があったとする説は成立しない。名古屋のわずかな人々がそれを志して試みたことはあったかもしれないが、社会現象としては「中京かるた」は成立していない。
第四に、上方の「いろは譬えかるた」が京都の発祥か、大坂の発祥かという問題である。すでに述べたように、京都を発祥の地とするいろはかるたは存在しない。江戸から京都に行った人が、そこで遊ばれているいろはかるたが江戸のものと違うことに驚いて、京都のかるたとして紹介した例はあるが、それは京都でも遊ばれていた大坂製のいろはかるたのことである。かるたの制作にかかわる様々な点の検討からしても、「いろは譬えかるた」が大坂の発祥であることは疑う余地がない。森田も、一時は京都のかるた屋である任天堂の怪しげな「京都かるた」売り出しの片棒を担いだ鈴木棠三に影響されたのか京都発祥説に傾いていた。後には正しく大坂発祥説に戻ったが危うい話である。後に吉海直人が、今度はもっと怪しい大石天狗堂の「京都かるた」売り出しのお先棒担ぎで考えた京都発祥説に成功できなかったことはすでに触れた。
[1] 伊藤高雄「いろはカルタの比喩―諺の絵画化と江戸文化―」『野州國文學』第七十一号、國學院大學栃木短期大學國文學會、平成十五年、二十五頁。
[2] 北村孝一「江戸いろはカルタ「犬も歩けば」再考」『青淵』平成十八年一月一日号、渋沢栄一記念財団、平成十八年、十六頁。