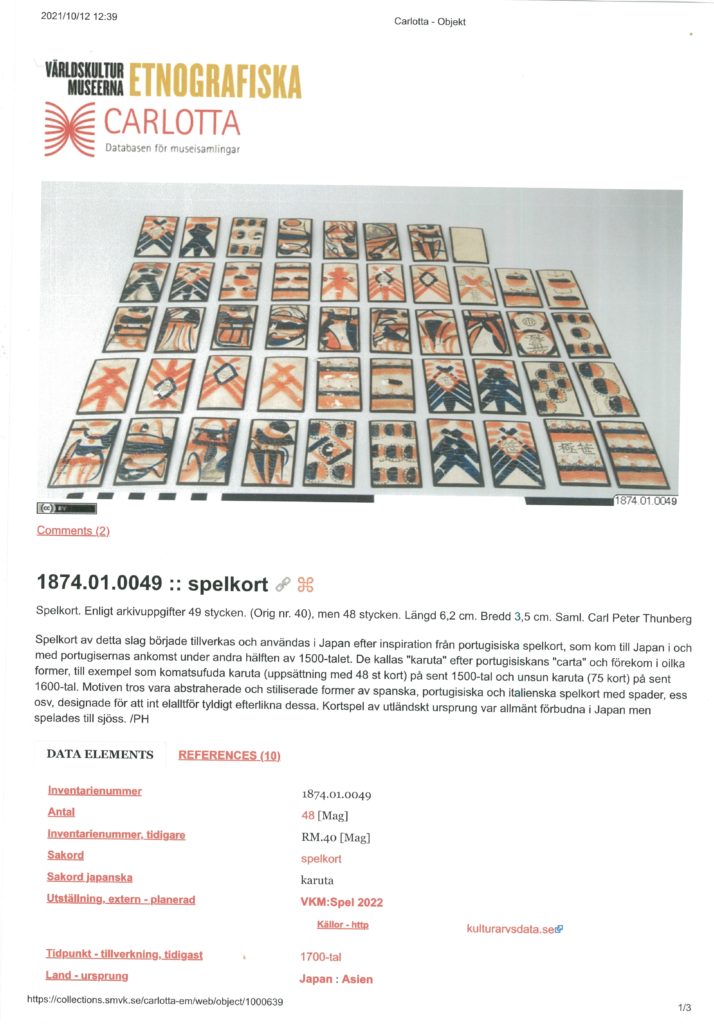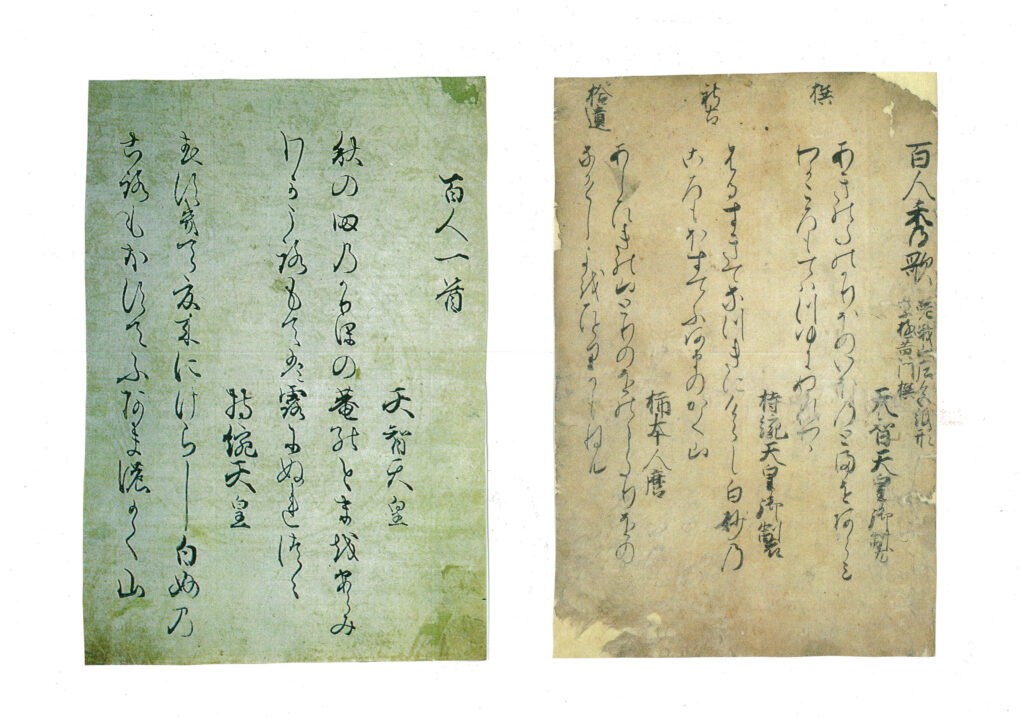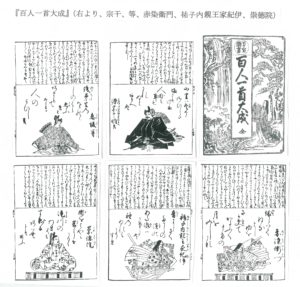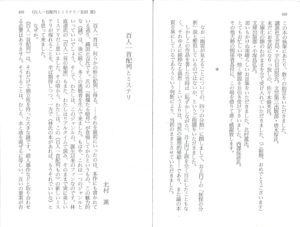六 江戸時代初期の日本国内でのカルタの発展と中国人の関与
ここからは、日本に上陸したカルタにどのような海域アジア文化の母斑があったのか、また、日本人が海域アジアに出かけて行ってカルタの遊技に染まっていったのなら、逆に、中国人が日本に来てカルタを遊び、その発達に貢献したと考えてみてもいいのではないか、という作業仮説で取り組んだ研究の結果を紹介したい。
まず触れたいのが、「シンゴ」と「カブ」である。江戸時代初期には、一組四十八枚のカルタを使う「シンゴ」又は「キンゴ」という遊技と「カブ」という遊技がほぼ同時にあった。前者は配布された札の数字の合計が「十五」だと最高というゲームで、この「シンゴ」はポルトガル語によるものと考えられており、多分ポルトガル由来の遊技であろうと思われる。一方「カブ」は、今日の「カブ札」の最古期の姿であり、「九」が最高の点数である。「九」という数を至上のものとして大事にするのはヨーロッパ文化ではなく中国文化の特徴であり、「九」を勝数としたあたりはいかにも賭博遊技の好きな南方中国人臭いと思う。「九」を「カブ」と発音するのは広東語の訛であるから、これは東アジアのどこかで中国化した「シンゴ」の遊技であろう。ここにも、中国人の影が色濃く存在している。
但し、誤解のないように書いておきたいが、一組四十八枚のカルタが上陸した場所と、一組七十五枚のカルタが上陸した場所の関係は分かっていない。前者が長崎で後者が鹿児島とか、前者は大友氏の城下町臼杵で後者は長崎などと別れていることが立証できればいいのだが、私には解明できなかった。カルタは鉄砲の伝来と同時期に種子島に伝来し、南蛮人の魔術の道具として恐れられたという史料根拠の提示のない説もあったのでずいぶん調べたが結局なにも発見できなかった。だから私は、前者は平戸か横瀬浦か長崎、後者は長崎、つまり基本的には双方とも上陸地点は長崎という可能性が高いと「妄想」している。そして前者は肥前名護屋の軍陣という大消費地で栄え、後者は、通常は数千人、時には数万人も滞在していたという長崎の中国人貿易関係の男性客相手に遊郭で栄えたと考えている。そして、長崎で栄えた一組七十五枚のカルタの遊技は、一組四十八枚のカルタに少し遅れて京都、大坂に伝来し、上流階級の好む遊戯具として発展していったように思える。その段階で画像が改良され、洗練されたかもしれない。
ちょっと話がずれるが、山口吉郎兵衛は、江戸時代初期、前期の「絵合せかるた」をよく蒐集なさっていた。残念ながら山口には、それを基に研究を進めて文章にする時間は残されていなかったので、名著『うんすんかるた』には、何点かの「かるた」についての、目録のような記述しかないが、その中に、「唐(唐土)武者絵合せかるた」という奇妙な「かるた」が含まれている。「山口吉郎兵衛新発見の品種」ということになる。
この「かるた」は、中国史上の勇者、五十人につき、人物を描いた同じ絵のある漢字札と平仮名札で一組になっていて合計百枚、大きさは縦七・九センチ、幅五・五センチ、漢字札、平仮名札とも、表面は紙地銀箔散し、裏面は銀無地だと紹介されている。『うんすんかるた』では「唐武者絵合せカルタ」という表記と「唐土武者カルタ」という表記が併用されているが、どちらも日本製、日本語の名前である。中国語ではこういう表現はしない。勇者はもちろん、唐代の人に限られることなく、各時代から選ばれている。漢字札と平仮名札があるのだから日本国内で制作されたことは確かだが、採録されている中国の武人の中には日本では知られていない人物も相当に含まれており、名前も日本語の漢字にはない中国文字のままという札が多く含まれている。そして肝心の勇者の画像は、ちょっと崩れた日本の鎧兜姿の武者である。中国人が描く中国人の勇者の姿とは違う。つまりこれは、日本人では持て余す、日本製の「絵合せかるた」である。このようなものが日本国内でとてもしっかりと制作され、実際に遊技に供されていたとすると、いったいどこでだれが制作し、だれが遊技したのかが問題である。私は、これなども、長崎の丸山遊郭あたりで中国人客の接待に遊女が活用したものと「妄想」している。
但し、遊技の現場を想像してみるとややこしい。たとえば「韋孝寛」の札の平仮名札は「いかうくわん」である。仮に遊女がこの平仮名札を読み上げると、中国人は「ウェイシアオコワン」か「イケウカン」か、いずれにせよこの日本語読みでは「韋孝寛」と特定できないので札が取れない。「諸葛亮」は「しよくわつりよう」と読まれるから「ジューガーリャン」と憶えている中国人には誰のことだかさっぱり分からない。遊女が馴染客にだけヒントを出したり、広東語の分かる遊女が平仮名札を手にしているのに怪しげな広東語で読み上げたり、客のしたお手付きの罰盃が回されたり、そこに生じるドタバタ劇も笑いの渦も、遊郭の宴席の余興であるからそれはそれで楽しいかもしれないが、ゲームの進行としてはややこしい。
これはほんの一例であり、他に、山口の著書『うんすんかるた』には、山口が蒐集して滴翠美術館に保管されている、江戸時代初期、前期の「漢詩カルタ」であるとか、「二十四孝絵合せカルタ」であるとかいう中国っぽいカルタが数種類、記録されている。私は、江戸時代初期、前期のカルタについて、しっかりした品質のものが相当の量で制作されていたと考えられるときには、そのカルタはどこで制作され、どこで消費されたのかを考えることにしている。そうすると、この中国人でないと読むことさえできないようなカルタへの国内生産を促すような需要が長崎のような開港都市にあったとすれば、中国文化の匂いの強い一組七十五枚の「うんすんカルタ」は、遊技で使われる言葉は数が少なく、日本人、中国人の間では一層使いやすく、大きな需要があったのではなかろうかと「妄想」している。この「妄想」から、私は、おそらくは日本の研究者としては初めてだと思うが、初期の「うんすんカルタ」の消費地として長崎、丸山遊郭とその周辺を考察の範囲におさめて考えるようになった。
いずれにせよ、まったく未知の海外文化であったカルタの遊技は、日本国内のどこかに中心的な消費地ができて、そこでそのカルタのゲームが多くの人々によって繰り返し試されて、少しずつルールが成熟していき、その中で多くの人々に支持された遊技法、ルールが徐々に標準化して拡散していくというプロセスで定着したのであろう。この中心的消費地こそが、そのカルタ遊技の手順だとか、禁則だとか、遊技法が徐々に変化して発展してゆく苗床であり、ここで多くの人間によって集中的に繰り返し遊ばれて慣らされないと、一定の遊技法が大方の理解を得て標準化するプロセスが起りにくい。少し後の江戸時代中期の「めくりカルタ」でも、最大消費地は江戸、吉原遊郭であったので、そこで考案された「吉原の役」というものがあって、吉原発祥のルールが、遊郭の外、江戸の一般の町内でも使われて普及したと思わせる史料がある。だから、根拠の弱い「妄想」であっても、主要な生産地と中心消費地をどこに想定するのかという点が、大きな絵としてはどうしても押さえておきたいポイントである。
こういう私でも、かつては、伝来一か所説を疑いもせずに従っていたので、同じ経路で日本に来たのに、カルタはなぜ一組が五紋標七十五枚のものと四紋標四十八枚のものに分れ、手描きと木版に分れ、カルタ用語や札の呼称が分かれ、カルタ札の大きさの違いが生じたのか。この違いが説明できないことにずいぶん悩まされた。ただ、一組四十八枚の「カルタ」に溢れるヨーロッパ文化の香りと、一組七十五枚の「うんすんカルタ」に現れる中国文化の香りとを感じ取っているうちに、もしかしたらこれは、異なった経路で伝来し、異なった消費地で栄えたのではないかと思うようになり、そうこうするうちに飛膜のある「ドラゴン」と火を吐く「火龍」の違いを発見して決定的に改説したのである。
こういう私の考えからすると、黒宮さんが紹介しているフランスの研究者、ドゥポリスの説は、やはり旧来の伝来一か所説の安心安全なプールの中で泳いでいるもののように見える。黒宮さんのご研究によると、ドゥポリスは、日本の一組五紋標七十五枚の「うんすんカルタ」の遊技法の進歩を巻き戻して一組四紋標四十八枚の「カルタ」でおこなってみると、日本に伝来した「原ウンスン」の遊技法にたどり着くとしたそうである。これはとても面白い発想だと感心するが、私は彼の考えとはちょっと違っていて、一組五紋標七十五枚の遊技を巻き戻すとしたら、それは日本人の知恵ではなく、海を越えて東南アジアの中国人社会の知恵と工夫に帰着すると思っている。この違いは、「うんすんカルタ」を見たときに、そこにヨーロッパ人らしく日本らしさを感じるのか、東アジア人であるのでより詳細に見て日本らしさと中国らしさの混交を見出せるかの違いに由来すると思われる。ドゥポリスには、中国の官僚を描いた札も、中国の火龍を描いた札も、日本らしいと見えたのではないかと「妄想」している。日本社会史、日本文化史に詳しい研究者でであれば、こんなに中国臭いものを純粋に日本国内で考案された日本遊技文化の結晶とは考えないと思う。
これまで日本の研究者は、「うんすんカルタ」の第五の紋標が日本の「巴(ともえ)」であることや、五枚ある「ウン」の札の図像が日本化された七福神のメンバーに達磨を加えたものである点などから、このカルタは、海外から伝来した一組四十八枚のカルタを基に、日本で考案されたものだと理解していたが、それが前提とする「一か所伝来説」が崩れると、複数経路での伝来が想定され、現在残されている江戸時代中後期の「うんすんカルタ」カードの、たとえば女戦士であった「ソウタ」が優雅に踊り、あるいは楽器を奏でるしとやかな女性(遊女)の「ソウタ」に代わってしまったように、日本的な特徴の濃い図像は、最初から一組五紋標七十五枚の形で中国系社会から伝来してきたカルタの一部の図柄が、日本上陸後に日本のかるた屋の工房の工夫で日本色を強めたものであって、このカルタの出自を物語るものではないと考えられるようになる。
ここで、伝来したカルタの需要はどこにあったのかを整理して確認しておこう。一組四紋標四十八枚のカルタについては、ポルトガル船の来航した平戸、横瀬浦、長崎などの町の人々、さらには朝鮮の役で動員されて肥前、名護屋の軍陣にいた人々が想定される。カルタには、初期の宣伝文句であろうか、「軍陣心休楽」であるという謎めいた言葉が伝わっている。だが、手描きの「うんすんカルタ」の愛好者のほうは従来のかるた史研究の成果ではうまく想定できない。黒宮さんはどのような人々を想定しているのだろうか、などと聞いてみたくもなる。一方的にお聞きするだけでは失礼なので根拠の裏付けが薄い私の「妄想」を紹介すると、もう何度も述べたことを繰り返して恐縮だが、私は、中国人の商売人が多数渡航して長期間滞在していた肥前、長崎の歓楽街、丸山遊郭や周辺のお茶屋、そして唐人屋敷などでの活用があったと考えている。
近年、江戸時代史の研究が進展して、鎖国の時期の長崎は東アジアで唯一、売春が公然と認められていた都市で、そこには、貿易船で来航して商売をして大儲けした中国商人たちが多数、時には数万人も帰国せずに長期に滞在していて、懐中で唸っている大儲けした財貨を浪費して遊楽、悦楽に明け暮れたことが明らかになってきた。江戸幕府、長崎奉行所はもちろんこれを承知の上で収入源として大事にして、丸山遊郭からの唐人屋敷への遊女の派遣も、逆に唐人の丸山遊郭への来訪も、また、丸山遊郭周辺のお茶屋での唐人の遊興も、表面は禁止あるいは制限されていたのだが、渡すものを渡せば大歓迎であったのだろう。
長崎といえば、以前は、この地域に残る、異国情緒のある建造物や料理や芸能、祭りの踊りなどの伝統が、南蛮文化とされ、遠く海外の文化への憧憬(しょうけい)が生んだ異国風文化といわれていたが、今考えれば、そのようにロマンチックな夢物語ではなく、現実に目の前にうろうろしている、交易の利益で懐の温かい中国人たちが出入りする遊郭があり、そこでの飲食、接待という極めて現実的な、しかも想像を絶するほどに巨大な利益を産んでいる商売のチャンスがあって、料理にせよ、酒類にせよ、芸能にせよ、性的接待にせよ、利益が見込まれるチャンスは大きいので、このような中国人上客が遊ぶ席の魅力が増すように、中国風の料理や音曲、舞踏、余興などと同様に中国風のカルタ遊技も工夫されて、中国人好みの「絵合せかるた」や、この「うんすんカルタ」が好んで使われたのではないかと考えている。また、そのために、長崎かその近辺で、手描きで、中国化している部分もある画像のカルタの制作があったのだろうとも思っている。もちろん、ここだけでということはないのであって、他の場所でも一組五紋標七十五枚のカルタは遊ばれていたと思うが、当時の日本社会では、鎖国下の長崎での貿易に伴う遊興は他の地域での消費行動をはるかに圧倒する巨大な需要であり、そこでの中国人の愛好も「うんすんカルタ」の盛行に貢献したと考えている。こういう発想にたどり着いたのには山口吉郎兵衛の蒐集品を見ることが大いに役立ったのであり、たった一人で闘って貴重な物品史料を残してくれた山口に感謝している。ちなみに、当時長崎に居たオランダ商館の関係者も相当自由に町中に出入りしていた記録があるが、全体的にはオランダ人は、中国人ほどは金持ちではなかったように見える。